黒ボク土ブドウ園における長期の有機物連用および草生栽培による土壌全窒素の増加
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
黒ボク土ブドウ園では、土壌全窒素増加が最大となる値の80%に達する期間は、オーチャードグラス全面草生栽培で9年、バーク堆肥3t /10a連用で11年、牛ふん堆肥3t /10a連用で18年である。草生栽培で、施肥窒素が刈草を経由して土壌全窒素となる割合は、17年目で20%に減少する。
- キーワード:黒ボク土、土壌全窒素、牛ふん堆肥、バーク堆肥、草生栽培
- 担当:果樹研・果実鮮度保持研究チーム
- 代表連絡先:成果情報のお問い合わせ
- 区分:果樹・栽培、共通基盤・土壌肥料
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
堆肥等の有機物施用により土壌有機物が増加して地力の増進が図られること、草生栽培により施肥窒素が草に吸収され刈草として土壌に還元されることで窒素溶脱が軽減することはよく知られている。しかし堆肥施用により土壌全窒素が最大に達するまでの期間や、草生栽培で土壌全窒素の増加による窒素溶脱軽減が期待できる期間については明らかにされていない。そこで、黒ボク土ブドウ園において有機物連用と草生栽培を長期間継続し、窒素収支算定の基礎となる土壌全窒素の増加する期間を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 黒ボク土のブドウ園で清耕栽培区、草生栽培区、牛ふん堆肥区(モミガラ混合牛ふん堆肥、年間3t/10a施用)、バーク堆肥区(年間3t/10a施用)を設けて24年間継続した場合、表土(深さ0~30cm)の土壌全窒素は、清耕区でほぼ一定であるが、牛ふん堆肥区とバーク堆肥区および草生栽培区では、清耕栽培区より土壌全窒素が高い値で維持される(図1)。
- 表土の全窒素の推移は指数関数モデルがあてはまる(図1)。
- モデル式から、土壌全窒素増加最大値(ΔNmax)の80%に到達する期間を求めると、草生栽培区で9年となり、草生により施肥窒素のかなりの割合が草に吸収され、刈草となり土壌に還元されて蓄積していると推定される。有機物連用では、堆肥由来窒素が27kg/10aであるバーク堆肥区で11年となり、堆肥由来窒素が23kg/10aである牛ふん堆肥区では18年である。これ以降の連年継続による土壌全窒素増加の効果は少ない(図1)。
- 草生栽培区の1年当たりの土壌窒素増加量/窒素施肥量の割合が50%となる期間は12年、20%となる期間は17年となる。施肥窒素から、土壌窒素増加量と、収穫物やせん定枝で園外への持ち出し分(27kg/10a)を差し引いた値が、溶脱可能な窒素と考えられるので、この期間を過ぎると、草生栽培による溶脱軽減効果は十分に期待できない(図2)。
- 有機物連用区の1年当たりの土壌窒素増加量/有機物由来窒素投入量の割合が50%となる期間は牛ふん堆肥区で7年、バーク堆肥区で11年となり、20%となる期間は牛ふん堆肥区、バーク堆肥区いずれも17年と推定される(図2)。
成果の活用面・留意点
- 本成果は、黒ボク土ブドウ園の有機物連用による堆肥中窒素を評価した窒素減肥および草生栽培による窒素溶脱軽減効果の算定に用いることができる。
- 黒ボク土ブドウ園は各区面積3a、開始時の樹齢6年生、品種:キャンベル・アーリー、栽植密度20本/10a(11年目以降は間伐実施)、成園後の平均収量2.1トン/10a、剪定法は長梢剪定である。
- 上記データは、清耕栽培区(施肥窒素年間平均8.3kg/10a施用、除草剤を用いて雑草の発生を抑制)、草生栽培区(オーチャードグラス全面草生、施肥窒素年間8.5 kg/10a、年3回程度草刈り)、牛ふん堆肥区およびバーク堆肥区(両区ともに有機物とは別に施肥窒素年間6.9kg/10a施用、有機物は11月下旬に地表面散布、断根の影響を避けるため深さ10cm程度に軽く耕起)として、24年間継続管理して得られた結果である。
具体的データ
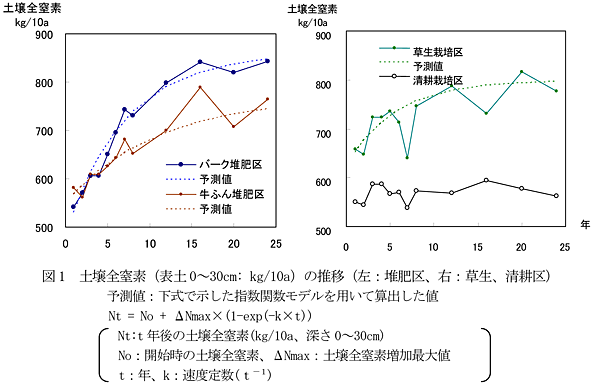
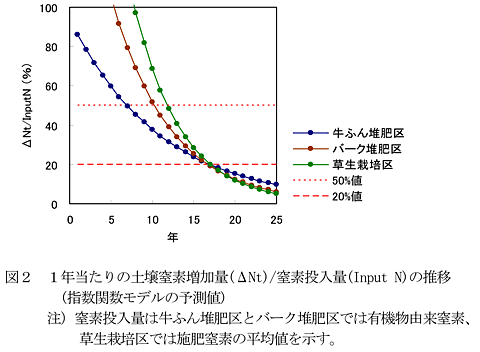
その他
- 研究課題名:果実の輸出等を促進する高品質果実安定供給のための基盤技術の開発
- 課題ID:313-a
- 予算区分:基盤研究費(1979~2005年度は経常予算)
- 研究期間:2006~2008年度 (地表面管理・有機物長期連用試験は1979年度から開始)
- 研究担当者:梅宮善章、井上博道
