産直における消費者へのメッセージ伝達モデル
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
産直による産消交流では、消費者へのメッセージとなる農産物の特性を流通過程で維持することと、その特性を定める栽培ガイドラインなどの規則(コード)を産消が共有することが必要である。そこでこれらの条件を論理式で記述したメッセージ伝達モデルを開発した。
- 担当:北海道農業試験場・総合研究部・農村システム研究室
- 連絡先:011-857-9309
- 部会名:総合研究(農業経営)
- 専門:経営
- 対象:
- 分類:研究
背景・ねらい
近年、都市在住の消費者から様々な形で農村との交流に対するニーズが強まっている。なかでも産直は、流通経路も多様化し取扱高も拡大傾向にある。但し、 これらの産直の中には交流ではなく単なる流通にとどまっている例も多く見られる。そこで、どのような場合に産直が生産者と消費者の交流となるのかを解明す ることが求められている。この課題では、産直におけるメッセージ伝達モデルを開発し、問題の発見および解決に役立つ方策を提示する。
成果の内容・特徴
- メッセージ伝達モデルの概要:このモデル式Fは、産直において生産者が農産物の特別な性質をメッセージとして消費者に伝えるためには二つの条件が必要であることを示している(図1)。その条件(式F-1と式F-2)は以下のような内容である。
①ある産直品が例えば「市場流通品より安全である」という特別な性質を持っていることを消費者に理解してもらうためには、そのメッセージ(Me)の媒体 (Ma)となる農産物(x)が収穫の時点(t0)で持っていた安全性という性質を、消費者の手に渡る時(tn)まで維持しなければならない(式F-1)。
②配送された農産物から消費者が読み取るメッセージは一つとは限らない。例えば減農薬農産物の虫食いの跡を「安全性」ではなく「規格外」とみなすことも ある。そこで農産物の「安全性」に関する栽培ガイドラインのように、ある媒体からメッセージを一つだけ選ぶ規則(コード)を取り決め、生産者(A)が農産 物にメッセージを与える際に従ったコード(Co1)と同じコード(Co2)を消費者(B)も所有(h)する必要がある(式F-2)。 - モデルの事例への適用1(条件を二つとも満たしているケース):生産者アンケートの結果、彼らの産直品に対する評価が3つのグループ(I安全性、II 一般的品質、III価格)に分類された産直において、5段階評価で4点以上を獲得した「安全性」が生産者からのメッセージと判断できる(図2)。 このメッセージに関しては、流通過程で安全性が維持され(式F-1)かつ栽培ガイドラインの取り決めがある(式F-2)ので、二つの条件はともに満たされ ており、交流は成立していると予想される。実際、消費者アンケートでもこの「安全性」というグループは4.58と高い評価を得た。これら両者の平均の差に ついて検定を行ったところ、メッセージは消費者によって確かに受け取られていることが確認された(表1)。
- モデルの事例への適用2(片方の条件を満たしていないケース):生産者が産直品に5つのメッセージ(安全・安心・新鮮・美味・安価)を与えている事 例において二つの成立条件を調べた結果、「安価」というメッセージに関してだけはコードが存在しておらず、式F-2を満たしていなかった。すなわちこの産 直では春の契約時に全体として農業経営が成り立つように作物ごとの価格を固定しているので、実際に品物が届く頃の市況によっては「価格が安い」と言えない 場合もあり得る。そこでこのメッセージは産消間で共有されていないと推測できる。現実にアンケート結果からも、生産者が期待するほど消費者はこの点につい て評価していないことが明らかとなった(表2)。
成果の活用面・留意点
このモデルを用いることで交流の成立していない事例の問題点を指摘し、改善方向を示すことができる。ただしこれは生産者から消費者へメッセージを伝達する過程に限定されるので、消費者からの反応については別途検討を行う。
具体的データ
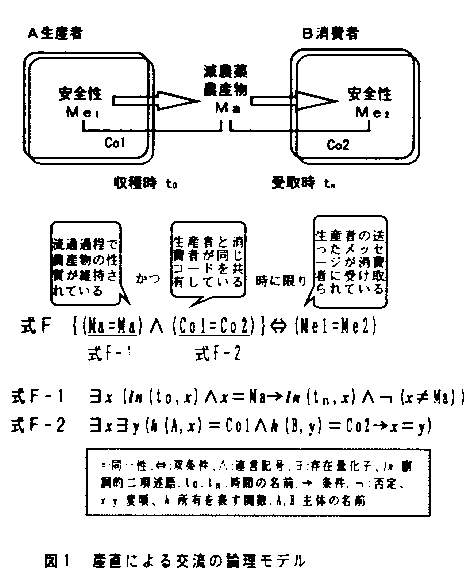
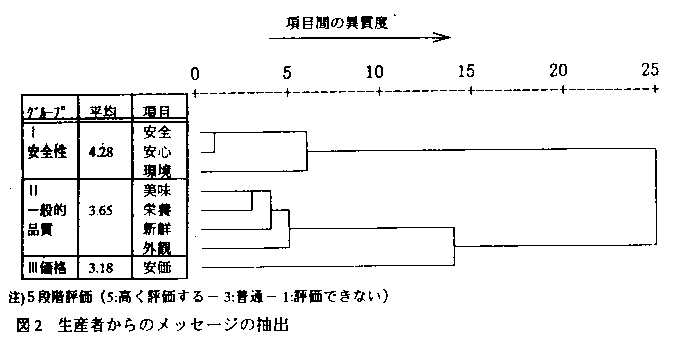
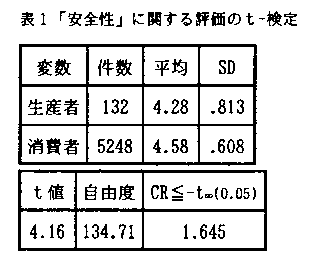
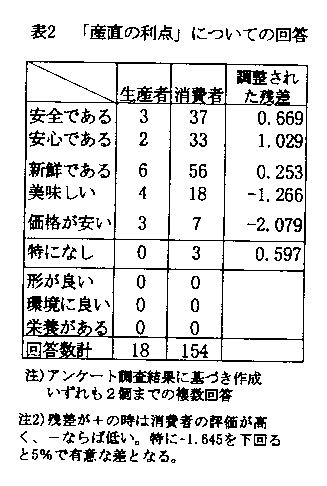
その他
- 研究課題名:農産物を媒介とする産消交流の成立条件の解明
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成8年度(平成6~8年)
- 研究担当者:森嶋輝也-->
- 発表論文等:産直における産消交流の論理モデルとその確証、農業経営通信 No.189
生協産直によるコミュニケーションの成立条件と課題、農業経営研究成果集報 第14号
