動向予測による2010年の大規模畑作経営タイプ
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
大規模畑作地帯の農業構造を動向予測した結果、2010年において、普通畑作基幹型経営、野菜作導入型経営、野菜作基幹型経営、という3つの典型的なタイプの畑作経営が想定された。
- 担当:北海道農業試験場・総合研究部・動向解析研究室
- 連絡先:011-857-9308
- 部会名:総合研究(農業経営)
- 専門:経営
- 分類:研究
背景・ねらい
大規模畑作地帯を巡る環境が著しく変化するもとで、地域農業の将来像の予測とそれに対応した技術開発が求められている。そのため、北海道・十勝管内の畑作農家を対象に、農業センサスデータを用いた推移確率分析により、2010年までの農業構造を予測し、開発技術の受け手となるような担い手層を想定した。
成果の内容・特徴
- 農家数減少のもとで規模拡大が進み、モード階層は2010年には30~35haに移動し、50ha以上が畑作農家の11.6%(385戸)占める。ただし、現在のモード階層も12.8%(424戸)を占め、労働市場が不変であれば、専業的な経営が多数存在すると考えられる(表1)。
- 次に、畑作農家を1990年の経営規模で3つに区分し、1戸あたり基幹的農業従事者数別の農家割合を予測すると、40ha以上の大規模層と20~40haの中規模層は、同3人以上の農家が半数以上を占めるが、20ha以下層では同2人未満の農家が約30%を占める(図1)。
- 同様に、経営面積に占める野菜作付面積率別の農家割合を予測すると、40ha以上層では野菜作付が増加傾向にあるが、非作付農家は約50%で、作付率5%未満を加えると70%になる。20~40ha層では、最も増加傾向が強く、同5%以上の農家が約40%を占める。20ha以下層では、同30%以上の野菜作を基幹とする経営が一定数存在すると予測される(図2)。
- 以上の結果から、2010年における大規模畑作の技術開発のための典型的な畑作経営は、以下の3つのタイプが想定できる。
1)普通畑作基幹型経営:大規模畑作の担い手としての50ha以上層の経営で、3名以上の基幹的農業従事者が主体で、普通畑作を中心とする作付構成が展開する。
2)野菜作導入型経営:モード層をなす30~40ha層の経営で、3名以上の基幹的農業従事者が主体で、普通畑作に加え野菜作面積が経営面積の10~20%を占める。
3)野菜作基幹型経営:経営面積25ha以下層のうち、3名以上の基幹的農業従事者を保有する経営が主体で、野菜面積率が30%以上を占め、野菜作への依存度が高い。
成果の活用面・留意点
技術開発研究の対象・目標設定に活用できる。ただし、北海道・十勝管内の家族経営を対象にした、開発技術の受け手としての担い手である。
具体的データ
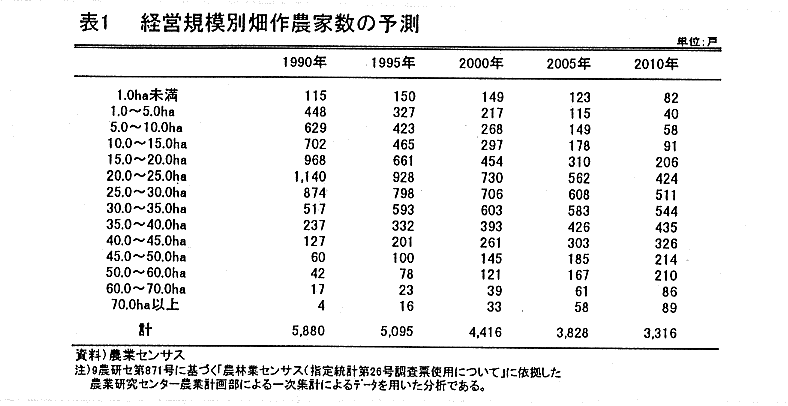
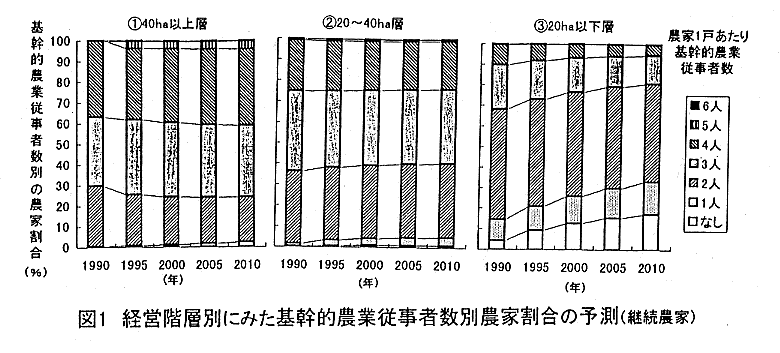
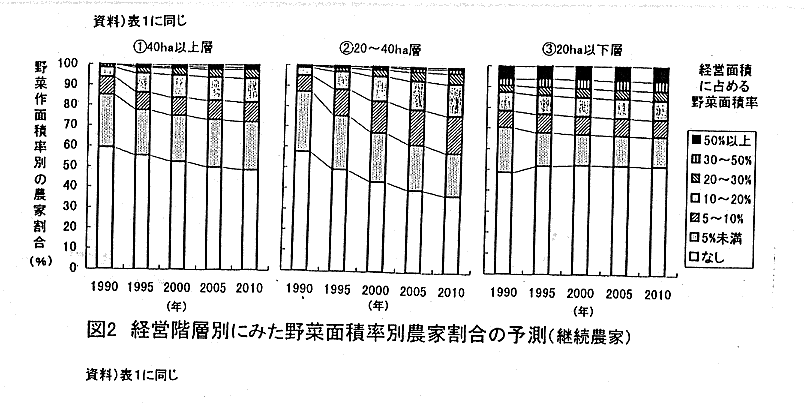
その他
- 研究課題名:大規模畑作地帯における農業生産動向解明による技術開発ニーズと
開発技術の導入可能性評価 - 予算区分:実用化促進(地域総合)
- 研究期間:平成9~11年
- 研究担当者:杉戸克裕、鵜川洋樹、天野哲郎、森嶋輝也、藤田直聡
- 発表論文等:「十勝畑作農業の動向予測と技術開発方向」,
平成11年度農林水産業北海道地域研究成果発表会講演要旨,pp1~9.
