夏まき緑肥の導入によるとうもろこしのアーバスキュラー菌根菌感染率と生育の改善
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
アーバスキュラー菌根菌と共生しない作物を収穫した後、菌根菌共生作物を夏まきの緑肥として導入することにより、翌年に栽培する後作とうもろこしのアーバスキュラー菌根菌感染率、生育が改善される。
- 担当:北海道農業試験場・生産環境部・養分動態研究室
- 連絡先:011-857-9243
- 部会名:生産環境
- 専門:肥料
- 分類:研究
背景・ねらい
アーバスキュラー菌根菌(菌根菌)共生作物の栽培は土壌中の菌根菌密度を増加させ、翌年に栽培した菌根菌共生作物の菌根菌感染率を高める。これにより、後作物のリン吸収が促進され、その生育、収量が向上する。しかし、輪作体系の中には、非共生作物の作付けも組み込まれている。そこで、菌根菌非共生作物の収穫後から降雪までの期間に、菌根菌共生作物を緑肥として導入することにより、翌年に栽培する作物の菌根菌感染率および生育、収量を改善できるか検討する。
成果の内容・特徴
- とうもろこしの生育(播種64日目の地上部乾物重)は、前作物跡地を春まで裸地にするよりも、ひまわり、ベッチ(菌根菌共生作物)を緑肥として導入した後で優れる。一方、シロガラシ(菌根菌非共生作物)を緑肥として導入しても、後作とうもろこしの生育は改善されない(図1)。この原因の一つには、とうもろこしの菌根菌感染率の違いが考えられる(図1)。また、各緑肥作物のすき込みの有無よりも緑肥作物の種類がとうもろこしの生育に大きな影響を及ぼす。
- ひまわりの導入による後作とうもろこしの菌根菌感染率・生育の改善は、ひまわりを8月に播種した場合に認められる(図2)。9月9日以降の播種ではひまわりの導入効果は認められない。これより、アブラナ科野菜やそば等の栽培期間が短い非共生作物後で、緑肥導入効果が期待できる。
- とうもろこしの地上部乾物収量は、菌根菌共生作物であるひまわり、ベッチの導入により改善された。緑肥導入の影響は、収穫時期には小さくなる(図3)が、初期生育の促進のほか、安定生産のためには、菌根菌共生作物の導入が有効と考える。
成果の活用面・留意点
- 本試験圃場の有効態リン酸は18 mg/100 g、とうもろこしへのリン酸施用量は10kg/10aである。
- 菌根菌を考慮にいれた栽培順序を構築する際の判断材料となる。
- 新たに緑肥を導入する時に、緑肥作物の種類を選定する際の参考とする。
- 各緑肥作物について、土壌病害、線虫密度などに及ぼす影響も検討する必要がある。
具体的データ
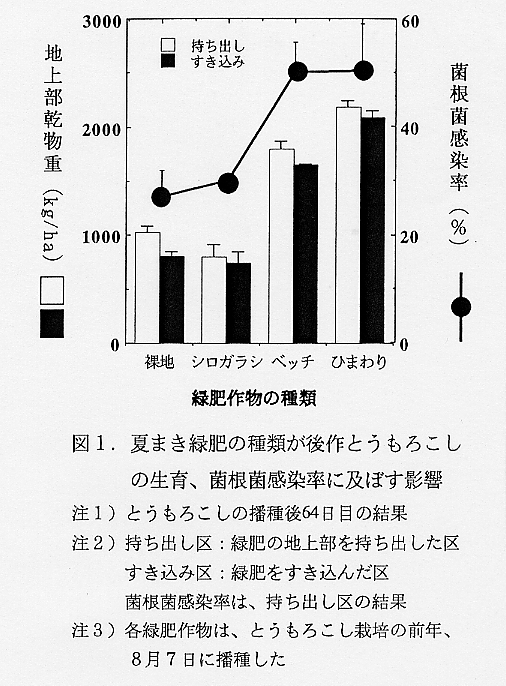
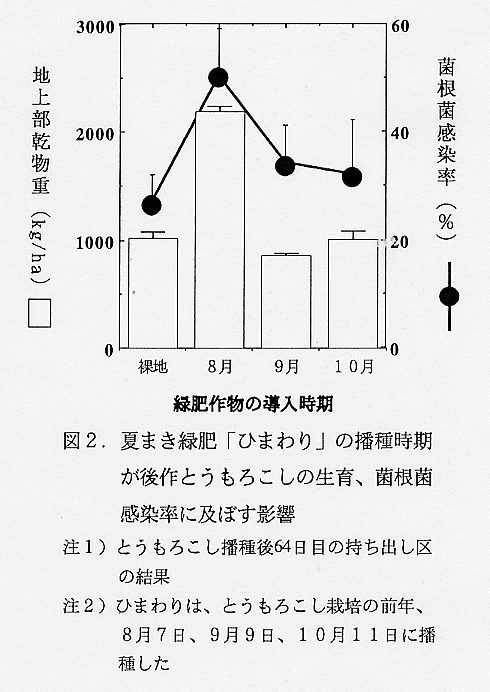
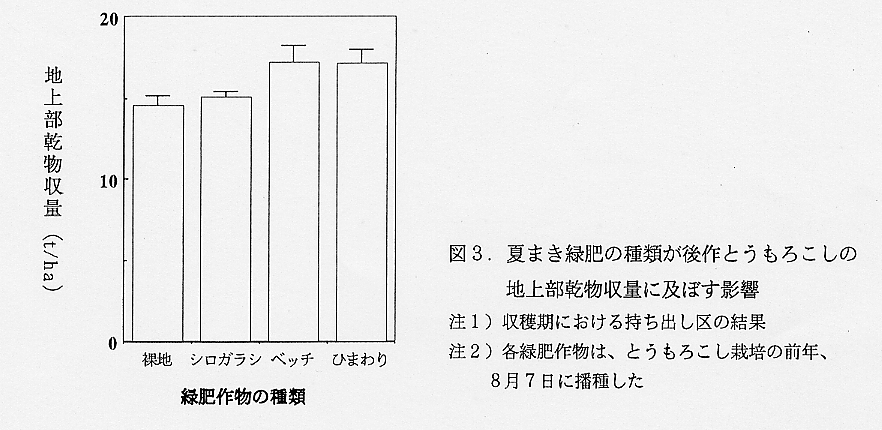
その他
- 研究課題名:寒地型作物の土壌肥沃度改善効果の検定と評価
- 予算区分:大型別枠(新需要創出)
- 研究機関:平成11年度(平成10~12年度)
- 研究担当者:唐澤敏彦、建部雅子、笠原賢明
- 発表論文等:夏播き緑肥の導入が後作トウモロコシの生育とアーバスキュラー菌根菌感染率に及ぼす影響、
土壌肥料学会講演要旨集、45、336
