秋まき小麦「きたもえ」、「北海257号」の追肥窒素吸収特性と子実蛋白質含有率
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
「きたもえ」、「北海257号」とも葉面施用窒素の利用率とその子実分配率が高く、「きたもえ」では幼穂形成期に施用した土壌表面追肥窒素の子実への分配率が高い。従って、「きたもえ」では窒素の葉面施用と幼穂形成期の多肥が子実蛋白質含量を限界以上に高める危険がある。一方、製パン用の「北海257号」には葉面施用は有効な追肥法である。
- キーワード:「きたもえ」、「北海257号」、窒素利用率、子実分配率、葉面施用、子実蛋白質含有率
- 担当:北道研・畑作研究部・生産技術研究チーム
- 連絡先:0155-62-9274
- 区分:北海道農業・生産環境
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
小麦の民間流通化の下では、高品質の小麦生産が求められており、品種特性に応じた蛋白質含有率の制御技術の確立が急がれている。そこで、北海道の麺用新品種「きたもえ」と開発中の製パン用新系統「北海257号」の追肥窒素の利用特性について、「ホクシン」を基準に明らかにする。
成果の内容・特徴
- 麺用新品種「きたもえ」の特性
1)土壌表面施用した追肥窒素の利用率は「きたもえ」と「ホクシン」でほぼ同様であるが、子実への分配率は「ホクシン」より「きたもえ」で高く推移し、特に幼穂形成期に明瞭である(図1)。
2)出穂またはその直後に葉面施用した窒素の利用率は「ホクシン」、「チホクコムギ」の62%、49%に比べて「きたもえ」は70%と高く(表1)、同時期の土壌表面施用窒素の利用率40~50%(図1)に比べて高い。
3)麺用小麦として原粒蛋白含量10~11%が求められる「きたもえ」の生産には「ホクシン」同様に葉面施用は危険であり、幼穂形成期の土壌表面への多肥も「ホクシン」以上に原粒蛋白含量を上昇させる可能性があり、適性施肥の遵守が重要である(表1)。 - パン用新系統「北海257号」の特性
1)「北海257号」における葉面施用窒素の利用率は67~87%と高く、2000年産では「ホクシン」の約1.4倍である(図2)。
2)出穂の前・後に葉面施用した窒素の利用率は、出穂前のほうが10%程度高く、その子実への分配率はともに80%程度と高い(図2)。
3)窒素の葉面施用は同時期の土壌表面施用(利用率40~60%程度)より利用率が高く、パン用小麦として原粒蛋白含量13%以上が求められる「北海257号」の生産に有効な追肥法である(表2)。
成果の活用面・留意点
- 「きたもえ」、「北海257号」の施肥体系構築とその遵守を指導するための基礎資料となる。
- 土壌表面施用窒素の利用率は土壌の種類や降雨などの気象条件により大きく変動する可能性がある
平成13年度北海道農業試験会議(成績会議)における課題名および区分「秋まき小麦「きたもえ」、「北海257号」の追肥窒素吸収特性と子実蛋白質含有率」(技術・参考)
具体的データ
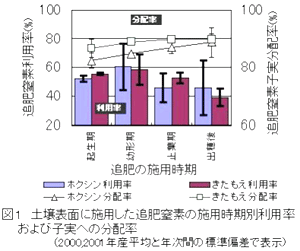
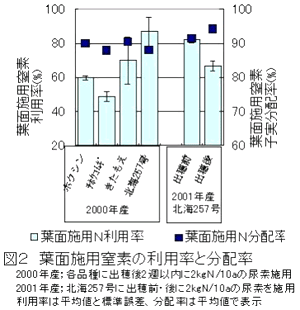
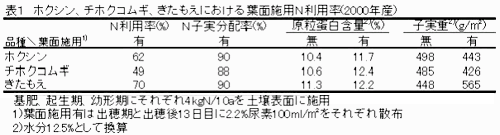
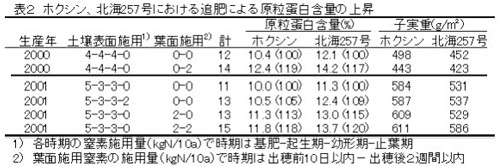
その他
- 研究課題名:秋播コムギ品種系統における窒素吸収・転流特性と蛋白含量
- 予算区分:麦緊急開発、21世紀プロ
- 研究期間:1998~2001年度
- 研究担当者:辻博之、中野寛、山縣真人
- 発表論文等:Hiroyuki Tsuji, H. Nakano, M. Yamagata(2001)Proceedings of 6th ISRR. :372-373
辻、中野、山縣(2001)日作紀70(別2):35-36
