降霜確率にもとづく作物初霜害のリスクマップ
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
北海道の任意地点の初霜日の平年値や、3年~30年に1回の確率で来る、季節はずれに早い初霜日が何月何日かを推定できる。これと発育モデルを組み合わせて大豆の初霜害リスクマップを作成し、初霜害リスク情報を提供する。
- キーワード:初霜害、リスク、マップ、メッシュ
- 担当:北海道農研・生産環境部・気象資源評価研究室
- 連絡先:電話011-857-9234、電子メールsame@affrc.go.jp
- 区分:北海道農業・生産環境 共通基盤・農業気象
- 分類:技術・普及
背景・ねらい
初霜害は作物に甚大な被害を与えるので、栽培スケジュール策定に際しては初霜害に関する支援情報が必要である。そこで、「○月×日に播種すると、△年に一度の確率で初霜害に遭う」というリスク情報推定手法を開発する。この手法を適用して、大豆「ユキホマレ」の初霜害リスクマップ(1kmメッシュ)を作成し、初霜害リスク情報を普及所等指導機関に提供する。この品種では水稲の移植作業との競合を避けて移植後に播種する作業体系が採用されており、遅い播種期が設定されるので初霜害回避の考慮が重要である。
成果の内容・特徴
- 以下の手法により作成した、「ユキホマレ」の初霜害リスクマップが利用できる。
1)北海道各地の気象台の最近30年間の初霜日の記録から、初霜日の平年値や、3年、5年、10年、20年、30年に
1回の確率で来る、季節はずれに早い初霜日がいつであるかを調べる(再現期間がk年の早い初霜日と呼ぶ)。
2)再現期間がk年の早い初霜日の、日最低気温平年値(Tmin)を調べ、図1の関係を求める。図1の関係を利用
すると、任意の再現期間(k)、例えば10年に1回の確率の季節はずれに早い霜が、何月何日であるかを、Tminから
推定できる。任意地点のTmin(日別値)は、メッシュ気候値CD-ROM(気象庁)の月別値を調和解析することにより
得られる。
3)さらに、ある日(x)より早く初霜日が来る確率(F(x))が、次式により推定できる。これにより、例えば10月1日までに
初霜が来るのは何年に1回の確率かを推定できる(pとqはパラメータ)。
F(x) = 1 / k = 1 / ( exp( (Tmin - p) /q ) ) (1)
4)一方、ある播種日を設定して、その日からの毎日の平年気温を作物発育モデルに入力すると、成熟日を推定する
ことができる。その成熟日以前に初霜日が来る確率として、作物が初霜害に遭うリスクを評価できる。
5)以上を統合すると、図2に示すフローにより初霜害リスクマップを作成できる。 - 5月20日から6月10日までの間に5回の播種日を設定して作成した「ユキホマレ」の初霜害リスクマップを比較すると(図3に一例、その他図略)、播種期によるリスクの相違、たとえば岩見沢を中心とする地域に注目すると、6月5日の播種ではリスクが10~20%の地域が広いが、6月1日の播種だと10%以下の地域が広がり、5月25日まで播種を早めると地域一帯のリスクが10%以下となること等を容易に把握できる。
成果の活用面・留意点
- 任意の再現期間の早い初霜日の推定方法は、北海道全域へ適用可能である。
- 初霜害リスク評価法は、大豆以外にも適用可能な作物がある。
- メッシュ区画内の凸凹などに起因する霜穴や霜道は考慮していない。
具体的データ
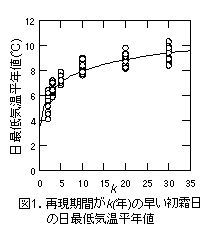
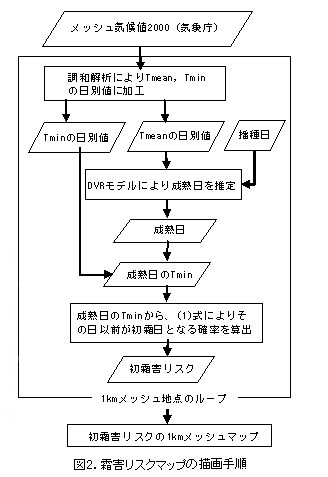
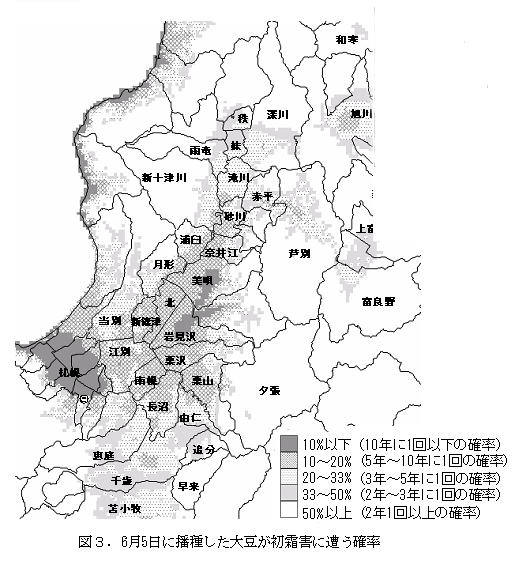
その他
- 研究課題名:生育初期の低温条件に注目した作物の温度反応の解析
- 課題ID:04-06-05-*-01-04
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2000~2004年度
- 研究担当者:鮫島良次、濱嵜孝弘、廣田知良
- 発表論文等:Sameshima et.al.(2004).J.Agric.Meteorol.60:865-868.
