泌乳初期の乳牛の採食量は第一胃内容量による物理的制約を受ける
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
泌乳初期の乳牛の採食量は、第一胃内容量に制約を受け、上限に近い第一胃内容量になると、濃厚飼料主体飼料では摂取量の低下は小さく、粗飼料主体飼料ではその低下は大きくなる。
- キーワード:飼料摂取量、第一胃内容量、泌乳初期、乳用牛、家畜生理
- 担当:北海道農研・畜産草地部・上席研究官、家畜生理繁殖研究室
- 連絡先:電話011-857-9269、電子メールmmurai@affrc.go.jp
- 区分:北海道農業・畜産草地、畜産草地
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
乳牛の泌乳初期では、乳生産の急激な増加で必要とする栄養量は摂取飼料量ではカバーしきれず、乾乳期の体蓄積を取り崩しながら乳生産を行っているが、近年の高泌乳化はこの傾向を一層顕著にしている。また、分娩前後のホルモンバランスの変化で、摂取栄養素・エネルギーの配分・制御変調が要因とされる採食量の減退や停滞が生じる。一方、消化生理機能の亢進・安定には、この時期も一定程度の粗飼料摂取が必要であり、この点も含めて泌乳初期における飼料摂取増進が望まれている。そこで、実測データの少ない乳量1万kg乳牛について、泌乳初期の飼料摂取量に対する第一胃容積の影響を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 泌乳期間中の乾物摂取量は、分娩1週間後頃では19.2 kgと低い値であったが、その後急激に増加して50日目前後までに最高値に達した後、乾乳期に向けて徐々に減少する(図1)。
- 朝の飼料給与後3時間目に、フィステルから第一胃内容物を全量取り出して計測した第一胃内容量は、分娩後10日目では89.5 kgであったが、100日目前後には最大値に達している(体重比では10日目に比べて、4.7ポイント高い18.7%である。)(図2)。
しかし、乾物摂取量が最大値に達している分娩後50日目では、まだピーク時の93%前後の第一胃内容量である(図1.2)。 - 分娩後10日目の粗飼料主体TMR(混合飼料)自由採食時に、24.5 kgの模擬の第一胃内滞留負荷を加えると、実質的な第一胃内容量は負荷前の69%となり、乾物摂取量はそれに応じて減少する(表1)。
- 分娩後20日目の濃厚飼料主体TMR自由採食時に同様の第一胃内滞留模擬負荷を行って第一胃内容量に対する乾物摂取量割合(A/B比)を比較すると、負荷前と負荷後で差はなく、同様の傾向は粗飼料主体TMR時にも認められる(表1)。
- 以上のことから、泌乳初期においてもホルモン等による栄養代謝変化による飼料摂取不全だけでなく、第一胃の内容量も採食量に影響しており、摂取飼料の第一胃滞留時間と第一胃機能の恒常性維持を勘案すると、分娩直前からの消化性の高い粗飼料の給与が重要である。
成果の活用面・留意点
- 乳量1万kg乳牛での実測値で、高泌乳牛の分娩前後に給与する第一胃滞留時間の短く第一胃内容積増加を亢進させる、食い込みの良い飼料の設計に参考となる。
- グラスサイレージと配合飼料主体のTMR給与下でのデータであり、模擬負荷量が1水準の結果である。なお、「消化性の高い粗飼料」は、切断長が長い出穂前のイネ科牧草・開花初期までのマメ科牧草の乾草・サイレージ等が望ましい。
具体的データ
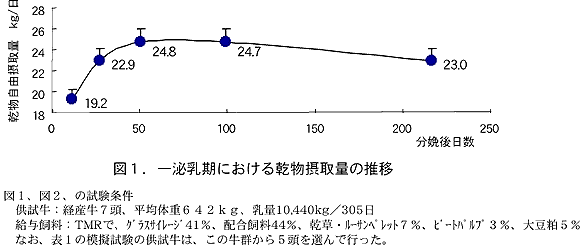
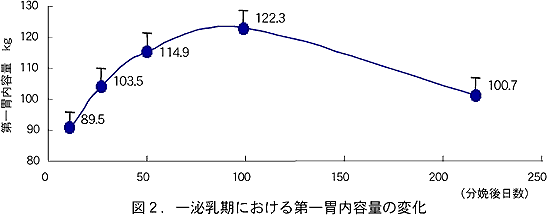
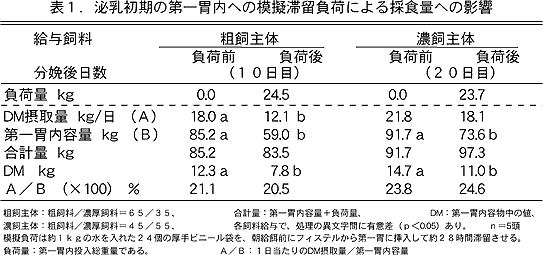
その他
- 研究課題名:泌乳初期の採食調節における物理的要因の役割の解明
- 課題ID:04-05-02-01-09-04
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2002~2004年度
- 研究担当者:押尾秀一、村井 勝、鎌田八郎、上田靖子
