フリーストール飼養乳牛における乾乳期削蹄の持続効果
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
分娩前2ヵ月に削蹄した前・後肢蹄は、分娩後2ヵ月には内・外蹄蹄尖部の伸び方に差異が生じて削蹄効果が消失する。また、フリーストール牛舎導入後から後肢蹄球糜爛が悪化し、分娩後2ヵ月には内・外蹄荷重の不均衡が著しくなる。
- キーワード:飼育管理、乳用牛、削蹄、蹄荷重、蹄病
- 担当:北海道農研・畜産草地部・家畜管理研究室
- 連絡先:電話011-857-9307、電子メールmasaton@affrc.go.jp
- 区分:北海道農業・畜産草地、畜産草地
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
フリーストール牛舎飼養では、従来の繋ぎ飼養より蹄病の発生が多く、蹄底潰瘍など後肢外蹄の蹄底角質に発生する疾病が多い。牛の削蹄の目的は正常な蹄形状を保ち、蹄に加わる体重配分を改善し、蹄の負重機能を維持することにある。そこで、分娩前2ヵ月のフリーストール牛舎飼養乳牛を削蹄し、分娩前後の内・外蹄形状、内・外蹄荷重、蹄角質硬度および蹄球糜爛の程度の経時的変化を調査する(図1)ことにより、削蹄の持続効果および蹄病発症要因を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 削蹄直後と比べ、前・後肢ともに内蹄背壁長の増加が外蹄背壁長の増加に比べて大きい。その結果、削蹄後2~4ヵ月には前・後肢内蹄蹄尖角度は有意に低下する(図2)。一方、前・後肢ともに内・外蹄反軸側壁長の増加に顕著な違いはない。
- 削蹄後2ヵ月経過すると、後肢外蹄蹄踵高が有意に増加する。
- 削蹄後3~4ヵ月で外蹄に対する内蹄負面面積割合は後肢では有意に減少する。
- 削蹄後4ヵ月で、後肢では外蹄の荷重が内蹄を上回り、前肢では逆に内蹄荷重が外蹄を大きく上回り、内・外蹄荷重の不均衡が生じる。このとき、再度削蹄すると内・外蹄荷重のバランスは分娩前2ヵ月の削蹄直後に近い値に戻る(図3)。
- 前肢に比べて後肢の蹄角質硬度は低く、蹄球糜爛スコアは高い。しかし、前・後肢蹄角質硬度はともに分娩後有意に低下する。後肢の蹄球糜爛スコアは分娩後1~2ヵ月で有意に増加し、前肢では分娩後2ヵ月で有意に増加する(図4)。
成果の活用面・留意点
- 削蹄は乾乳前期までに行い、分娩後2~3ヵ月で再び行うことが望ましい。
- 乾乳期間中はコンクリート床の屋外パドック、分娩後1週からはコンクリート床のフリーストール牛舎飼養で得られた結果である。
平成16年度北海道農業試験会議(成績会議)における課題名および区分
課題名:フリーストール飼養乳牛における乾乳期削蹄の持続効果(指導参考)
具体的データ
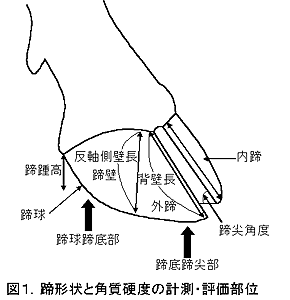
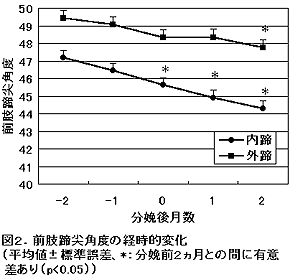
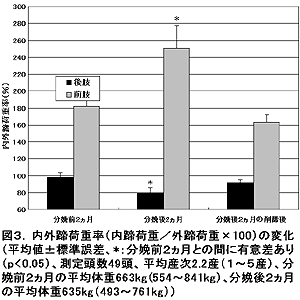
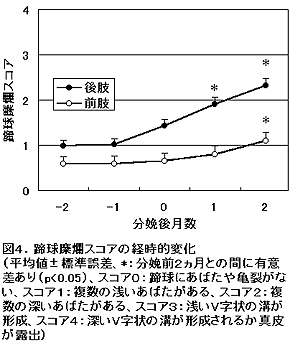
その他
- 研究課題名:蹄球糜爛による蹄の負重機能変化の解明と予防法に関する研究
- 課題ID:04-05-03-*-09-04
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2002~2004年度
- 研究担当者:中村正斗、矢用健一、森岡理紀、伊藤秀一
- 発表論文等:1) 中村ら(2004)平成15年度研究成果情報北海道農業:136-137
