先行後追放牧による搾乳牛用集約放牧草地の利用率向上
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
3頭/ha以下で年1回の採草兼用利用を伴う集約放牧条件下では、先行後追放牧による放牧草栄養価の改善効果は小さいが、牧草収量を低下させずに利用率を向上できる。先行牛の放牧草由来栄養摂取量を確保するためには割り当て草量の維持が重要である。
- キーワード:牧草、メドウフェスク、ペレニアルライグラス、乳用牛、放牧
- 担当:北海道農研・畜産草地部・放牧利用研究室
- 連絡先:電話011-857-9313、電子メールksudo@affrc.go.jp
- 区分:北海道農業・畜産草地、畜産草地
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
放牧草を効率的に利用するためには単位面積あたり放牧頭数を上げる必要があるが、搾乳牛の場合、放牧草採食量への影響が懸念される。また、泌乳盛期牛の放牧では補助飼料の増給与により、放牧草の利用率が低下する場合も想定される。よって、集約放牧条件下でも、養分要求量の高い搾乳牛(先行牛)に葉部割合が高い放牧草を採食させ、残った草を養分要求量の低い育成牛等(後追牛)に採食させる先行後追放牧の導入を検討する余地がある。そこで、搾乳牛放牧地内に育成牛の後追放牧を行う牧区と行わない牧区を3年間にわたり設け、利用率、収量、栄養価および搾乳牛の放牧草由来栄養摂取量への影響を検証する。
成果の内容・特徴
- 年1回余剰草を採草兼用利用し、haあたり放牧頭数1.6頭で搾乳牛を半日放牧中の1日輪換放牧地に育成牛を24時間後追放牧し、放牧頭数2.7頭/haとすると、各放牧回次毎の利用率は32.3%から40.2%に向上する。先行後追放牧により、各放牧回次の放牧前草高と草量はそれぞれ14%、20%減少するが、年間収量に有意な減少は認められない。先行牛に対する放牧草のTDN含有率が向上する時期は限られ、放牧期間全体では有意差にいたらない。(表1)
- 先行後追放牧の有無別に求めた搾乳牛の割り当て草量と放牧草由来栄養(TDN)摂取量との回帰式は併合が可能で、放牧草由来TDN摂取量は、先行後追放牧の有無によらず、割り当て草量に大きく影響される(寄与率77%、図1)。よって、先行牛の放牧草由来栄養摂取量を確保するためには割り当て草量の維持を重視すべきである。
- 先行後追放牧により、年間の地上部生産量に対する放牧と採草を含めた利用率は85.8%から89.7%に向上し、秋の放牧草中の枯死草の割合が32.3%から21.2%に減少する。また、後追牛としたホルスタイン種育成牛(平均体重381kg)の日増体量は5-9月に0.95kgを示し、良好である。
成果の活用面・留意点
- メドウフェスクまたはペレニアルライグラス草地において、3頭/ha以下で集約放牧を実施する場合に活用できる。
- 先行牛の割り当て草量が不足する際には、後追牛の放牧を中止する。永続性の点からメドウフェスク草地の放牧後草高は10cm以上とすることが望ましい。
具体的データ
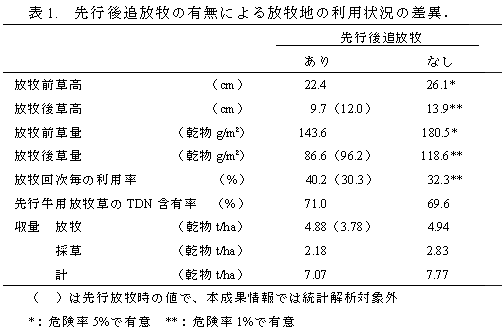
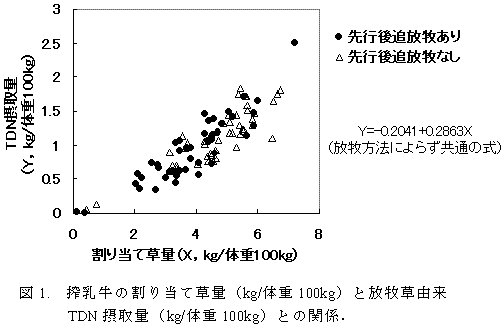
その他
- 研究課題名:乳牛放牧に適した草種の特性解明と利用技術の開発
- 課題ID:04-05-04-*-07-03
- 予算区分:交付金
- 研究期間:1998~2003年度
- 研究担当者:須藤賢司、落合一彦、池田哲也、梅村和弘、小川恭男、渡辺也恭
- 発表論文等:1) 須藤ら(2004)日草誌50(5):391-398.
