遊休農地化を防ぐための休閑期間の管理法と輪作体系
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
休閑期間に緑肥導入や隔年のロータリ耕管理を行うことで休閑後の雑草発生を抑えられるとともに休閑期間中の作業時間の短縮が図れる。特に休閑後1、2年目に秋まき小麦を栽培する場合には期間の長短にかかわらず緑肥導入が望ましい。
- キーワード:休閑、緑肥、輪作、耕作放棄、ロータリ耕
- 担当:北海道農研・畑作研究部・生産技術研究チーム
- 連絡先:電話0155-62-9274、電子メールkazuei@affrc.go.jp
- 区分:北海道農業・生産環境、共通基盤・総合研究
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
北海道においては耕地の大規模化への対応策として休閑を導入した輪作の構築が着目される。しかし、休閑期間中の圃場の管理様式の違いによる休閑後の作物の収量性や雑草の消長が問題となっている。そこで休閑期間中に手を加えない長期放任の影響やロータリ耕管理による土壌表層の攪乱、緑肥作物の導入効果を検討し、対策を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 休閑期間に放任するとスギナ、エゾノギシギシが優勢となり、休閑後3年目にも雑草発生が著しい。休閑期間3年間のロータリ耕管理では休閑後1年目の雑草発生量が多い傾向にある。緑肥導入や隔年のロータリ耕管理では雑草発生を抑えることができる(表1)。
- 総作業時間(経営耕地面積40haの1割を休閑と仮定)は、畑輪作の68.1時間/ha/年から緑肥導入で6.3時間/ha/年、休閑期間中の年5回のロータリ耕管理で6.7時間/ha/年の短縮ができると試算され、放任した場合と大差が生じない(表2)。
- 休閑後1、2年目にバレイショ、テンサイ、大豆を栽培する場合の収量性は、休閑期間の管理法の違いによる影響が小さい。休閑後1、2年目に秋まき小麦(表3下線の値)を栽培する場合の収量性は、ロータリ耕管理では休閑期間の長短にかかわらず劣り、緑肥導入が望ましい(表3)。
成果の活用面・留意点
- 北海道十勝地方における休閑期間中の管理や除草場合、耕作放棄を回避する管理法の参考となる。
- 作業時間は北海道農林水産統計年報(農業経営統計編)平成14年~15年(畑作物の生産概況:小麦、豆類、いも類、工芸作物の面積割合から算出)および北海道農業生産技術場合北海道農政部編第2版により算出した試算値である。
- 長期間の耕作放棄ではマツなどの永年性の植物も侵入するので畑への還元が困難になる。
- ロータリ耕管理では裸地状態となるので土壌浸食に注意する。
具体的データ
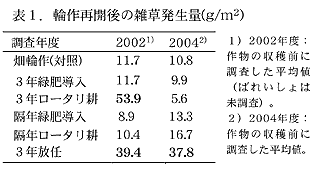
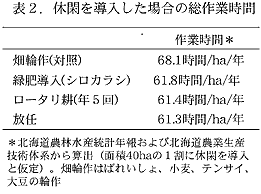
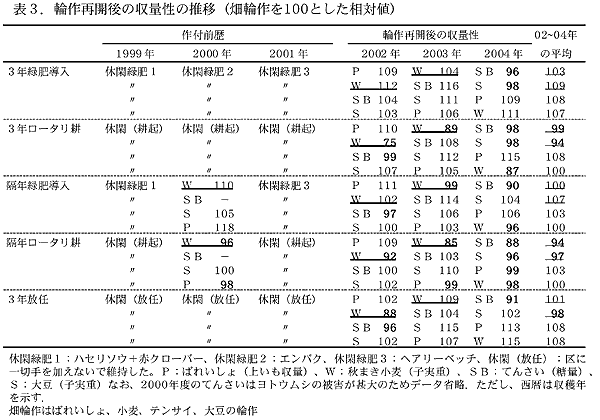
その他
- 研究課題名:大規模畑作への休閑を主体とした省力的栽培管理導入効果の解析
- 課題ID:04-04-01-*-03-04
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2002~2005年度
- 研究担当者:臼木一英、辻博之、中野 寛、奥野林太郎、古賀伸久、岩田幸良
