表面流式人工湿地による排水中無機態窒素の処理
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
無機態の窒素が多く含まれる排水を人工湿地で処理する。オオカサスゲを植栽した表面流式湿地により、夏期及び冬期(積雪がある場合)を通じて良好な処理が可能である。
- キーワード:酪農雑排水、排水処理、人工湿地、窒素
- 担当:北海道農研・畜産草地部・家畜管理研究室、畜産環境研究チーム
- 連絡先:電話011-857-9307、電子メールrmorioka@affrc.go.jp
- 区分:北海道農業・畜産草地、畜産草地
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
畜産からの雑排水を対象とする簡易な曝気法や活性汚泥法などは、主に有機汚濁負荷の除去には十分であっても、窒素など富栄養化の原因となる無機汚濁負荷に対しては不十分であることが多く、河川や湖沼、沿岸域の汚染源となる。ここでは上記のような好気的処理後に無機汚濁負荷が主体となった排水について、既存浄化施設に付加する簡易な高度処理法として、表面流式の人工湿地を用いるため、浄化能力の低下する積雪期間での運用を含めた周年での処理能力の観察を行った。
成果の内容・特徴
- ヨシ・ガマと比べて低温期でも枯死しにくいオオカサスゲを用いて表面流式人工湿地を作成し、浄化能力が低下すると思われる積雪期間中も観察を行った試験である。
- オオカサスゲ植栽人工湿地(2m x 8m = 16m²、流路長16m、夏期水位20cm、冬期水位40cm:図1)について、北農研パーラ排水の活性汚泥処理後の濃度を想定し、無機態窒素成分を80mg/L程度含有するように調整した合成排水を100L/日(水理学的滞留時間:夏期30日)で供給し、2004年6月中旬より11月中旬(1年目夏期)、同年12月中旬より2005年4月上旬(冬期)、また2005年6月中旬(2年目夏期)以降行った試験の結果である。
- 1年目の夏期における試験での処理水中全窒素は、秋期までの試験期間中(平均水温16°C程度)を通じて低い水準(平均して原水の11%)が保たれる(図2)。また、試験前後の掘り取り調査では、通算の窒素処理量全体に対して植物体中での窒素蓄積量は16%に留まっている。
- 冬期期間の試験での処理水中の全窒素についても、水位を調整し滞留時間を長くすることで、夏期から秋期と変わらず低い水準が保たれる(図3)。またこの期間は、積雪とともに水温の低下が抑えられ、平均して4°C程度が保たれる(図4)。
- 2年目の夏期から継続している試験での処理水では、全窒素について1年目とほぼ同等の低い水準が保たれる。また、水温15°Cを上回る9月下旬までは、全窒素濃度は水路長の1/3地点において原水の平均16%まで低下するが、以降は同水準まで低下するためにほぼ全長近くを要する。
成果の活用面・留意点
- 有機汚濁成分や懸濁物質の含まれない合成排水を処理した成績である。
- 積雪があり、水面付近の凍結のみで内部では水の移動が可能な条件での試験である。
- 同面積であっても、流路長によって残存する窒素濃度は異なる。排水の湿地への流入口と処理水の放流口は十分に離し、立地条件などにより流入口と放流口を近づけざるを得ない場合は、短絡流が生じないように仕切り板を設置するなどして対応する必要があると思われる。
- 植物体の刈り取りは一部サンプル採取以外は試験期間を通じて行っていない。
具体的データ
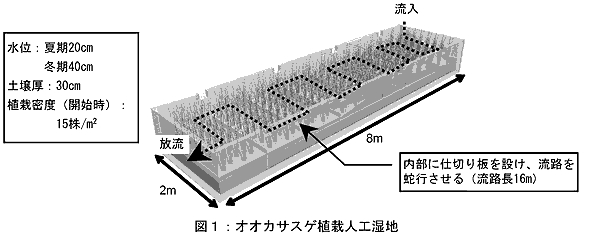
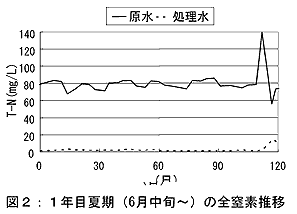
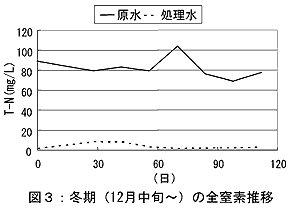
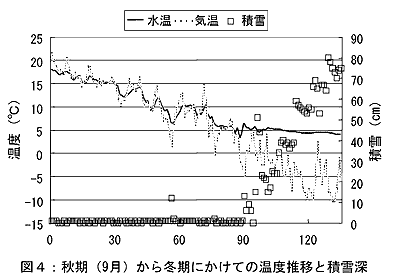
その他
- 研究課題名:酪農雑廃水処理の高度化手法の開発
- 課題ID:05-05-03-01-13-05
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2004∼2005年度
- 研究担当者:森岡理紀、中村正斗、中島恵一
