泌乳曲線平準化を目指した選抜指数による改良効果の検証
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
泌乳曲線平準化を目指した選抜指数上位の種雄牛を選抜した場合、泌乳後期の日乳量の減少が小さくなり、前期と後期の平均日乳量差は小さくなる。また、泌乳持続性の高い牛の供用産次数が長い傾向がある。
- キーワード:泌乳曲線、平準化、改良効果、乳用牛
- 担当:北海道農研・畜産草地部・家畜育種研究室
- 連絡先:電話011-857-9270、電子メールtake@affrc.go.jp
- 区分:北海道農業・畜産草地、畜産草地
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
泌乳最盛期乳量が高い泌乳曲線をもつ乳牛は、最盛期の栄養要求量が高く放牧など自給飼料だけで要求を満たすことが難しく、また、ス トレスにより供用年数の低下につながると言われる。このために、泌乳曲線平準化を目指した選抜指数が開発された。ここでは、2002年1月∼2004年8 月の乳検データに50頭以上の初産娘牛のデータを持つ種雄牛390頭を用いてその改良効果を検証する。
成果の内容・特徴
- 表1に 見られるように、泌乳曲線平準化を目指した指数が高い種雄牛は、乳量も高い傾向があるが、後期日乳量の減少量や、前期後期の日乳量差が小さい。指数Iと 305日乳量の相関は0.48、指数IIと305日乳量は0.28と正の値であり、乳量とともに泌乳持続性の改良が期待できる。
- 305日乳量上位の種雄牛を選抜した場合と較べて、泌乳曲線平準化を目指した選抜指数上位の種雄牛を選抜した場合の改良効果は、泌乳後期の日乳量の減少が小さく(後期回帰係数が大きく)なり、前期と後期の平均日乳量差は小さくなる(表2)。
- 北海道の乳検で、1994年から1998年に初産泌乳記録のある雌牛について、供用産次数の持続性(後期日乳量減少率)に対する回帰係数は、初産で0.57、2産で1.15と有意な値を示しており、泌乳持続性の高い牛の供用産次数が長い傾向がある(表3)。
成果の活用面・留意点
- 選抜指数式は、初産のデータを元に作成したものである。
- 持続性と供用年数の関係は、2産の方が強く、2産記録も含めた複数産次による選抜指数を作成することで、乳生産性と健全性を両立するより有効な改良が期待できる。
具体的データ
式1
泌乳曲線平準化を目指した選抜指数式
指数I= -3.64 G1+G2 前期乳量 0:後期乳量+1
の比率で改良する指数
指数II= -4.37 G1+G2 前期乳量-1:後期乳量+5
の比率で改良する指数
ここで、G1は前期(5-65日)乳量の育種価、G2は後期(65-305日)乳量の育種価。
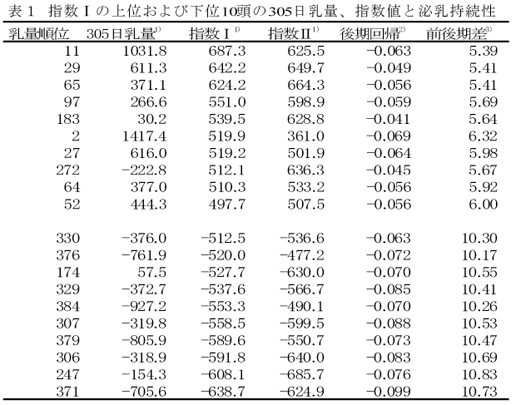
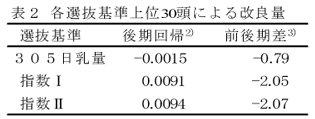
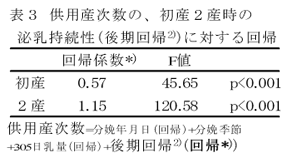
注 1)305日乳量、指数I、指数2:対象雄牛平均からの偏差で表示(kg)
2) 後期回帰:65-305日の期間での日乳量の単回帰係数(kg/日)
3) 前後期差:前期(5-65日)平均日乳量と後期(65-305日)平均日乳量の差
(kg)
その他
- 研究課題名: 低ピーク高持続性乳牛作出のための選抜モデルの構築
- 課題ID: 04-05-01-01-10-05
- 担当部署: 農研機構・北海道農研・畜産草地部・家畜育種研
- 予算区分: 委託プロ(健全畜産)
- 研究期間: 2003∼2007年度
- 研究担当者: 武田尚人、山崎武志、西浦明子、富樫研治
