ばれいしょ加工時のアクリルアミド生成に関わる要因
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
生イモ中の還元糖量、チップ中のアクリルアミド量が顕著に増加する貯蔵温度域は8℃未満である。アクリルアミド生成に最も強く関与する生イモ中の成分は還元糖である。
- キーワード:ばれいしょ、貯蔵温度、ポテトチップ、アクリルアミド、遊離糖、遊離アミノ酸
- 担当:北海道農研・畑作研究部・品質制御研究チーム、ばれいしょ育種研究室
- 連絡先:電話0155-62-9278、電子メールmechie@affrc.go.jp
- 区分:北海道農業・農産利用
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
炭水化物を多く含む食材を油加工など高温で加熱すると、発がん性の疑われているアクリルアミド(AA)が生成し、これがポテトチッ プなどばれいしょ加工食品に高いレベルで含まれる場合があることが報告された。日本のチップ原料は、トヨシロ等の加工用品種を秋∼翌春までは北海道産を貯 蔵して使用、その後の端境期は暖地産から順次北上して使用している。本研究では、品種や貯蔵条件による原料ばれいしょ中の成分の違いが、チップ加工時のア クリルアミド生成に与える影響を解明し、加工用高品質品種の育種開発、加工時の原料イモの管理技術等の基礎的知見とする。
成果の内容・特徴
- 加工用品種「トヨシロ」「スノーデン」「らんらんチップ」、および生食用品種「男爵薯」「インカのめざめ」のいずれにおいても、生イモ中の還元糖量、チップ中のアクリルアミド量が顕著に増加する貯蔵温度域は8℃未満である(図1)。
- チップ中のアクリルアミド量は、生イモ中の各成分のうち、還元糖量の変化とよく対応して変化し、両者には有意な相関がある(決定係数R2はフラクトース0.687(図2)、グルコース0.699、スクロース0.240 (n = 387))。一方、遊離アミノ酸は、有意な相関が見られない(アスパラギン(図2)、グルタミン酸、グルタミン)か、低い相関(アスパラギン酸)である。これらから、アクリルアミド生成に最も強く関与する生イモ中成分は還元糖である。
- チップカラーL*(明度)はアクリルアミド量と高い相関がある(R2 = 0.871, P < 0.001)。8℃未満の温度域での貯蔵塊茎から加工されたチップは、いずれの品種においてもL* < 54と低く、色相は暗褐色を呈する(図3)。これらから、従来のカラーでのチップ加工用系統の選抜法が、アクリルアミド低生成型系統の選抜においても有効であること、また、メーカーにおけるチップ製造ラインでの不良カラーチップの除去が、製品への高アクリルアミド含有チップの混入を防ぐ上で有効である。
成果の活用面・留意点
- これらの成果を、加工用ばれいしょの育種開発の基礎知見、チップ加工時の原料管理の基礎知見とする。
- チップ加工は、当部ばれいしょ育種研究室の標準調理検定法により作成した。
- 8℃未満の温度域での貯蔵試験はアクリルアミド生成の要因成分を解明するための手法であり、この温度域で貯蔵された塊茎は、通常チップ加工に用いられることはない。
具体的データ
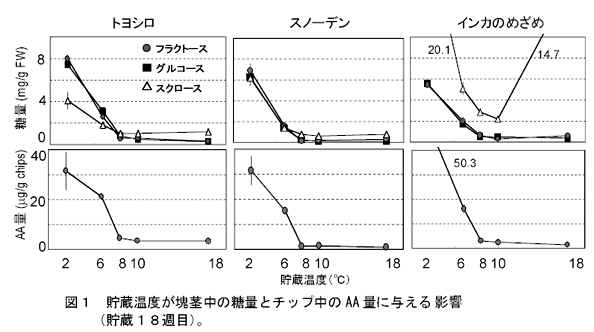
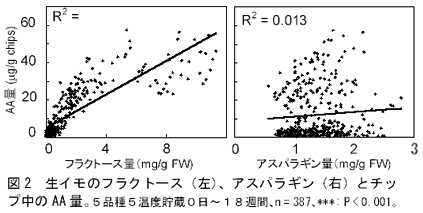

その他
- 研究課題名:バレイショ加工時のアクリルアミド生成に関わる要因解明と低生成型品種・系統の選定
- 課題ID: 04-03-02-03-35-04
- 予算区分: 食品総合
- 研究期間: 2003∼2004年度
- 研究担当者: 遠藤千絵、高田明子、小林 晃、津田昌吾、瀧川重信、野田高弘、山内宏昭、森 元幸(北農研)/忠田吉弘、小野裕嗣、箭田浩士、吉田 充(食総研)
- 発表論文等:
1) Chuda, Y., Ono, H., Yada, H., Ohara-Takada, A., Matsuura-Endo, C., and Mori, M. (2003) Biosci. Biotechnol. Biochem. 67: 1188-1190
2) Ohara-Takada, A., Matsuura-Endo, C., Chuda, Y., Ono, H., Yada, H., Yoshida, M., Kobayashi, A., Tsuda, S., Takigawa, S., Noda, T., Yamauchi, H., and Mori, M. (2005) Biosci. Biotechnol. Biochem., 69: 1232-1238
3) Matsuura-Endo, C., Ohara-Takada, A., Chuda, Y., Ono, H., Yada, H., Yoshida, M., Kobayashi, A., Tsuda, S., Takigawa, S., Noda, T., Yamauchi, H., and Mori, M. (2006) Biosci. Biotechnol. Biochem. (in press)
