トレンチへの灌漑による湿原の地下水位制御
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
長さ28m、幅23cm、深さ20cmで掘削したトレンチに灌漑を行った場合、地下水位を上昇させる効果はトレンチから約15mの範囲、水位を深さ5cmに保てるのは約5mの範囲であり、それに必要な灌漑水量は一日トレンチ1m当たり0.08m3である。
- キーワード:湿原、農業用水、灌漑、トレンチ、地下水位制御
- 担当:北海道農研・寒地温暖化研究チーム
- 連絡先:電話011-867-9260、電子メールseikajouhou@ml.affrc.go.jp
- 区分:北海道農業・生産環境
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
北海道に残る湿原の多くは、ササの繁茂によって湿原独特の景観が失われているが、湿原植生の復元、保全の手段として地下水位を高く維持することが有効とされている。そこでササが繁茂した湿原内に(図1(A))、レーザーレベルで割り出した等高線に沿って、長さ28m、幅23cm、深さ20cmのトレンチ(溝)を掘削し(図1(B))、湿原外部から導水を行い灌漑する方法を用いた湿原の地下水位制御効果を検証する。
成果の内容・特徴
- トレンチの水位を高く(ここでは深さ5cmとした)維持するため水田灌漑用自動給水栓を用いた。トレンチから離れたササ群落内の平均地下水位は15cmであり、これを上回る水位となる範囲が用水による灌漑効果が及ぶ範囲であると考えた。用水が常時供給されていた5月、6月の測定結果から、15cmを上回る範囲は、トレンチから内側12m、外側18mであった(図2)。また、この期間、トレンチの水位と同じ地下水位を5cmに保たれる範囲はトレンチから5m程の範囲であった(図2)。これらの条件を満たすために必要な灌漑水量は、一日トレンチ1m当たり0.08m3と算出された。
- 蒸発散量が0.8、1.5、2.5、4.3 mm/dの場合の地下水位と蒸発散量の関係をシミュレートした(図3)。平均的な蒸発散量である2.5mm/dの場合、地下水位が15cm以上になる範囲は、トレンチ両側の約15mと評価された。この結果と、上記の地下水位の測定結果がほぼ一致することから、本方法を用いた湿原の地下水位灌漑効果は約15m程度と評価出来る。
- 用水の供給が終わった9月には地下水位は全体的に低下するが、10月以降は、給水なしでも自然に水位が上昇する(図2)。
成果の活用面・留意点
- 用水の供給が停止する場合、導水を行うホースや管に空気が溜まり送水が困難となるため、用水が再供給される際に空気を抜くための工夫が必要である。
- 用水には種子やゴミなどが含まれるため、ろ過してからトレンチに導水する必要がある。
- トレンチ内は泥炭の残渣が堆積するので適宜、排出する必要がある。
具体的データ
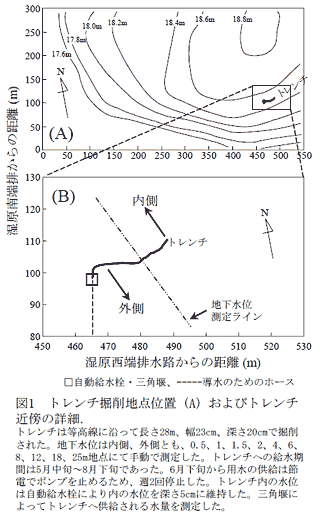
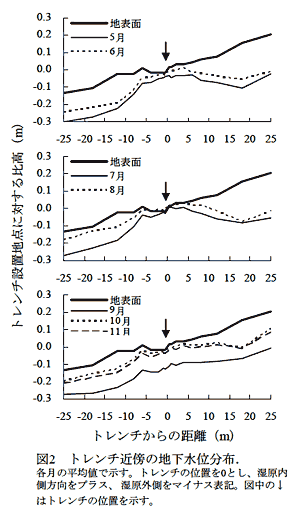
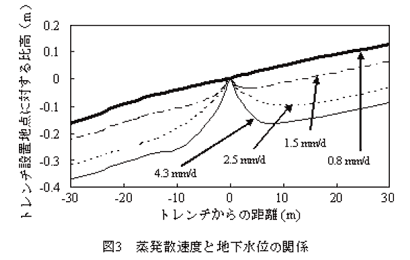
その他
- 研究課題名:寒地における気候温暖化等環境変動に対応した農業生産管理技術の開発
- 課題ID:215-a
- 予算区分:委託プロ(公害防止)
- 研究期間:2003~2006年度
- 研究担当者:永田 修、鮫島良次
- 発表論文等:1) Iiyama et al.:Soil Sci. Plant Nutri., 51(3), 313~322(2005)
2) 飯山ら:農土誌, 74(7), 591~594(2006)
