ダイズの難裂莢性DNAマーカー
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ダイズ品種「SJ2」由来の難裂莢性遺伝子は多様な遺伝的背景で効果を発揮し、その選抜DNAマーカーは裂莢し易い国内の主要品種と多型を示すことから、機械収穫適性に関するマーカー育種に有用である。
- キーワード:ダイズ、機械収穫適性、難裂莢性、マーカー育種、高精度マッピング
- 担当:北海道農研・低温耐性研究チーム、作物研・大豆育種研究チーム、道立十勝農試・大豆科、道立中央農試・畑作科、北海道大学・農学研究院
- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp
- 区分:北海道農業・生物工学、作物
- 分類:研究・普及
背景・ねらい
近年、ダイズ栽培においてコンバイン収穫が全国的に普及し、それに適した品種の育成が求められている。莢がはじけにくい性質(難裂莢性)はそのために重要な形質であるが、国内で育成された難裂莢性品種は少なく、普及面積は10%に満たない。全国に対応した品種群を迅速に育成するためには、難裂莢性に関する簡便かつ高精度なマーカー選抜システムが必要である。そこで、北海道で利用実績のある、タイ品種「SJ2」由来の難裂莢性遺伝子に強連鎖し、かつ国内の主要な易裂莢性品種と多型を示すDNAマーカーを高精度マッピングにより開発し、その効果を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 「SJ2」由来の難裂莢性遺伝子が座乗する遺伝子座qPDH1は、第16染色体(旧分子連鎖群J)の29547kb(マーカーA)から29681kb(マーカーB)までの領域内に存在する(図1)。
- 「SJ2」と易裂莢性品種「トヨムスメ」とのゲノムを比較すると、この領域で挿入/欠失配列が見いだされ(図1)、その配列をもとに設計したPCRベースのマーカーがSRM1、SRM2である(表)。いずれのマーカーも難裂莢性遺伝子との遺伝距離は0.2cM未満と推定される。
- 「SJ2」由来の難裂莢性品種・系統(ハヤヒカリ、ユキホマレ、十系992号、CH001)は、すべてSRM1およびSRM2に関して「SJ2」と同じ対立遺伝子型を示す(表)。
- 一方、裂莢性が易から中程度の国内主要品種(トヨムスメ、キタムスメ、トヨハルカ、フクユタカ、タチナガハ、サチユタカ、エンレイ、リュウホウ、スズユタカ、すずかおり、あやこがね、ナカセンナリ、ことゆたか、ふくいぶき)は、SRM1に関して、すべて「SJ2」と多型を示す(表)。
- 「すずかおり」以外の上記主要品種は、SRM2に関しても、「SJ2」と多型を示す(表)。
- 対立遺伝子型(増幅されるDNA断片の長さ)の差異に基づき(表)、SRM1は小型のポリアクリルアミドゲル電気泳動で、SRM2はアガロースゲル電気泳動で簡易に判別ができる。
- 「SJ2」由来の難裂莢性遺伝子をもつ品種・系統と易裂莢性品種・系統の交雑後代では、栽培地に関係なく、SRM1が「SJ2」型のものは難裂莢性になる(図2)。
成果の活用面・留意点
- ダイズの難裂莢性に関するマーカー選抜に利用できる。
具体的データ
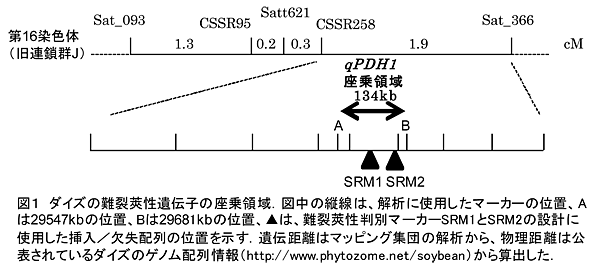
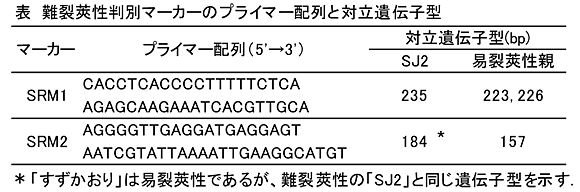
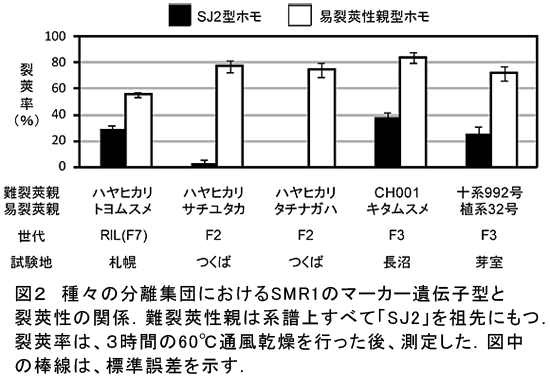
その他
- 研究課題名:作物の低温耐性等を高める代謝物質の機能解明とDNAマーカーを利用した育種素材の開発
- 課題ID:221-e
- 予算区分:実用技術
- 研究期間:2006~2008年度
- 研究担当者:船附秀行、羽鹿牧太、山田哲也、萩原誠司(十勝農試)、田中義則(十勝農試)、
藤田正平(道立中央農試)、石本政男、辻博之、藤野介延(北大院農) - 発表論文等:1) Funatsuki H. et al. (2006) Plant Breed. 125: 195-197
2) Funatsuki H. et al. (2008) Breed. Sci. 58:63-69
