九州の火山灰土壌に見られる硬盤層の特性
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
九州各地の火山灰土壌に見られる硬盤層(非常に硬い層)は、土壌化の進んでいるものといないものに大別される。前者は乾燥した際に収縮硬化するが、後者は湿った状態でも硬い。前者は土壌分類上で定義されている硬盤層のいずれとも異なる新しいタイプである。
- 担当:九州農業試験場・生産環境部・土壌特性研究室
- 連絡先: 096-242-1150
- 部会名: 農業環境(環境資源特性)
- 専門: 土壌
- 対象:
- 分類: 研究
背景・ねらい
九州の火山灰土壌には、島原半島の「かしの実層」、久住地域の「花牟礼層」、阿蘇周辺の「ニガ土」および仮称「バンバン」、薩摩半島の「コラ」などの硬盤層が見られる。これらの硬盤層の諸性質を鉱物化学的、微細形態学的、土質工学的に総合解析した研究例はなく、また硬化の機構も解明されていない。本研究では九州の火山灰土壌に見られる硬盤層の諸性質や成因を解明し、適正な土壌管理方法の策定に資する。
成果の内容・特徴
- 理化学性から、硬盤層は「ニガ土、かしの実層」のグループ(以下タイプ1)と「花牟礼層、バンバン、コラ」のグループ(以下タイプ2)に大別される(表1)。
- タイプ1は土壌化が進んでおり、その理化学性は一般の火山灰土壌と性質が同じである。タイプ2は土壌化が進んでおらず、火山噴出物の堆積直後に硬化したと考えられる。 タイプ1は生土の状態ではさほど硬くないが、乾燥に伴い大幅に収縮して非常に硬くなる。硬化の度合いは砂が少なく粘土が多いもので大きい。タイプ2は生土の状態でも硬く、乾燥に伴う収縮・硬化はない(図1)。
- タイプ1の土塊は、風乾と水漬を繰り返すと徐々に砕けていくが、通常の黒ボク土にくらべ、砕土性ははるかに低い(図2)。
- タイプ1・2のどちらでも、土塊の強度が大きいものの微細形態は、孔隙が少なく、互いにつながり合わないのが特徴である(図3)。
成果の活用面・留意点
- タイプ1は、既存の土壌分類上で定義されている硬盤層のいずれにも当てはまらず、新たな種類の硬盤層と位置づけられる可能性がある。
- タイプ1の硬盤層が表土化する場合は、大きな塊のまま硬化しないように、表土化した直後の湿った状態で細かく砕くことが土壌管理上重要である。
具体的データ
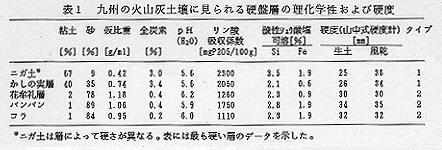
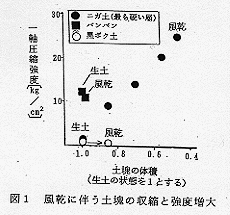
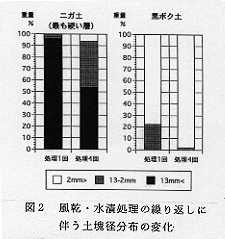
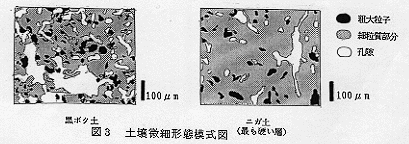
その他
- 研究課題名:埋没黒ボク土(黒ニガ)の特性解明
- 予算区分 :経常
- 研究期間 :平成6年度(平成4年~6年)
- 発表論文等:Indurated Volcanic Ash Soils in Japan. Their Characteristics,
Land Use and Management;Proc. 15th International Congress of
Soil Science(1994)
九州のテフラ由来土壌に見られる硬盤層の諸性質と成因、九農研57
(投稿中)
