赤米・短稈の水稲新品種候補系統「西海209号」
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
水稲「西海209号」は、南海97号/対馬赤米の組合せから育成された赤米粳系統で、晩生、やや短稈、穂発芽性中の特徴がある。赤い色素を生かした酒、菓子や観賞用としての用途が期待できる。
- 担当:九州農業試験場・水田利用部・稲育種研究室
- 連絡先:0942-52-3101
- 部会名:作物生産・水田作
- 専門:育種
- 対象:稲類
- 分類:普及
背景・ねらい
赤米系統は、米の需要拡大のための新形質米プロジェクト研究において、低アミロース、巨大胚、蛋白成分などの新しい形質系統とともに育成された。赤米は、古代米として人気があり、町おこし、村おこしのための特産品として栽培するほか、赤酒の酒造用原料、赤い色素を活用する工業面で、生け花・ドライフラワー用には芒の赤色をかつようした需要拡大が見込まれている。しかし、従来の赤米は、在来種であり、ほとんど改良されておらず、栽培特性、特に耐倒伏性、収量性、休眠性などに欠点が多い。農家や町おこしなどのグループからは、栽培特性に優れる赤米品種の育成が強く望まれている。このような期待に応えるため米の需要拡大のための新形質米プロジェクト研究の中で、赤米系統の育成を行ってきた。
成果の内容・特徴
- 「西海209号」は、1987年に九州農業試験場において「南海97号」を母本とし「対馬赤米」を父本として交配し、その後代から育成された。
- 出穂期は「対馬赤米」より早く、「レイホウ」より3日程度遅い晩生の早に属する赤米粳系統である。
- 稈長は「対馬赤米」よりかなり短く、「レイホウ」並かやや短い。穂長は「対馬赤米」より短く、「レイホウ」よりやや長い。
- 耐倒伏性は「対馬赤米」より強く、「レイホウ」よりやや弱い“中”である。
- ふ先色は「対馬赤米」と同様赤褐で、芒は「対馬赤米」、「レイホウ」より明らかに多くて長い。脱粒性は中である。
- いもち病真性抵抗性遺伝子はプラスかあるいは未知の真性抵抗性遺伝子を持つと推定され、圃場抵抗性は中である。
- 収量性は「対馬赤米」より多収であるが、「レイホウ」より少収である。
- 穂発芽性は「ユメヒカリ」より易で、「レイホウ」より難の“中”である。
成果の活用面・留意点
- 「西海209号」は奨励品種採用県はないが、命名登録によって、九州各地域において、町おこしの特産物用として普及すると思われる。
- 晩生なので、適地を選定するとともに、晩植は避ける。
- 赤米は通常の品種と混じると検査等級を下げるなどの問題があるので、種子の管理は徹底して行う。
具体的データ
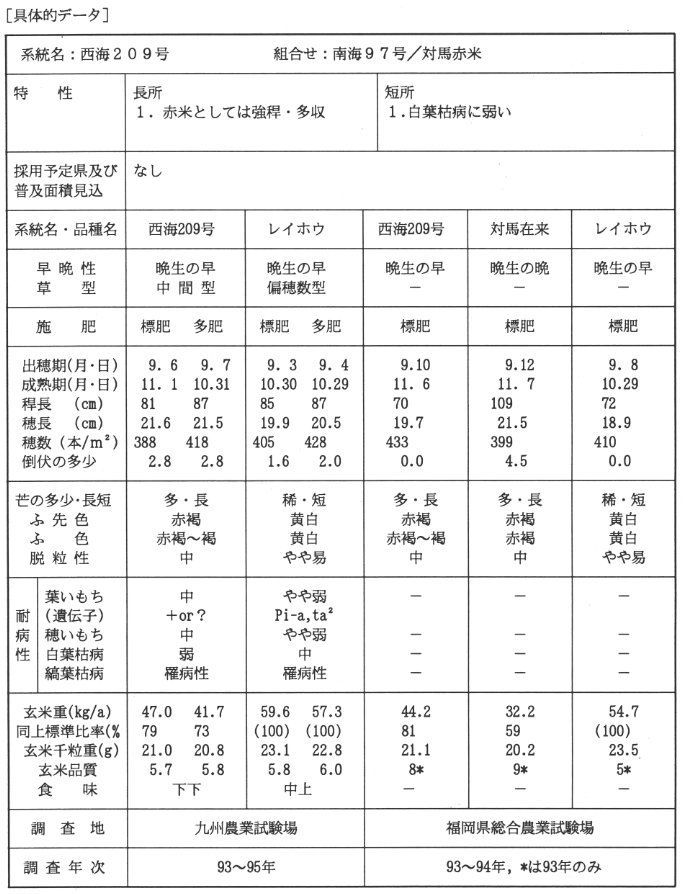
その他
- 研究課題名:暖地向き水稲の良質安定多収品種の育成
- 予算区分:総合開発研究(新形質米)
- 研究期間:平成7年度(昭和62年度~平成7年度)
