1994年の猛暑が九州地方の牛乳生産に及ぼした影響
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
1994年の猛暑による牛乳生産への影響として、個体のFCM乳量が平均で約3~5%低下した。被害は、乳量水準の高い牛、気温の高い地域で大きかった。また、農家は繁殖面での被害を最も深刻にとらえていた。
- 担当:九州農業試験場・畜産部・環境生理研究室
- 連絡先:096-242-1150
- 部会名:畜産・草地
- 専門:飼育管理
- 対象:家畜類
- 分類:行政
背景・ねらい
1994年の記録的な猛暑により、九州地域の農業生産は甚大な被害を被ったが、とりわけ冷涼な地域を原産とする乳牛の被害は大きかったと推察される。そこで、猛暑が牛乳生産に及ぼす被害の実態を明らかにするとともに、猛暑に対する農家の被害意識や各種暑熱対策技術の実施状況を明らかにすることにより、今後の暑熱対策に役立てる。
成果の内容・特徴
- 熊本県牛群検定成績による被害状況の解析a.1~3月に分娩した牛の5月の乳量を100とした時の7、8月の乳量を指標として、夏季の平均気温が3~4度低かった前年度と比較した結果、1994年の猛暑では、個体乳量が約3~5%低下した(図1)。b.乳量水準の高い牛ほど乳量の低下割合は大きかった(図2)。c.気温の高い地域ほど乳量の低下が著しく、気温が1度高くなると、乳量は約2.4%低下した(図3)。
- 猛暑の被害に対する農家の意識(表1)。農家が猛暑による被害を実感した項目は、繁殖(73%)、乳量(38%)、乳質(31%)および乳房炎(25%)で、特に、受胎率の低下に対する関心が高かった。
- 農家における暑熱対策の取り組み状況(表2)。a.飼料給与面では、ほとんどの農家が夏季に良質粗飼料を給与できるように配慮し、高泌乳牛に対するサプリメントの利用を行っていた。b.設備面では、ほとんどの農家が換気扇や細霧装置、牛体散水などの簡易に行える対策を実施していた。
成果の活用面・留意点
- 猛暑時の被害推定に活用できる。
- 多くの農家が簡易に行える暑熱対策を既に実施しており、今後はこれらの複数の暑熱対策を効果的に活用していくことが重要である。
具体的データ
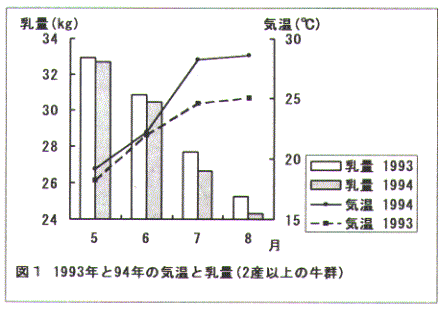
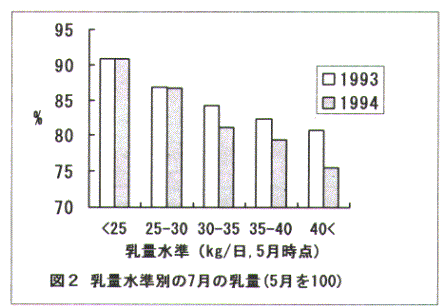
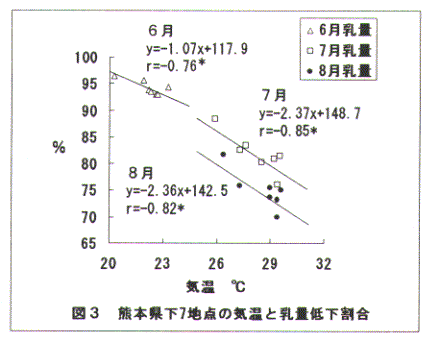
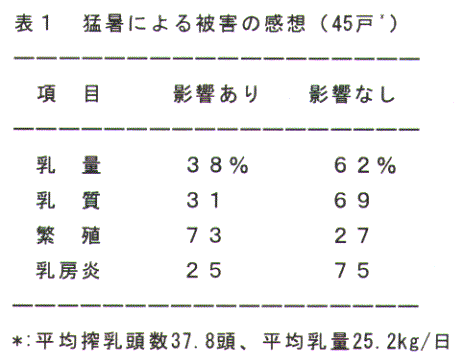
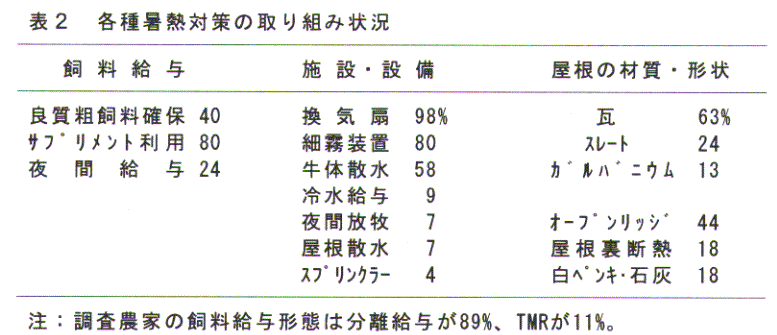
その他
- 研究課題名:猛暑が九州地域における牛乳生産に及ぼした影響の解析と暑熱対策技術の評価
- 予算区分:緊急調査
- 研究期間:平成7年度(平成6年度)
- 発表論文等:熊本県における94年猛暑による牛乳生産被害状況の解析.九州農業研究.第58号.1996.
