暖地の有機物長期連用水田におけるメタン生成の特徴
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
稲わら堆肥の連用は水田土壌中のメタン生成菌密度を増加させるが、化学肥料や稲わらを連用した場合に比べて、メタンフラックスとメタン生成能を低下させる。
- 担当:九州農業試験場・生産環境部・土壌微生物研究室
- 連絡先:096-242-1150
- 部会名:環境評価・管理、生産環境
- 専門:土壌
- 対象:稲類
- 分類:研究
背景・ねらい
水田への有機物施用は温室効果ガスであるメタンの発生に大きな影響を及ぼす。西南暖地の二毛作水田における稲わら及び稲わら堆肥の30年以上の連用が、メタン生成に及ぼす影響を明らかにし、水田からのメタン発生制御のための基礎的知見を得る。
成果の内容・特徴
- 土壌中のメタン生成細菌密度は年間を通じてほぼ一定で、化学肥料連用区や稲わら連用区と比べ、稲わら堆肥連用区では約1桁増加する(表1)。
- メタンフラックスは、化学肥料連用区や稲わら連用区と比べ、稲わら堆肥連用区で低い(図1)。
- 土壌のメタン生成能は、中干しを境に、化学肥料連用区では増加するが、稲わら連用区や稲わら堆肥連用区では減少する(図2)。
- 以上の結果から、稲わら堆肥の連用により、水田土壌中のメタン生成菌密度は増加するが、メタンフラックスとメタン生成能は減少する。
成果の活用面・留意点
- 水田からのメタン発生の制御技術開発のための基礎資料となる。
- 西南暖地の長期連用二毛作水田における調査結果である。
- メカニズムについては今後の検討が必要である。
具体的データ
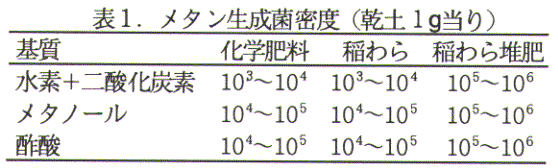
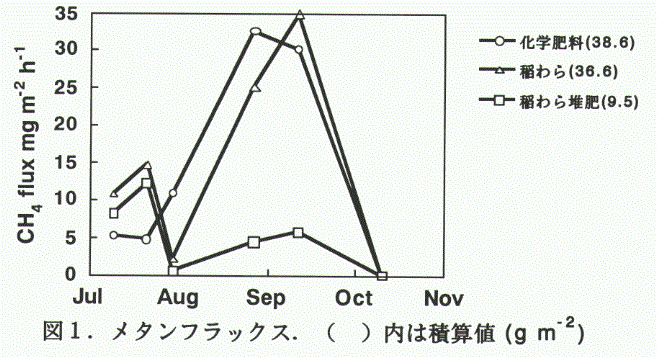
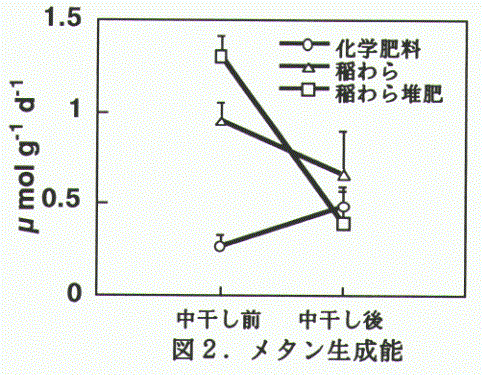
その他
- 研究課題名:メタン生成菌の活性制御技術の開発
- 予算区分:一般別枠(地球環境)、流動研究
- 研究期間:平成7年度(平成5~8年)
- 協力・分担:九州農試・水田利用部・水田土壌研、千葉大・園芸学部・土壌研
- 発表論文等:水田土壌におけるメタン酸化、生成の活性と菌数およびフラックスの相互関係、第11回日本微生物生態学会講演要旨集、1995
