土壌診断に基づく青果用かんしょ「ベニオトメ」の適正なカリウム施用法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
「ベニオトメ」の上イモが最適収量を得るために必要なカリウム(K)量は約170kg/haである。かんしょ苗植付け前の土壌中のK(IN酢安抽出)濃度から生育に有効なKの存在量が推定出来る。最適収量を得るには「ベニオトメ」のK必要量から土壌中の有効なK存在量の差を施用する。
- 担当:九州農業試験場・生産環境部・上席研究官,土壌資源利用研究室
- 連絡先:096-242-1150
- 部会名:生産環境
- 専門:肥料
- 対象:かんしょ
- 分類:指導
背景・ねらい
かんしょにカリウム(K)を多用すると塊根の肥大が促進されるが,乾物率が低下したり,余剰のKが土壌環境を撹乱する。そこで塊根の最大収量を得るのに必要なK量を植付け前の土壌中の交換性K量から推定し,不足するK量を施用する方法を開発する。
成果の内容・特徴
- 厚層多腐植質黒ボク土で「ベニオトメ」を栽培した場合、年次により上イモ収量に違いが認められるが,上イモ収量が最高値を得るためのK吸収量は窒素施用量が0から50kg/haの範囲内であればいずれの年次も145-206kg/ha(平均170kg/ha:収量曲線から試算)である(図1)。
- 施用K量が多いと前作物が吸収できなかった量が土壌中に残存して交換性K濃度が増加する。両者間には正の相関関係が成り立つ(図2)。
- 苗の植付前の土壌(作土深30cm)からIN酢酸アンモニウム(酢安)で抽出されるKを測定すると土壌に残存するK量が推定できる。施用K量と残存K量との和が170kg/ha(施肥試験から塊根が最大収量を得る値と試算)になるように設計するとその年次の最適収量が得られる(図3)。
成果の活用面・留意点
- カリウムの合理的な施用法の指針となる。
- 本方法は「ベニオトメ」を黒ボク土壌で栽培したものであり,品種や土壌の種類が異なる場合は検討する必要がある。
具体的データ
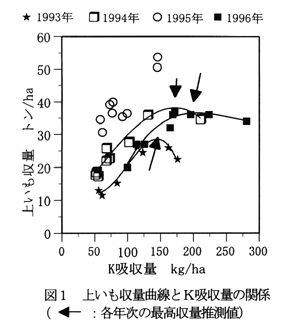
図1 上いも収量曲線とK吸収量の関係(←:各年次の最高収量推測値)
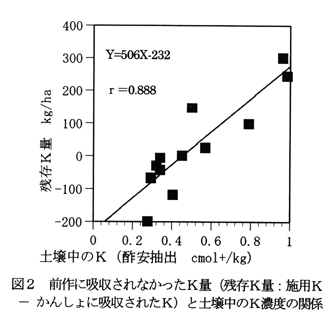
図2 前作に吸収されなかったK量(残存K量:施用K-かんしょに吸収されたK)と土壌中のK濃度の関係
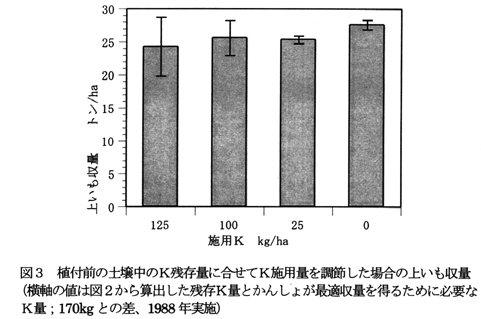
図3 植付前の土壌中のK残存量に合せてK施用量を調節した場合の上いも収量(横軸の値は図2から算出した残存K量とかんしょが最適収量を得るために必要なK量;170kgとの差、1988年実施)
その他
- 研究課題名:甘しょの高品質化をめざした養分環境制御技術の開発,甘しょの適正K施用量の推定
- 予算区分 :総合的開発研究、経常(単年度)
- 研究期間 :平成10年度(平成4年-9年,10年)
