暖地の小麦早播き栽培におけるスズメノテッポウの発生消長の特徴と生産された種子の発芽能力
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
小麦早播き栽培におけるスズメノテッポウの発生は普通期播き栽培に比べて早く、小麦播種後31~44日目に累積出芽率が90%に達する。小麦の播種時期にかかわらず、2月中旬までに発生した個体で生産された種子は発芽能力を有するが、3月中旬に発生した個体で生産された種子は発芽能力がない。
- キーワード:小麦早播き栽培、スズメノテッポウ、発芽能力、発生消長
- 担当:九州沖縄農研・水田作研究部・雑草制御研究室
- 連絡先:0942-52-0675
- 区分:九州沖縄農業・水田作
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
稲麦二毛作体系の生産安定化のために秋播き型早生小麦を用いた作期の前進化が検討されている。播種時期を早めることは雑草の発生や生育に変化をもたらす。そこで、主要雑草であるスズメノテッポウについて小麦早播き栽培における発生消長の特徴を明らかにするとともに、異なる時期に発生した個体で生産された種子の発芽能力を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 早播き栽培におけるスズメノテッポウは、小麦播種後に速やかに発生が始まり、その累積出芽率は小麦播種後31~44日目に90%に達するが、発生はその後も3月下旬まで続く(図1、表1)。
- 極端な乾燥年を除いて、発生の速度は普通期播き栽培に比べて早播き栽培のほうが速やかで、累積出芽率が90%に達するまでの日数も短くなる(表1)。さらに累積発生本数は早播き栽培のほうがやや多い(表2)。
- 極端な乾燥年(1998年)では、発生の速度は小麦の播種時期にかかわらず緩やかで、発生本数も少ない(図1、表1、表2)。
- 小麦群落内のスズメノテッポウは小麦の播種時期にかかわらず、3月中旬に発生した個体が生産した種子は発芽能力を持たず、2月中旬までに発生した個体が生産した種子は発芽能力を有する(表3)。
成果の活用面・留意点
- 小麦早播き栽培における必要除草期間策定のための基礎的知見として活用する。
- 早播き栽培の播種期は、北部九州の普通期播き栽培に比べて20日程度早い11月4~7日である。
具体的データ
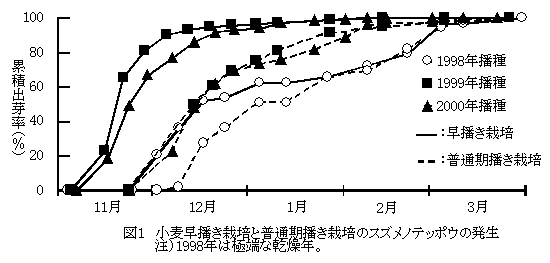
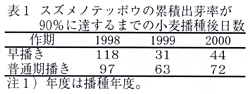
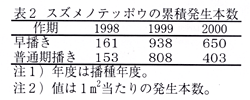
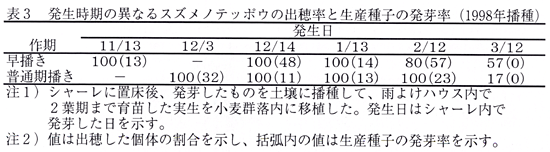
その他
- 研究課題名:暖地の小麦早播き栽培における雑草制御技術の確立
- 予算区分:21世紀プロ1系
- 研究期間:1999~2004年
- 研究担当者:大段秀記、住吉正、児嶋清(中央農研)、小荒井晃
- 発表論文等:1)住吉・児嶋(2000)雑草研究45(別):156-157.
