小麦および水稲の子実には土壌ダイオキシン類はほとんど移行しない
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
稲麦二毛作の小麦、水稲のダイオキシン類濃度は根>茎葉>穎、籾殻>小麦穀粒、玄米の順に低くなり、TCDDおよびCo-PCBの占める割合が土壌に比べ高く、OCDDの占める割合が土壌に比べ低い。さらに、子実のダイオキシン類濃度は土壌の影響をほとんど受けない。
- キーワード:ダイオキシン類、水田土壌、小麦穀粒、玄米
- 担当:九州沖縄農研・水田作研究部・水田土壌管理研究室
- 連絡先:電話0942-52-0681、電子メールt2711@affrc.go.jp
- 区分:九州沖縄農業・生産環境(土壌肥料)、共通基盤・土壌肥料
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
過去に使用されたPCPやCNP等の水田除草剤あるいはゴミ焼却等に由来するダイオキシン類の動態が社会的に問題となっている。西南暖地の稲麦二毛作地帯では土壌が還元状態と酸化状態を交互に繰り返すため、ダイオキシン類の動態がこれらの影響を受けることが予測される。そこで、ダイオキシン類組成の異なる土壌において、稲麦二毛作体系が土壌及び作物のダイオキシン類濃度に及ぼす影響を解明する。
成果の内容・特徴
- 稲麦二毛作の水田土壌の0~30cmの土層ではダイオキシン類濃度はB圃場(稲わら1t/10a連用)の方がA圃場(有機物無施用)より高く、主にCNPに由来するTCDD濃度はB圃場で高く、A圃場では低い。主にPCPに由来するOCDD濃度はB圃場で特に高い。さらに、経年的に総ダイオキシン類濃度は低下し、還元状態を経過した水稲跡より次作の酸化状態を経過した小麦跡で低い傾向が見られる(図1)。
- 作物体では根>茎葉>穎、籾殻>小麦穀粒、玄米の順にダイオキシン類濃度は低下し、TCDDの占める割合が土壌に比べ高く、OCDDの占める割合が土壌に比べ低い(図2~図5)。さらに、地上部ではCo-PCBの占める割合が土壌に比べ高い。作物体の部位別では水稲根のダイオキシン類濃度が小麦根より高いが、その他の部位では水稲で低い。いずれも土壌のダイオキシン類組成の影響を根や茎葉では受けるが子実ではほとんど受けない(図2~図5)。さらに、可食部である小麦穀粒及び水稲玄米のダイオキシン類濃度は土壌ダイオキシン類濃度の高低にかかわらず、2~8pg/g(0.002~0.006pg-TEQ/g-wet)程度と低い(図5)。
成果の活用面・留意点
- ダイオキシン類と土壌の酸化還元状態との関係解明に参考となる。
- 九州沖縄農研センター水田作研究部の細粒灰色低地土で1963年より稲麦二毛作をしている隣接2圃場の結果であり、土壌の灼熱減量はA圃場で8.9%、B圃場は9.5%である。
- TCDDは4塩素ジベンゾジオキシン、OCDDは8塩素ジベンゾジオキシン、Co-PCBはコプラナーPCB、PCDDはポリ塩化ジベンゾジオキシン、PCDFはポリ塩化ジベンゾフランであり、ダイオキシン類はPCDD、PCDF、Co-PCBの総称である。なお、TEQは毒性等量濃度である。
具体的データ
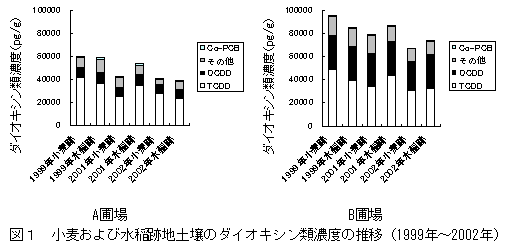
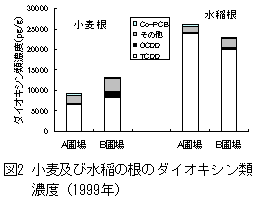
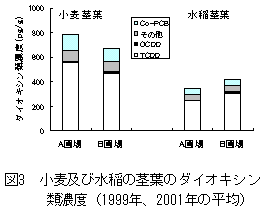
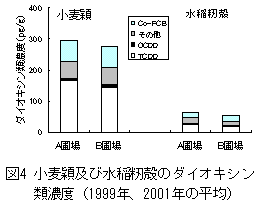
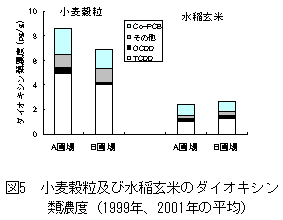
その他
- 研究課題名:稲・麦二毛作が内分泌かく乱物質の動態に及ぼす影響と作物への吸収・蓄積過程の解明
- 予算区分:環境ホルモン
- 研究期間:1999~2002年度(平成11~14年度)
- 研究担当者:土屋一成、草佳那子、森泉美穂子、原嘉隆、西田瑞彦
