サツマイモ茎中からの窒素固定細菌Pantoea agglomeransの分離と共存培養による窒素固定活性の向上効果
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
サツマイモ茎中から内生窒素固定細菌Pantoea agglomerans K1-7株を分離した。K1-7株と非窒素固定性内生細菌Enterobacter asburiae K1-1株を共存培養すると窒素固定活性が向上する。非窒素固定性内生細菌K1-1株は内生窒素固定細菌の窒素固定活性を高める働きをもっている。
- キーワード:サツマイモ、内生窒素固定細菌、非窒素固定性内生細菌、共存培養
- 担当:九州沖縄農研・畑作研究部・生産管理研究室
- 連絡先:電話0986-22-1506、電子メールkadachi@affrc.go.jp
- 区分:九州沖縄農業・生産環境(土壌肥料)、共通基盤・土壌肥料
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
南九州の畑作地帯で基軸作物として栽培されているサツマイモの茎中に生息する内生窒素固定細菌の生態に関して、これまで窒素固定細菌Klebsiella oxytocaを分離し、切片培養・アセチレン還元活性測定法により茎中に窒素固定細菌が生息していることを確認した(2001年度成果情報)。ここでは、これまでサツマイモからの分離例のない新しい内生窒素固定細菌の分離を試みる。また、サツマイモ茎中には窒素固定性と非窒素固定性の両方の内生細菌が生息していることから、これらの内生細菌同士は何らかの相互作用を持つことが予想される。そこで、サツマイモ茎の同一サンプルから分離された窒素固定性内生細菌と非窒素固定性内生細菌の間で共存培養を行い、培養液中の窒素固定活性への影響を検討する。
成果の内容・特徴
- サツマイモ(品種:コガネセンガン)の茎中から分離された内生窒素固定細菌K1-7株(長桿菌、写真1A)は、Pantoea agglomeransである(表1)。
- コガネセンガンの茎中(同じ茎サンプル)から非窒素固定性内生細菌Enterobacter asburiae K1-1株(写真1B)を分離した。
- 内生窒素固定細菌K1-7株と非窒素固定性内生細菌K1-1株とを共存培養すると、培養液中の窒素固定活性は、K1-7株単独培養の場合と比べて約2倍に向上する(表2)。このことは、非窒素固定性内生細菌K1-1株が、窒素固定細菌K1-7株の窒素固定活性を高める働きをもっていることを示す。
- 共存培養における培地構成成分を順に欠除するマイナスエレメント試験により、共存培養による窒素固定活性向上効果には、培地中のショ糖とリンゴ酸が影響していることがわかる(図1)。
成果の活用面・留意点
- Pantoea agglomeransは、トウモロコシや小麦等に内生窒素固定細菌として生息していることが確認されている。また、P. agglomeransはサツマイモ葉面から病原性糸状菌に対する拮抗微生物として分離された(2000年)。しかし、サツマイモから内生窒素固定細菌としてP. agglomeransが分離されたのは世界で初めてである(文献情報データベースCAB、BIOSIS、Current Contents Connect検索結果として記述、2003年1月現在)。
- 非窒素固定性内生細菌K1-1株は、複数のサツマイモ内生窒素固定細菌に対して同様の窒素固定活性向上効果を持つ。
- 内生窒素固定細菌の接種技術開発に向けて、Pantoea agglomeransや非窒素固定性内生細菌との共存による窒素固定活性向上効果が活用できる。
- 共存培養による窒素固定活性向上効果が、サツマイモ植物体内でも同様に働いているかどうか、検討する必要がある。
具体的データ
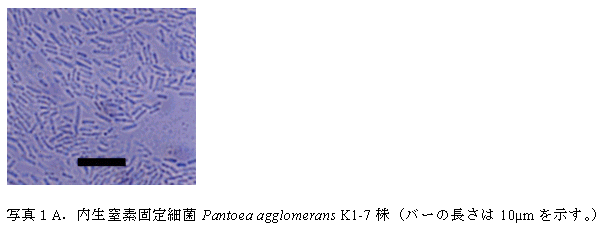
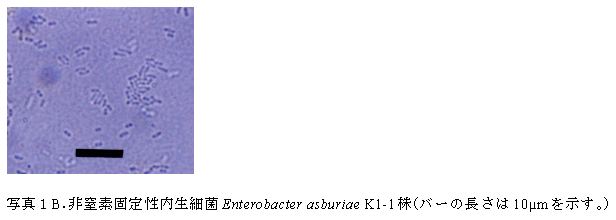
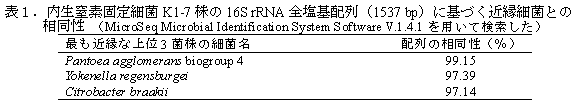
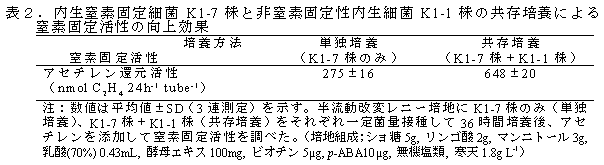
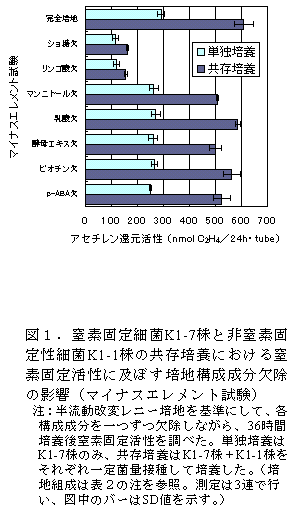
その他
- 研究課題名:1)南九州の畑作物に共生する微生物の分離と共生機作の解明、
2)カンショ内生窒素固定細菌の同定・利用技術の開発 - 予算区分:1)交付金、2)農研機構平成14年度重点強化費
- 研究期間:1999~2002年度
- 研究担当者:安達克樹、Constancio A. Asis, Jr.(JSPS外国人特別研究員)
