乳牛スラリー連用畑下層土には多様な低栄養性脱窒菌が多数生息する
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
乳牛スラリーを多量に投入した畑地では、作物根の届かない4mの下層土にも多くの脱窒菌が生息し、その大部分は低い栄養濃度の培地で増殖する低栄養性脱窒菌である。
- キーワード:乳牛スラリー、下層土、窒素代謝、低栄養性脱窒菌
- 担当:九州農研・環境資源研究部・土壌微生物研究室
- 連絡先:電話096-242-7765、電子メールhasimoto@affrc.go.jp
- 区分:九州沖縄農業・生産環境(土壌肥料)
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
農地への有機物や化学肥料の過剰施用による地下水系等への窒素溶脱が懸念される中、窒素過剰土壌の環境負荷低減技術の開発に向けた脱窒菌群の動態評価が重要である。従来研究対象とされてきた脱窒菌は、通常の高栄養培養条件に適応した菌群(普通脱窒菌群)だけであった。一方、土壌環境、特に下層土は一般的に低栄養条件であることから、低栄養性脱窒菌群の生態とその機能に関する知見は脱窒による窒素浄化技術の開発に向けて極めて重要である。そこで、窒素収支が明らかにされた乳牛スラリー連用畑土壌中の低栄養性脱窒菌の動態を調査する。
成果の内容・特徴
- 普通脱窒菌数は表層ではスラリー投入量(0, 60, 150, 300t/ha)に対応した菌数分布を示すが、下層では投入量との関係は認められない。一方、低栄養性脱窒菌数の場合、表層から下層までスラリー投入量に対応した垂直分布を示す(図1)。
- いずれの土壌層位においても、低栄養性脱窒菌数が普通脱窒菌数よりも10~105倍多い。また、スラリー投入量が多いほど、下層における低栄養性脱窒菌群が相対的に増加する(図2)。
- 普通脱窒菌数及び低栄養性脱窒菌数は、いずれの場合も脱窒活性との有意な相関関係が認めらる(前者r=0.756**、後者r=0.462**)。しかし下層土だけで見ると、有意な相関関係は認められない。
- 各土壌層位から分離した脱窒菌(61株、うち45株が低栄養性脱窒菌)の16SrDNA解析により、低栄養性脱窒菌を含む多様な脱窒菌群の生息が明らかとなった(表1)。
成果の活用面・留意点
- 今回分離した多様なグループに属する低栄養性脱窒菌の特性評価は今後の課題である。
具体的データ
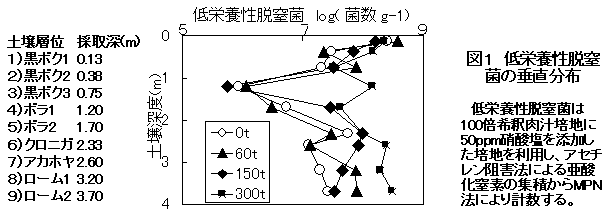
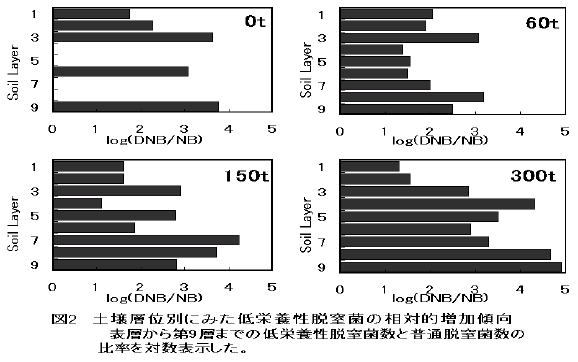
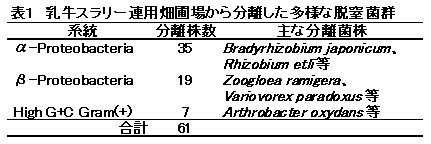
その他
- 研究課題名:南九州畑地下層土の脱窒菌群の動態解明、
畑地下層土からの低栄養要求型脱窒菌の分離と脱窒能・亜酸化窒素生成能の評価 - 予算区分:自然循環、科研費
- 研究期間:2000~2002年度、2002~2005年度
- 研究担当者:橋本知義、浅川晋、長岡一成(重点研究支援協力員)、永原彰子(重点研究支援協力員)、
黄敬淑(牧園大)、金澤晋二郎(九州大)、安起弘(九州大)
