利用者の違いに応じた地場農産物直売施設の販売戦略
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
地場農産物直売施設は、集客範囲が広い「レジャー型」施設では、特産的商品や安全な商品を揃え、周辺施設を充実させること、利用頻度の高い利用者が多い「日常利用型」直売施設では、価格設定や品揃えに留意することなど、利用者の購買行動の違いに応じた販売戦略が必要である。
- キーワード:地場農産物直売施設、購買行動、販売戦略、青果物
- 担当:九州沖縄農研・総合研究部・農村システム研究室、動向解析研究室
- 連絡先:電話096-242-7696、電子メールhiroyuki@affrc.go.jp
- 区分:共通基盤・経営
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
地域活性化を目指し増加してきた地場農産物直売施設のなかには、売上が伸びずに経営状況の厳しい施設がみられる。この情報では、熊本県の直売施設の売上高に関する状況を整理するとともに、2つの特徴の異なる直売施設の利用者アンケート結果に基づいて、利用者層の違いに応じた青果物の販売戦略の必要性を指摘する。
成果の内容・特徴
- 地場農産物直売施設の売上高は施設間で格差が大きく、その差は拡大する傾向にある。売上高の高い施設では、野菜等の青果物の販売額割合が高い傾向にあり、青果物の売上を高めることが、施設全体の売上を高めるためには重要である(表1)。
- 売上高が高い直売施設間でも、立地条件の違いにより利用者の構成割合は異なる。例えば、都市郊外に立地する施設Aは、集客範囲が広く、月1~2度以下の利用者が多い「レジャー型」施設であるのに対し、都市に隣接する施設Bは、集客範囲が狭く、利用頻度の高い利用者が多い「日常利用型」施設である(表2)。
- 直売施設の利用者は、青果物購入に際して、商品自体に対しては「新鮮さ」「生産者名表示等による安心感」「低価格」を、施設の特性に対しては「品揃え(量)の豊富さ」「駐車場・周辺道路の整備」「特産的商品がある」を、施設利用理由の上位にあげる。特に「新鮮さ」は利用者に強く求められている要素であり、直売施設が商品管理において最も留意しなければならない事項である(表3)。
- しかし、利用者の属性によって、施設利用理由には違いが認められる。利用頻度の高い利用者や青果物消費に占める直売施設利用割合が高い利用者は、「低価格」や「店員や生産者との交流」を、遠距離からの利用者は「有機・減農薬等の安全性」「地域特産商品がある」「イベントや周辺施設の充実」等を、近場の利用者は「生産者名表示等による安心感」「品揃え(量)の豊富さ」等を、相対的に強く支持する傾向にある(表3)。
- したがって、施設Aのような「レジャー型」施設では、特産的商品や有機栽培・減農薬等の安全な商品を揃え、イベントや付帯施設の充実を図り、施設Bのような「日常利用型」施設では、価格設定、品揃えの確保、生産者名表示の徹底に留意する等の、利用者の購買行動の違いに応じた販売戦略をたてることが重要である(表3)。
成果の活用面・留意点
- 直売施設毎の販売戦略に応じた生産・出荷体制の整備が必要である。
- 販売額の大きい直売施設を対象とした成果である。売上げが伸び悩む小規模直売施設の対策については、別の視点も含めて検討する必要がある。
具体的データ
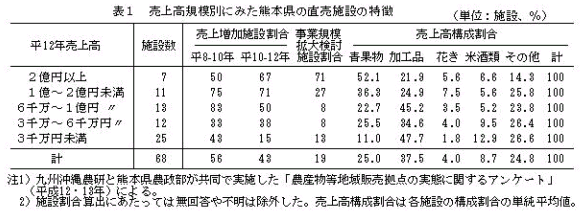
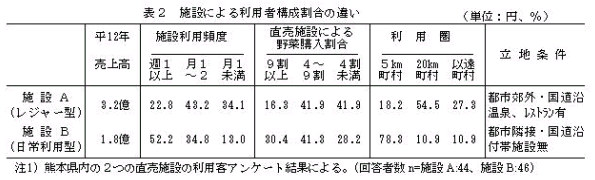
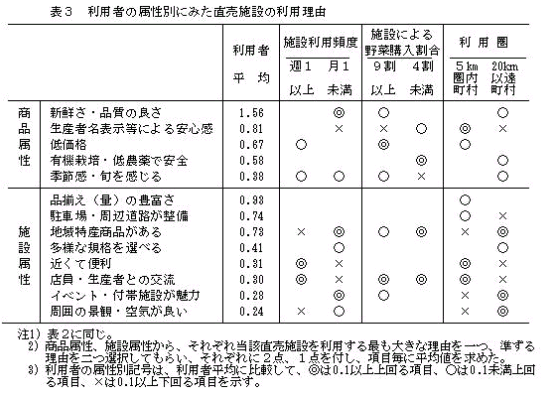
その他
- 研究課題名:地場農産物直売施設を核とした活性化メカニズムと活性化支援方策の解明
- 予算区分:農村経済活性化
- 研究期間:1999~2002
