沖縄本島における農地貸借あっせんシステムの重要性
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
沖縄本島では、親戚間を中心に農地貸借が成立してきたが、近年、その取引範囲が広がっている。これにより、大規模経営の成立が徐々に進みつつあるが、個別相対取引のもとでの借地確保の困難さが、さらなる規模拡大の制約要因となっている。農地貸借あっせんシステムを機能させることが重要である。
- キーワード:沖縄、農地貸借、あっせんシステム、個別相対取引
- 担当:九州沖縄農研・総合研究部・農村システム研究室
- 連絡先:電話096-242-7696、電子メールhiroyuki@affrc.go.jp
- 区分:共通基盤・経営
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
沖縄本島では、その特有な社会経済的条件のもとにあって、農地所有の性格や農地貸借の形成メカニズムが、本土とは異なっている。
本情報は、宜野座村M集落で実施した農地貸借に関する聞き取り調査結果に基づいて、沖縄本島における農地貸借の特徴と、貸手・借手間関係にみられる近年の変化を明らかにし、これが地域農業の展開に及ぼしている影響を指摘する。
成果の内容・特徴
- 沖縄本島地域では、農地の男子分割相続慣行が支配的で、非営農者や村外転出者も相続を受けるため、農地所有規模が小さく、土地持ち非農家世帯や村外在住の農地所有世帯が多い。農地相続を受けた非営農者や、後継者が他出している高齢農業者は、自分や子供の近い将来の帰村や就農の可能性に備えて、農地を所有したまま貸し付けるため、多数の貸借が形成されている。貸付にあたっては、「必要時にいつでも返してくれる」「畑を丁寧に耕作する」借手を強く選好するため、兄弟を含む親戚との間で、個別相対で成立する貸借が多数を占めてきた(図1)。
- しかし近年は、農地の受け手が減少し、狭い取引相手との関係のなかでは貸借成立が困難になってきたことや、「親戚だとトラブルを生じた時に面倒」等の意識の広がりのなかで、農地所有者が必ずしも血縁にこだわらなくなったなかで、親戚以外との貸借が増加している(表1)。
- この農地貸借における取引範囲の広がりは、一方では規模拡大を可能とする条件となっている。親戚間での貸借が主であったため、従来沖縄の貸借は階層性(大規模層に借地が集中する傾向)が不明瞭であったが、親戚外との貸借が増えることで、農地集積による大規模経営の成立が徐々に進みつつある(表1)。
- しかし、こうした取引相手の広がりのなかにあっても、貸借が個別相対取引を基本とする点は変わっていない(表2)。親戚外との貸借においては、第三者がこれを仲介する例もみられるが、農業委員(会)や集落役員の仲介は希である。現在の規模拡大志向農家にとって、個別相対取引の下での農地確保の困難さが、さらなる規模拡大を進めるうえでの主たる制約要因となっている(表3)。
- 以上の点は、集落等の地縁的組織が持つ農地の所有・利用調整機能が弱い当地域では、農業委員会主導の農地貸借あっせんシステムを機能させることが重要であることを示している。
成果の活用面・留意点
沖縄県内でも、農地の相続慣行や農地貸借の性格には地域性がある。この情報は、主として沖縄本島を適用範囲としている。
具体的データ
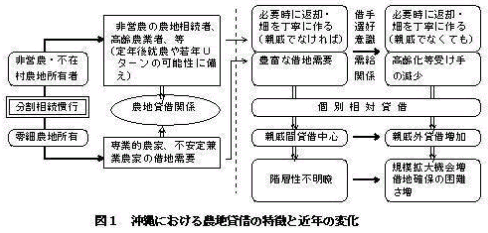
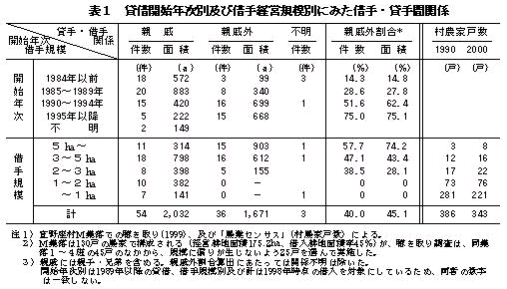
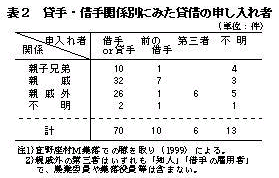
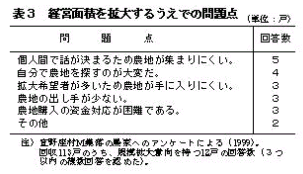
その他
- 研究課題名:開発技術の定着条件の解明および支援方策の策定
- 予算区分:亜熱帯野菜・花き
- 研究期間:1998~2002年度
- 発表論文等:井上・田口(2001)沖縄における農地貸借の形成メカニズムと今日的特徴、農業経営研究 39(2):75-78
