極良食味で多収の暖地向き晩生水稲新品種候補系統「あきまさり(西海248号)」
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
「あきまさり(西海248号)」は、「ユメヒカリ」熟期の晩生の粳種である。強稈で耐倒伏性に優れ、収量性は「ユメヒカリ」「かりの舞」を約10%上回る多収である。食味は「ユメヒカリ」に明らかに優る極良食味である。「ユメヒカリ」等の代替として熊本県で普及予定である。
- キーワード:イネ、晩生、良食味、多収
- 担当:九州沖縄農研・水田作研究部・稲育種研究室
- 連絡先:電話0942-52-0647、電子メールmsakai@affrc.go.jp
- 区分:九州沖縄農業・水田作、作物・稲
- 分類:技術・普及
背景・ねらい
近年、九州地域の稲作は市場評価の高い中生種のヒノヒカリに作付が集中する傾向があり,収穫作業の競合や共同乾燥調製施設の運営に支障をきたし、刈り遅れ等による品質低下も懸念されている。平坦部の稲作地帯では中生品種と組合せ可能な食味の良い晩生種の導入が期待されている。このため、「ユメヒカリ」熟期で食味と栽培特性に優れた晩生種を育成する。
成果の内容・特徴
- 「西海248号」は1996年に晩生、極良食味の「南海127号」(後の「かりの舞」)を母とし、晩生、多収、極良食味の「西海230号」(後の「あきさやか」)を父として人工交配を行った組合せから育成された。(表1)。
- 出穂期は「ユメヒカリ」より1日程度早いが、籾数が多くつきやすいので、登熟期間はやや長く、成熟期は「ユメヒカリ」より2~4日程度遅い“晩生の晩”である。
- 稈長は「ユメヒカリ」より3~5cm長く、草型は“偏穂重型”である。耐倒伏性は「ユメヒカリ」並の“強”である(表1)。
- 収量は「ユメヒカリ」より10%以上多収である(表1)。
- 千粒重は「ユメヒカリ」より1g程度重く、玄米の見かけの品質は「ユメヒカリ」と同程度の“上下”である。
- 食味は「ユメヒカリ」に優り、「コシヒカリ」に近い“上中”である。
- いもち病抵抗性遺伝子は“Pii”を持つと推定され、葉いもち圃場抵抗性は「ユメヒカリ」並の“やや弱”、穂いもち圃場抵抗性は「ユメヒカリ」並の“中”である。白葉枯病抵抗性は「ユメヒカリ」より弱い“やや弱”である。
成果の活用面・留意点
- 晩生の多収、良食味品種として暖地の平坦部、準平坦部に適する。
- 熊本県の奨励品種として平坦地、山麓準平坦地において、「ユメヒカリ」、「レイホウ」の全部及び「ヒノヒカリ」の一部に替えて5000haの普及を予定している。
- いもち病には強くないので、多肥栽培をさけ、適期防除を行う。
- 白葉枯病には弱いので、常発地での栽培を避ける。
- 籾数が多くなりやすく登熟期間が長いことに留意して刈り取り時期を定める必要がある。
具体的データ
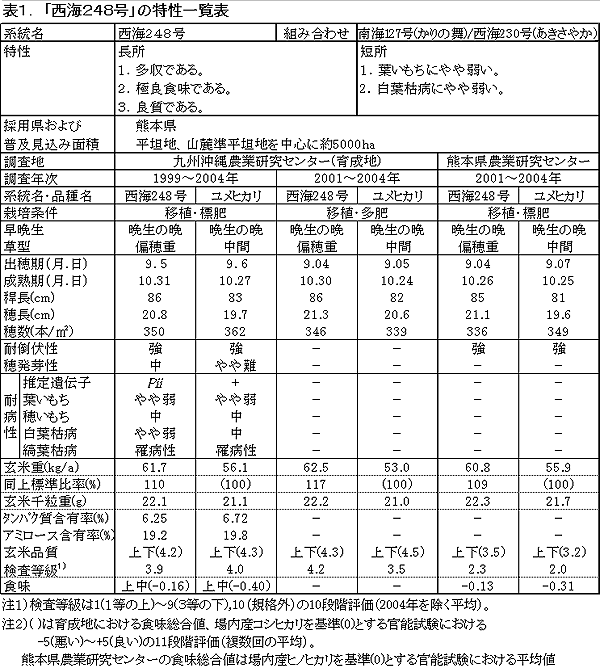
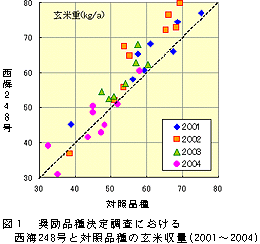

その他
- 研究課題名:暖地の普通期作に適する良食味安定多収水稲品種の育成
- 課題ID:07-02-01-01-07-04
- 予算区分:交付金
- 研究期間:1996~2004年度
- 研究担当者:坂井 真、梶 亮太、田村克徳、岡本正弘、西村 実、八木忠之、溝淵律子、平林秀介、深浦壮一、
富松高治、山口末次
