九州沖縄の各種土壌の硬化強度特性と赤黄色土の再軟化性
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
九州に分布する赤色土や黄色土の乾燥時の硬化強度は、粘土含量およびpHと正の関係にある。灰色低地土やグライ土の硬化強度はpHとは関係せず、粘土含量のみに依存する。硬化強度が極めて大きい細粒質・高pHの黄色土でも、含水比0.15 kg kg-1前後で耕耘に問題がない状態まで軟化する。
- キーワード:土壌、硬化強度、pH、粘土含量
- 担当:九州沖縄農研・環境資源研究部・土壌資源利用研究室
- 連絡先:電話096-242-7764、電子メールkubotera@affrc.go.jp
- 区分:九州沖縄農業・生産環境(土壌肥料)
- 分類: 科学・参考
背景・ねらい
これまでに、沖縄県のマージ土壌(赤色土、黄色土および暗赤色土)のpHが高くなると乾燥時に強く硬化することが明らかになってい る。これを踏まえ、九州の各種の土壌について、pHや粘土含量が硬化強度に及ぼす影響を明らかにし、さらに硬化が著しい黄色土を用いて加水による再軟化性 に関する検討を行う。
成果の内容・特徴
- 粘土含量30%前後の各種土壌について、乾燥時の硬化強度を測定すると、黄色土は無処理(pH(H2O) 4前後)の状態では0.1∼0.2 MPaと小さいが、pHの上昇に伴い1.0∼1.3 MPaまで増大する。灰色低地土は、無処理(pH(H2O) 5.4)の状態でも1.2 MPaと大きいが、pHの上昇に伴う硬化強度の増大は見られない。黒ボク土はpHに関係なく、硬化強度はほぼゼロである(図1)。
- 赤色土や黄色土(長崎県)と、灰色低地土やグライ土(佐賀県)のいずれも、粘土含量が多い土壌ほど硬化強度が大きい。赤色土や黄色土ではpHが高い土壌で硬化強度が大きいが、灰色低地土およびグライ土ではこの傾向は見られない(図2)。
- pHが高く(7.6)、粘土含量が多い(53%)黄色土でも、乾燥して強く硬化した土塊を含水比0.15 kg kg-1前後(握った手に湿り気が残る程度)に湿らせると、砕土に支障がないレベルまで強度が低下する(図3)。
成果の活用面・留意点
- 土壌硬化への対策上、灰色低地土やグライ土では砂客土などによる粒径組成の粗粒化が、赤色土や黄色土では粒径組成改善と土壌pHの管理が重要である。
具体的データ
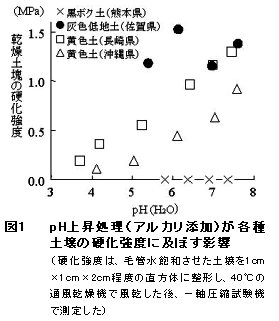
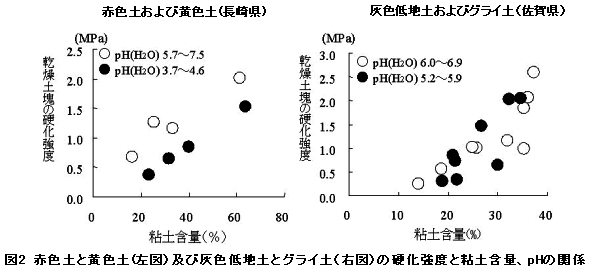
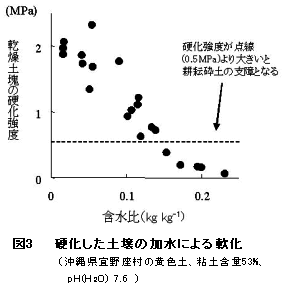
その他
- 研究課題名:pHおよび交換性陽イオン量が土壌の硬化・砕易特性に及ぼす影響の解明
- 課題ID:07-06-01-01-09-04
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2002∼2004年度
- 研究担当者:久保寺秀夫
- 発表論文等:
1) Kubotera(2004) Soil Sci. Plant Nutr. 50(2):269-275.
2) 久保寺(2004) 土肥誌 75(5):565-566.
3) Kubotera(2005) J. Agric. Meteorol. 60(5):1069-1072.
