乾熱土のアンモニウム態窒素による水田土壌の窒素肥沃度の簡便迅速推定
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
水田の風乾土を乾熱すると、150℃以下では温度が高いほどアンモニウム態窒素が増加し、105℃・1日乾熱後のアンモニウム態窒素量は培養後無機態窒素量と高い相関があるので、乾熱土のアンモニウム態窒素量によって窒素肥沃度を簡便迅速に推定できる。
- キーワード:土壌分析、窒素肥沃度、簡便迅速法、乾熱土、アンモニウム態窒素
- 担当:九州研・九州水田輪作研究チーム
- 連絡先:電話0942-52-0681、電子メール yshara@affrc.go.jp
- 区分:九州沖縄農業・生産環境(土壌肥料)、共通基盤・土壌肥料
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
輪作水田で窒素肥沃度に応じて次作の窒素施肥量を調整する場合、土壌の窒素肥沃度を前後作の間の短い期間に迅速に把握することが求められる。また、多くの水田を対象とする場合、一定の精度が有れば精度よりも簡便性に優れる手法が望ましい。ところで、風乾土を乾熱するだけでアンモニウム態窒素が増加する現象が知られているが、これまで窒素肥沃度との関係を調べた報告はみあたらない。そこで、風乾土を乾熱した土壌(以下、熱土と略)のアンモニウム態窒素量と乾熱条件および培養後無機態窒素量との関係を調べ、熱土のアンモニウム態窒素を利用した窒素肥沃度の簡便迅速推定の可能性を判断する。
成果の内容・特徴
- 乾熱温度が150℃以下(期間1日)では、温度が高いほど熱土のアンモニウム態窒素量が多くなるが、180℃以上ではこの発現量は低下する(図1、(この関係は4で述べる))。
- 乾熱温度が180℃を超えると、熱土のアンモニウム態窒素量が減少するが、これは全窒素量の傾向(図2)から、このとき、アンモニウム態窒素が気化し、気化の程度が土壌で異なるためと推測される。
- 窒素肥沃度推定の可能性がある150℃以下の乾熱のとき、熱土アンモニウム態窒素量は乾熱期間が長いほど多くなり、2週間経っても一定値にならない(図3)。
- 迅速な測定のために乾熱期間を1日とした場合、105℃でのアンモニウム態窒素量は、培養後無機態窒素量に対して少ないものの、水田を想定した湛水培養(r=0.90**、図4)、畑を想定した湿潤培養(r=0.84**、図省略)のいずれとも高い相関が得られる。より高温で乾熱するとアンモニウム態窒素量は多くなるが、培養後無機態窒素量との相関は低下する(150、200℃のとき、それぞれ、湛水培養r=0.61**, 0.11、湿潤培養でr=0.40**, 0.11)。
- 以上から、風乾土を水分測定条件と同じ105℃・1日乾熱し、塩化カリウム抽出液のアンモニウム態窒素を定量することで、窒素肥沃度を簡便迅速に推定できる。
成果の活用面・留意点
- 本法は、風乾土に対する分析を熱土で行うだけで済み、水分測定に用いる乾熱器以外の新たな設備や技術は不要である。また、土壌の乾熱は水分測定と兼ねられる。さらに、アンモニウム態窒素を試験紙で定量すればより簡便迅速となる。
- 本法は特に簡便性で優れており、実際の農業現場となる数多くの水田において、施肥量調整のために大まかな窒素肥沃度を推定したい場合に適するが、従来の手法と比べて精度で劣り、詳細な窒素肥沃度の評価には適さない可能性がある。
- 乾熱処理の際は、乾熱器内の温度を事前に上げておき、乾熱期間も正確にする。
- 硝酸態窒素量は105℃・1日で乾熱してもほとんど変化しないので(デ-タ略)、熱土の抽出液の硝酸態窒素量を定量することによって風乾土の硝酸態窒素量を推定できる。
- 福岡県筑後地域を中心とする灰色低地土の結果である。
具体的データ
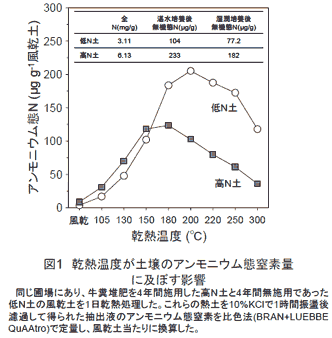
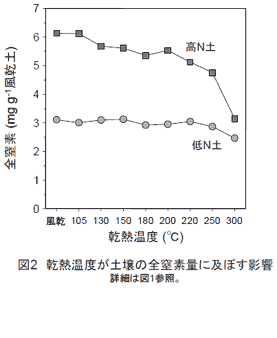
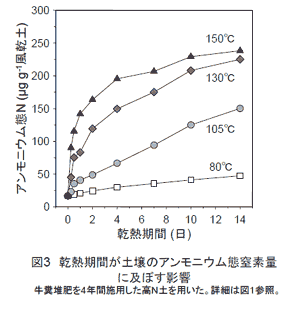
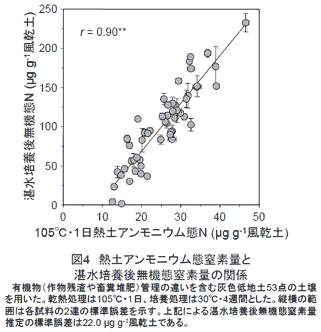
その他
- 研究課題名:地域条件を活かした高生産性水田・畑輪作のキーテクノロジーの開発と現地実証に基づく輪作体系の確立
- 課題ID:211-k
- 予算区分:交付金・基盤
- 研究期間:2001~2006年度
- 研究担当者:原嘉隆、土屋一成、中野恵子、草佳那子
- 発表論文等:原ら(2005) 九州農業研究 67:45.
