TMRの導入の有無および意向別に見た熊本県酪農経営の特徴
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
熊本県では約3割の酪農経営でTMRが導入されている。未導入経営のなかでもTMR導入を考えている経営が14%、導入までは考えていないが関心を示す経営が33%存在し、潜在的なユーザーと想定できる。これら類型間では経営構造、技術水準、TMR技術に対する認知度、食品残さ利用に対する認知度が異なる。
- キーワード:酪農経営、TMR
- 担当:九州沖縄農研・イネ発酵TMR研究チーム
- 連絡先:電話096-242-7574、電子メールkazushin@affrc.go.jp
- 区分:九州沖縄農業・農業経営
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
国産粗飼料と食品残さを用いる新TMR給与技術を普及させるためには、一般的に輸入乾草を用いる既存TMRの導入経営を把握するとともに、未導入経営における潜在的ユーザーの掘り起こしが必要である。そこで、熊本県酪農経営に対して調査を実施し、上記の問題に対する現状を整理するとともに、類型別の特徴を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 調査対象経営の28%が既存TMRを導入しており、未導入経営はその意向別に「関心があり導入してみたい(類型1)」(14%)、「関心はあるが導入までは考えない(類型2)」(33%)、「関心が無い(類型3)」(24%)の3類型がある(表1)。未導入経営の類型1、類型2はその関心度から潜在的なユーザーと想定できる。
- 既存TMRの導入経営は大規模経営が多く、約6割はフリーストール+パーラーという畜舎構成である。また、未導入経営と比較して乳量水準が高い一方で、1頭当たり飼料面積が小さく粗飼料自給率が低い(表1)。
- 未導入経営間で比較すると、①頭数規模で類型1>類型2>類型3、②乳量水準で類型1>類型2≒類型3という傾向がある(表1)。また、TMR技術に対する認知度では類型1で「よく知っている」と回答した経営が82%であるのに対して、類型2、類型3では5割を下回る(表2)。
- TMR未導入経営に対する判別分析(多項ロジット分析)では、判別要因として上記の頭数規模、乳量水準、TMR技術に対する認知度が有意である(表3)。つまり、頭数規模が大きいほど、乳量水準が高いほど、技術に対する認知度が高いほど、導入意向が高まる。
- 調査対象の全ての類型において、食品残さの利用率が1割を下回っている。認知度に関しても、「よく知っている」と回答した経営は3割を下回り、4~5割の経営が「聞いたことはある」程度の認知度である。ただし、TMR導入経営は未導入経営よりも「よく知っている」の回答率が高い(表4)。
成果の活用面・留意点
- 今後の新TMR開発・利用研究における基礎的データである。
- 調査票は平成18年に熊本県867戸の酪農経営に配付され、47%(406戸)の高い回収率を得た。
- 他県においては各類型の構成が異なる可能性がある。
具体的データ
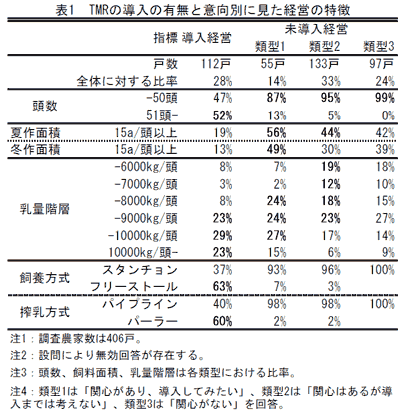
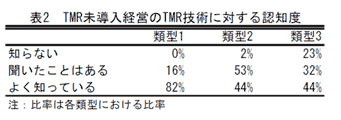
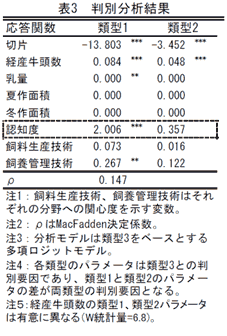
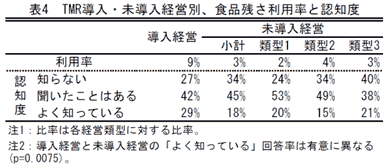
その他
- 研究課題名:暖地における飼料イネ等の発酵TMR生産技術の開発による地域利用システムの構築
- 課題ID:212-b
- 予算区分:基盤、えさプロ、科研費
- 研究期間:2006年度
- 研究担当者:西村和志
