飼料イネ品種Taporuriの2回刈り乾物多収栽培法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
Taporuriの2回刈り栽培では、基肥を多く施用した水田において、4月中旬(4月下旬)に移植し、7月下旬(8月上旬)の穂揃期に1回目を収穫および追肥し、10月下旬(11月上旬)の黄熟期に2回目を収穫することにより、極めて高い乾物収量が得られる。
- キーワード:飼料イネ、Taporuri、2回刈り栽培、乾物収量、栽培法
- 担当:九州沖縄農研・イネ発酵TMR研究チーム
- 連絡先:電話0942-52-0670
- 区分:九州沖縄農業・水田作、共通基盤・総合研究(飼料イネ)、作物・稲
- 分類:技術・普及
背景・ねらい
飼料イネでは、低コスト生産を実現するために、高乾物収量が求められている。台湾の在来品種Taporuriは、乾物生産能力が 高いが、耐倒伏性に問題がある。倒伏は、飼料イネの乾物収量を減少させるだけでなく、ホールクロップサイレージの品質を低下させる。このため飼料イネで は、倒伏を回避した乾物多収栽培技術の確立が必須である。これまでにTaporuriは、2回刈り栽培において、合計乾物収量が高く、倒伏しないことが明 らかになっている。そこで、Taporuriの2回刈り栽培における1回目刈り取り時期、総窒素施肥量、窒素施肥法、1回目刈り取り時の刈り取り高さ、お よび1回目刈り取り時の収穫機による刈り株への踏圧が合計乾物収量に及ぼす影響を明らかにすることにより、Taporuriの2回刈り乾物多収栽培法を開 発する。
成果の内容・特徴
- Taporuriの2回刈り栽培では、穂揃期に1回目を刈り取り、総窒素施肥量は多肥で、1回目に重点的に施肥することにより、極めて高い乾物収量が得られる(図1)。
- 1回目刈り取り時の刈り取り高さは、合計乾物収量に影響しない(図2)。しかし、高品質(推定TDN含有率およびホールクロップサイレージの品質)の2回目(表1)を多く収穫するためには、1回目刈り取り時の刈り取り高さを15cm程度まで高くする。
- 1回目刈り取り時の収穫機による刈り株への踏圧は、2回目の茎数および1茎重に大きな影響を及ぼさないため、2回目の乾物収量に影響しない(図2)。
- 現地におけるTaporuriの合計乾物収量は、機械収穫作業によるロス(坪刈りの約30%)を含めない全刈りで1.8~1.9t/10aと極めて高く、これに伴い推定TDN収量も0.9t/10aと高い(表1)。
- 1回目のホールクロップサイレージは、乾物率が低いが、pHが低下し乳酸含有率が増加するため、品質が良い。また2回目のホールクロップサイレージは、乾物率が高く、十分にpHが低下し乳酸含有率が増加するため、品質が極めて良い(表1)。
- Taporuriの2回刈り栽培では、4月中旬(4月下旬)に移植し、7月下旬(8月上旬)の穂揃期に1回目を収穫し、10月下旬(11月上旬)の黄熟期に2回目を収穫することにより、極めて高い乾物収量が得られる(表2)。
成果の活用面・留意点
- Taporuriの2回刈り栽培の適地は、生育期間の気温が高い九州南部である。
- 苗箱播種量は、Taporuriの籾重が食用品種に比べ小さいので、少なくする。
- Taporuriは、茎数が多く長稈であるため、疎植する。
- 1回目刈り取り時には、十分に落水し、収穫機が入れるようにする。
- 1回目刈り取り後の入水は、再生芽が十分に出現してから行う。
- Taporuriの種子は、農業生物資源ジーンバンクから配布された品種である。
具体的データ
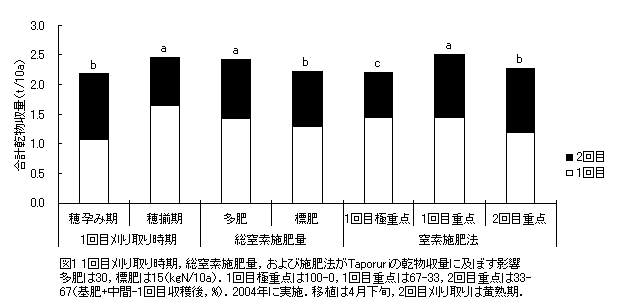
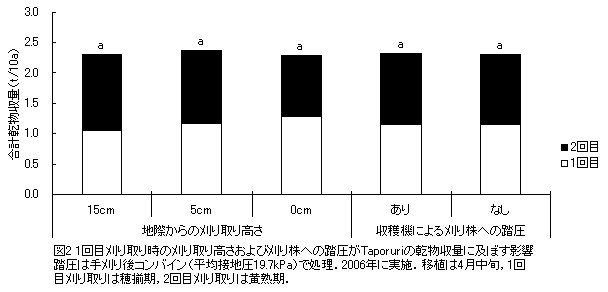
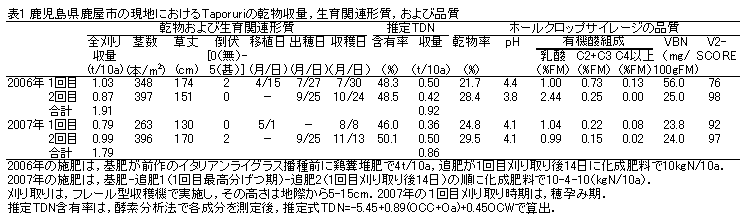
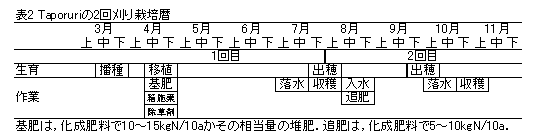
その他
- 研究課題名:暖地における飼料イネ等の発酵TMR生産技術の開発による地域利用システムの構築
- 課題ID:212-b
- 予算区分:基盤、委託プロ(ブラニチ、えさプロ)
- 研究期間:2003~2007年度
- 研究担当者:中野洋、森田敏、佐藤健次、服部育男、楠田宰、北川壽、高橋幹
- 発表論文等:
Nakano H. and Morita S. (2007) Field Crops Res. 101 (3): 269-275.
Nakano H. and Morita S. (2008) Field Crops Res. 105 (1-2): 40-47.
