最確数法と制限酵素断片長多型分類法を組み合わせた微生物相の同定・定量法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
最確数法と断片長多型分類法を組み合わせ多岐に渡る微生物相を同定・定量できる方法を開発した。本法は、試料に含まれるPCR阻害物質量に影響されず、死菌や増殖能を欠落した菌に由来する擬陽性が無く、雑多な病原微生物を含む試料を安全に同定・定量できる。
- キーワード:最確数法、断片長多型分類法、同定・定量法
- 担当:九州沖縄農研・九州バイオマス利用研究チーム
- 連絡先:電話096-242-7768
- 区分:九州沖縄農業・畜産草地、バイオマス
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
有機性廃棄物の効率的な再資源化や、有害微生物を含む畜産廃棄物等の処理を安全・効率的に行うには、処理工程や安全性に関与する 多様な微生物相を簡便に同定・定量する方法の確立が必要であるが、微生物相の解析法であるDGGE法やT-RFLP法では、菌群を定量化することはでき ず、定量法として用いられるリアルタイムPCR法等では、検出対象となる特定の微生物以外の大多数の微生物相についての情報が得られない。よって多岐に渡 る微生物相の同定・定量が同時に可能な方法を開発する。
成果の内容・特徴
- 段階的に希釈されたDNAをユニバーサルプライマーでPCR増幅後、制限酵素で切断し、複数種の細菌由来断片を含む制限酵素 断片パターンから選抜した単一遺伝子由来の断片データを用い類縁性検索(渡邊・奥田:国内特許第3431135号;米国特許第7006924号)した結果 を、希釈段階毎に集計し最確数法で定量することで多岐に渡る微生物相が同定・定量できる(図1;1-①、②)。試料から直接抽出したDNAはPCR阻害物質による増幅効率の変動が大きいため、選択培地で培養後、抽出したDNAを用いている(図1;2-①、②、③)。
- 本法は混入するPCR阻害物質による擬陰性が無く、他の遺伝子解析法と異なり試料(土壌、堆肥、家畜糞、様々な有機性廃棄物等)を選ばず同一操作で定量できる。
- 本法は培地を代えることで、大きな細菌相の変化(堆肥化の工程等:表1)から、胞子状態/栄養増殖状態にある菌相等の同定・定量等、幅広い用途に用いることが出来る。また他の遺伝子解析法と異なり、増殖が早い微生物を優先的に解析しているため、死菌や増殖能を欠落した菌に由来する擬陽性が無い。
- 本法では菌を分離することなく混合系のまま類縁性検索を行うため、雑多な病原微生物を含む試料の同定・定量が培養法とくらべ安全に解析できる(図1)。
成果の活用面・留意点
- 適切な培地を選択することで様々な機能性微生物群の質と量が同時に把握できるため微生物指標として活用できる。
- 様々な試料に含まれる抗生物質耐性菌等の有害微生物のリスク評価法として利用できる。
- 記載したプライマーは全体概要を把握するための一般細菌用のユニバーサルプライマーで、病原遺伝子等に特異性が高いプライマーとデータベースを用いることで病原菌の感染ルートの特定等の高精度な同定・定量が要求される場合にも利用できる。
- 記載したプライマーで増幅されない一部の古細菌等や糸状菌等の真核生物では使用するプライマーに対応したデータベースを渡邊・奥田の方法で編集する。
- 類縁性解析の精度は機器の精度・解像度や一度に解析できる試料量に大きく依存しており、微生物取り扱い技術、遺伝子取り扱い技術の習得が無い機関等への普及技術とするためには、データ選抜アルゴリズム等のデータ処理プログラムの開発が必要となる。
具体的データ
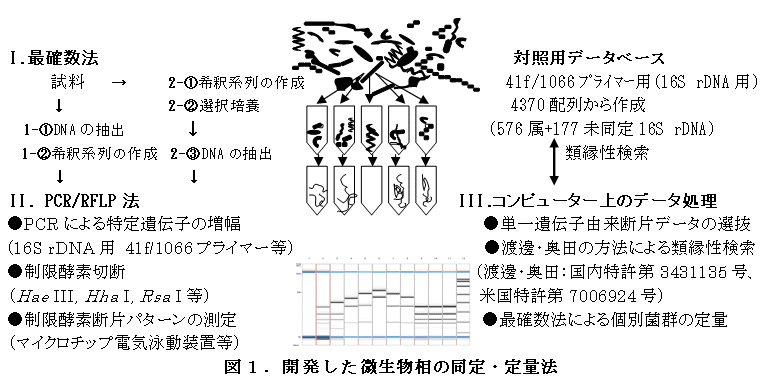
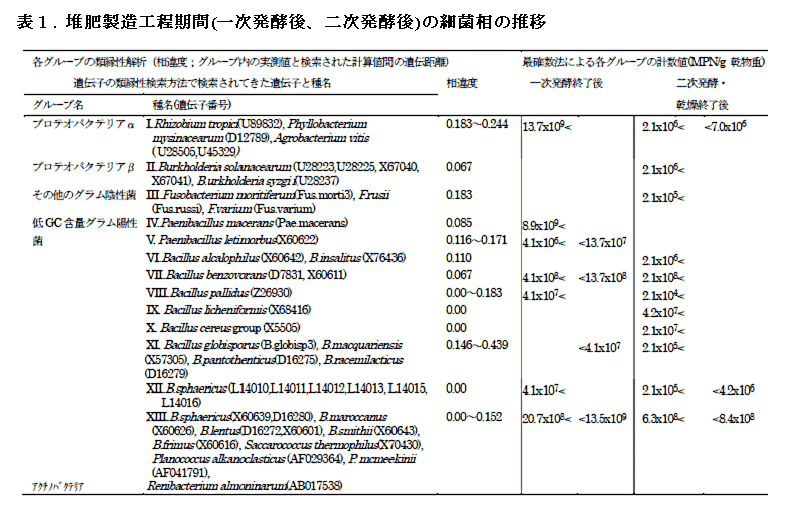
その他
- 研究課題名:暖地における畑作物加工残さ等地域バイオマスのカスケード利用・地域循環システムの開発
- 課題ID:411-d
- 予算区分:運営費交付金
- 研究期間:2005~2007年度
- 研究担当者:渡邊克二、田中章浩、薬師堂謙一、田村廣人
- 発表論文等:Watanabe K.et al. (2008) Soil Sci.Plant Nut. 202-213, 54(2)
