スクミリンゴガイは耐寒性上昇時に体内にグリセロールを蓄積する
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
スクミリンゴガイは、耐寒性上昇時に体内のグリコーゲンを消費しグリセロール濃度を上昇させる。数種類の遊離アミノ酸濃度も耐寒性上昇に伴い増減する。
- キーワード:スクミリンゴガイ、耐寒性、グリセロール、グリコーゲン、遊離アミノ酸
- 担当:九州沖縄農研・九州水田輪作研究チーム、難防除害虫研究チーム
- 連絡先:電話096-242-7732
- 区分:九州沖縄農業・病害虫、九州沖縄農業・水田作
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
スクミリンゴガイは1980年代に日本に侵入して以来、西日本を中心にイネの重要害貝となっている。本種は冬期に耐寒性を上昇さ せて越冬するため、本種の耐寒性メカニズムの解明は、冬期の防除技術開発に重要である。そこで、昆虫で知られている耐寒性関連物質に注目し、本種の耐寒性 上昇に伴うそれらの濃度変化を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 低温順化処理(25℃5日間→20℃5日間→15℃5日間(温度低下終了)→10℃4週間)により実験的に耐寒性を付与したスクミリンゴガイにおいて、耐寒性の上昇に伴い、体内のグリコーゲン濃度の減少とグリセロール濃度の上昇がみられる(図1)。
- 水田で採集した貝においても、耐寒性上昇に伴い、同様の体内成分の変化がみられる。(図2)。以上から、スクミリンゴガイは耐寒性を高めるために栄養貯蔵物質であるグリコーゲンを消費し、グリセロールを生産していると考えられる。
- グリセロールは、昆虫をはじめ多くの生物で耐寒性上昇に機能していることが知られており、スクミリンゴガイにおいても耐寒性に関与していると思われる。
- グルコースも耐寒性関連物質として知られているが、本種の耐寒性上昇に対する直接的な関与はない。(図1、2)。
- 耐寒性上昇に伴い、遊離アミノ酸の1種であるグルタミンが上昇し、フェニルアラニンは減少する。その他のアミノ酸は耐寒性と関連する濃度変化はしない(データ略)。
成果の活用面・留意点
- 冬期のスクミリンゴガイ耐寒性上昇のメカニズムの解明や防除技術開発のための基礎的知見となる。
- 本研究は、淡水生の巻貝で耐寒性上昇に伴う低分子化合物の変化を明らかにした最初の事例であり、今後淡水生貝類の耐寒性メカニズム解明のための貴重な知見となる。
具体的データ
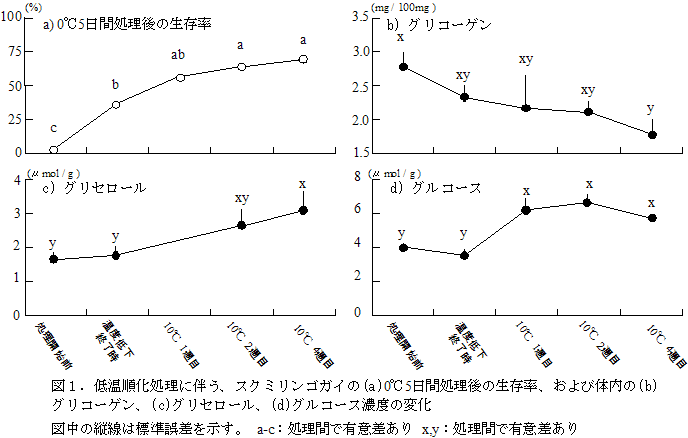
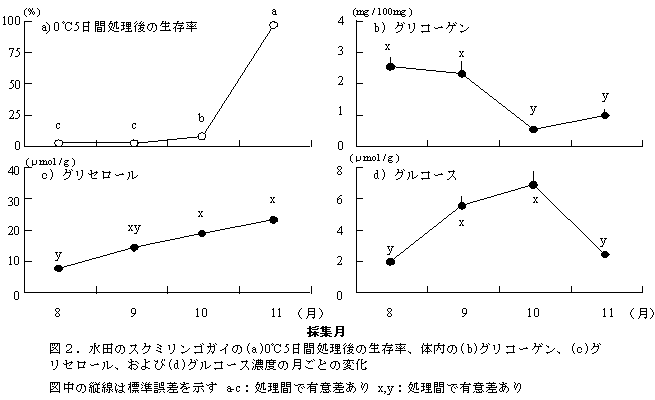
その他
- 研究課題名:地域条件を活かした高生産性水田・畑輪作のキーテクノロジーの開発と現地実証に基づく輪作体系の確立
- 課題ID:211-k
- 予算区分:交付金、基盤
- 研究期間:2005~2007年度
- 研究担当者:松倉啓一郎、和田 節
- 発表論文等:Matsukura et al. (2008) Cryobiology 56:131-137
