半矮性インド型水稲品種「タカナリ」による多収実証
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
多肥条件において、半矮性インド型水稲品種「タカナリ」は高温多照の1994年には粗玄米重990g/m2という超多収性を示した。本品種は面積当たり全籾数が多く、さらに登熟期間の乾物増加量が大きいことが超多収性の要因であった。しかし、低温少照の1993年には障害不稔が多発し、低収にとどまった。
- 担当:農業研究センター・作物生理品質部・稲栽培生理研究室
- 連絡先:0298-38-8952
- 部会名:作物生産
- 専門:生態
- 対象:稲類
- 分類:研究
背景・ねらい
稲作のより一層の低コスト化を図るためには、収量の増加による土地生産性の向上も有効な手段である。そのため、温暖地東部で栽培可能な多収水稲品種・系 統の生産力を種々の条件下で比較することにより、超多収水稲品種に求められている生理生態的特性を明らかにして、品種育成に資するとともに、超多収栽培法 を確立する必要がある。本研究では、1990年に品種登録された半矮性インド型品種「タカナリ」の超多収性を実証するとともに、その生育特性を日本型の多 収性品種で出穂期がほぼ同じである「コチヒビキ」と比較した。
成果の内容・特徴
- 多肥条件で実施した本研究では、穂重型である「タカナリ」の面積当たり全籾数は「コチヒビキ」より平均して38%多かった。このため、粗玄米収量 は「コチヒビキ」を平均して23%上回り、特に高温多照であった1994年の5月移植区では全研究期間で最高の粗玄米重990g/m2を記録した。 しかし、1993年の4月移植区では、出穂前後の低温少照により、「コチヒビキ」では比較的少なかった障害不稔が「タカナリ」に多発し、308g/m2と低収であった。この事例を除くと収量比率は31%増となり、籾数の増加が収量増に結びついていた(表1)。
- 1994年5月移植区の面積当たり全乾物重は、出穂期までは両品種間に大きな差はなかったが、倒伏の影響のない出穂後の2週間の全乾物 増加量は「タカナリ」の方が「コチヒビキ」より大きく、さらに「コチヒビキ」が登熟中期に倒伏し始め、その後の全乾物増加量が小さくなったため、成熟期に は大きな差となった。また、「タカナリ」の面積当たり全籾数が多いため、この期間の高い乾物生産能力を穂重の増加に利用することができた(図1)。
- 気象条件が大きく異なった全研究期間を通じて、障害不稔が多発した試験区以外では「タカナリ」は登熟期間の全乾物増加量(茎葉への再蓄 積量を除く)が「コチヒビキ」より大きく、さらに同期間の転流量(茎葉乾物重の減少量)も「コチヒビキ」と同程度であり、面積当たり全籾数の多さに十分見 合う乾物生産・転流特性を備えていると考えられた(図2)。
成果の活用面・留意点
土地生産性を向上させるために求められている安定多収品種の育成・選抜の基礎的知見となる。
「タカナリ」は障害不稔に弱いので、超多収性を発揮させるためには出穂前後に低温に遭遇しやすい栽培条件は避ける。また、本品種は日長感受性が低く、晩植・晩播栽培では出穂が他の品種より遅れて登熟不良になりやすいので注意する。
具体的データ
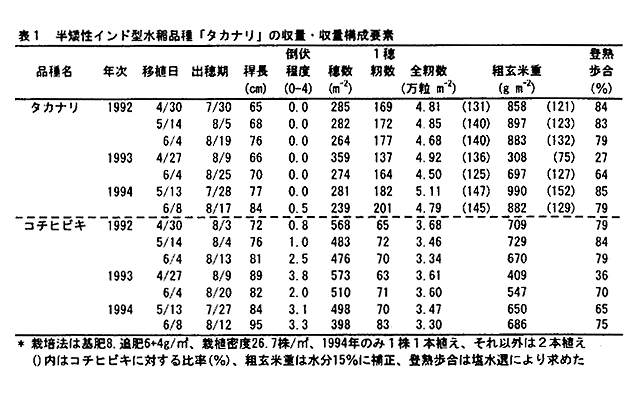
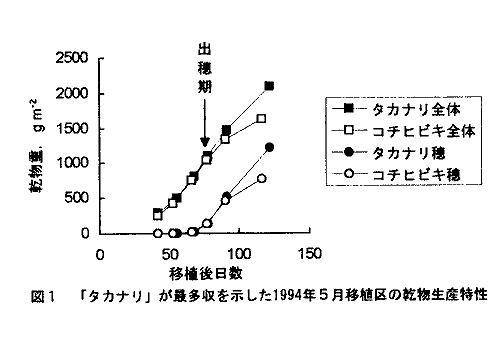
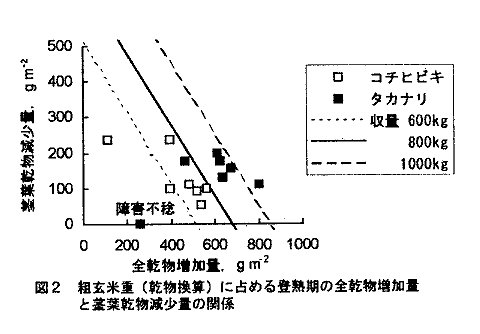
その他
- 研究課題名:温暖地東部向き育成系統の超多収性の検定と栽培特性の解明
- 予算区分 :総合的開発研究(新形質米)
- 研究期間 :平成6年度(平成4年~6年)
- 発表論文等:温暖地における水稲超多収系統の乾物生産特性、日本作物学会紀事、
62巻(別1):82-83,1993
