イネいもち病菌のnit変異菌株作出培地の改良
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
イネいもち病菌の生態的研究のためのマーカーとして有用なイネいもち病菌のnit変異菌株(硝酸塩利用能欠損変異株)を高頻度に作出できる培地を開発した。
- 担当:農業研究センター・病害虫防除部・水田病害研究室
- 連絡先:0298-38-8940
- 部会名:生産環境
- 専門:作物病害
- 対象:稲類
- 分類:研究
背景・ねらい
塩素酸塩に耐性の変異株であるnit変異菌株は一般の糸状菌と異なり塩素酸塩を含んだ培地上でも生育できるため、糸状菌の動態解明のためのマーカーとし て使用されている。いもち病菌の圃場内での動態や無性的変異機構解明を効率的に進めるためにも、nit変異菌株が有効である。イネいもち病菌のnit変異 菌株の作出はDaboussiら(1989)による報告があるが、当研究室保存のイネいもち病菌ではnit変異菌株が得られなかった。そこで新たに的確に nit変異菌株が得られるイネいもち病菌nit変異菌株作出用培地を開発する。
成果の内容・特徴
- 今回、新たに開発したnit変異菌株誘導用培地、nit変異菌株検定用培地を用いてイネいもち病菌のnit変異菌株の作出に成功した(第1表、第2表)。新培地はいもち病菌の最少培地を基に開発した。
- nit変異菌株作出手順は次のようである(第1表)。 供試いもち病菌→ジャガイモ寒天培地で培養→nit変異菌株誘導用培地(MMC)へ移植、25°Cで培養→nit変異誘導→培養約4週間→菌叢生育(変異菌 株)→nit変異菌株検定用培地(MM)へ移植、25°Cで約1週間培養→素寒天培地での培養類似の極く薄い菌叢発達→nit変異菌株→ジャガイモ寒天培地 で保存。
- 菌株によりnit変異菌株出現率にばらつきがみられた(第3表)。
- 作出されたnit変異菌株では継代培養2~3代で野生株へ復帰するものが多いが継代7代まで安定している菌株もある。またイネ体上では nit変異菌株の菌叢接種では安定性が高いが、病斑上に形成される分生胞子では野生株への復帰菌株とnit変異菌株が混在している場合が多い。
成果の活用面・留意点
生態的研究や菌糸融合のためのマーカーとして利用する際には、形質の安定したnit変異株を使用する必要がある。
具体的データ
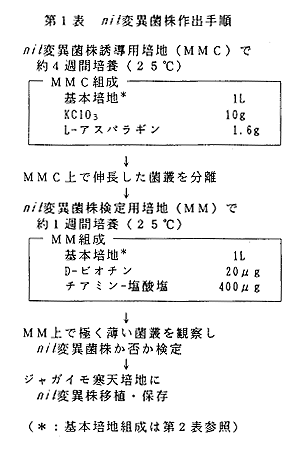
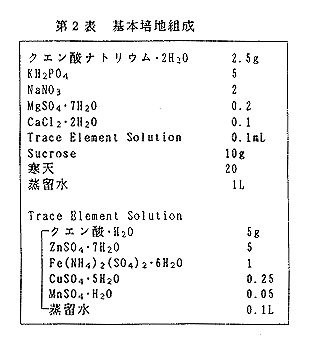
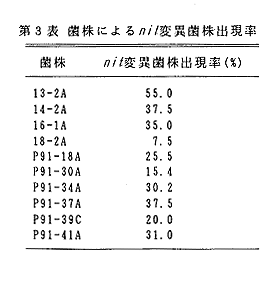
その他
- 研究課題名:いもち病流行機構の解明
- 予算区分 :経常
- 研究期間 :平成6年度(昭和63~平成4~(平成10))
- 発表論文等:イネいもち病菌のnit変異株の作出 日本植物病理学会報 第59巻
第6号 1993(講要)
