イネのツマグロヨコバイ耐虫性遺伝解析のための簡易幼苗個体検定法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ふ化幼虫放飼3~4日後の生存率と幼虫発育程度(2齢到達率)を調査することにより、幼苗期においてツマグロヨコバイ耐虫性程度をイネの個体レベルで正確かつ簡易に判定できる。
- 担当:北陸農業試験場・水田利用部・虫害研究室
- 連絡先:0255-26-3243
- 部会名:生産環境
- 専門:作物虫害
- 対象:稲類
- 分類:研究
背景・ねらい
イネのツマグロヨコバイ耐虫性の検定には、幼虫の生存・死亡を調べる抗生作用検定と、虫の寄主選好反応を利用した非選好性検定がある。耐虫性の遺伝分析を行う場合、解析に用いるイネ雑種集団の個体ごとの耐虫性程度を正確に判定する必要がある。これまでの抗生作用検定は生存率が連続的に分布するため、生存率のみの判定では、耐虫性個体と感受性個体とを正確に判別することが困難であった。耐虫性品種上にツマグロヨコバイ幼虫を放飼すると、幼虫が死亡しない場合でも生存虫の発育が遅延する。そこで、幼虫の生存率とともに生存虫の発育程度を指標とする検定法の開発を試みる。
成果の内容・特徴
- 1.8*18cmの試験管に第2葉期のイネ幼苗と水0.5mlを入れ、ふ化1日以内の1齢幼虫5頭を放飼する(25°C)。
- 感受性品種上では、ふ化幼虫は3~4日後に1齢から2齡に発育することから(図1)、放飼3~4日後に2齡に到達した幼虫個体数を幼虫発育程度の指標とする。
- この検定法の精度を確認するため、ツマグロヨコバイ耐虫性系統である水稲中間母本農6号(以下中母農6号)と感受性品種トヨニシキを交配したB1F1雑種集団(トヨニシキ/中母農6号//トヨニシキ)80個体について、幼苗期(第2葉期)に耐虫性検定を行い、その後生育中期及び出穂前期に従来法による検定を行い、両者の値を比較した。幼苗期において3日後の幼虫生存率及び2齢到達率から、耐虫性個体と感受性個体とが明確に分離した(図2)。また、幼苗期の検定で耐虫性、感受性と判定された個体は、生育中期及び出穂前期の検定においても同様に判定された。
- この検定法を用いると、従来法と同程度の労力で、より高い精度で耐虫性の判定ができる。
成果の活用面・留意点
本検定法はイネの個体レベルで耐虫性が判定できるため、遺伝解析に用いられるとともに、雑種集団における簡易選抜法としても活用することができる。
具体的データ
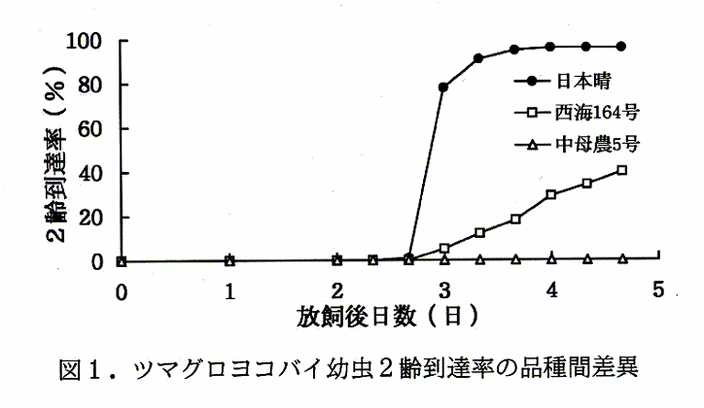
図1:ツマグロヨコバイ幼虫2齢到達率の品種間差異
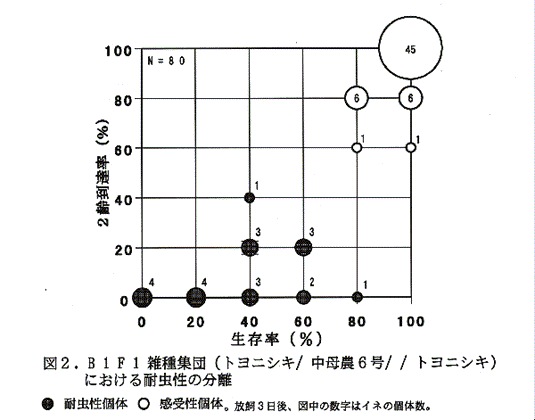
図2:B1F1雑種集団(トヨニシキ/中母農6号//トヨニシキ)における耐虫性の分離
その他
- 研究課題名:分子マーカー利用によるイネのツマグロヨコバイ耐虫性の遺伝的機構の解明
- (重要基礎)水稲の耐虫性利用によるツマグロヨコバイ制御技術の開発(経常)
- 予算区分 :科振調(重点基礎)、経常
- 研究期間 :平成8年度(平成7~8年)、平成8年度(平成6~10年)
