植物-濾材系(バイオジオフィルター)水路の窒素浄化機能の強化
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
植物-濾材系水路に生育時期の異なる資源作物・花卉等を栽植し、生育の衰えた植物から順次植え替えることで、窒素浄化機能を高く維持できた。さらに、稲わら等の水路中流への補填は、冬期の窒素除去速度を高め、年間の浄化機能の安定化に役立つことを明らかにした。
- 担当:農業研究センター・土壌肥料部・水質保全研究室
- 連絡先:0298-38-8829
- 部会名:生産環境
- 専門:環境保全
- 対象:
- 分類:行政
背景・ねらい
農村地域の都市化、混住化等に伴い、生活系排水による農業用水の汚濁が進行し、その対策が急がれている。バイオジオフィルター水路は、幅40~50cm、水深30cm程の水路内に濾材を充填し資源作物や花卉を栽植した水路で、植物・濾材・微生物の働きにより排水中の窒素等の浄化を行うことができる。本研究では、植物の栽植組み合わせや稲わら等の補填により、年間の水質浄化機能の安定化を図る水路の管理法について検討した。
成果の内容・特徴
- 夏~秋にパピルスを栽植し、冬~春に半分をハナナに植え替えたバイオジオフィルター水路の窒素除去速度は、パピルスの生育旺盛な8~9月には0.65g・m-2・d-1と高まり、窒素濃度1mgL-1前後の良好な処理水が得られた。一方、パピルス移植直後や冬期(12~1月)には著しく低下した(図1)。
- パピルス、ケナフ、マリーゴールド、イタリアンライグラス、ハナナ等生育時期の異なる植物を栽植し、生育の衰えた植物から順次植え替えることで、水路の窒素除去速度を高く維持できた(図2)。
- 稲わらと再生紙の水路中流(3.7~4.0m流下地点)への補填は、植物の浄化機能が低下する冬期の窒素除去速度を高め、流出水の窒素濃度は、稲わら等補填前(10/25~11/7)の14.0mgL-1から、稲わら等補填後(11/15~29)には8.9mgL-1に改善できた(図2、図3)。
- 本水路の年間の平均窒素除去速度は0.72 g・m-2・d-1、また、冬期(12~2月)の平均窒素除去速度も0.6g・m-2・d-1となり、年間の浄化機能の安定化が図れた(図2)。
- 水路中流に稲わら等補填後も、流出水の全有機炭素(TOC)濃度はほとんど上昇せず、水路外への顕著な流出は認められなかった。
成果の活用面・留意点
- 本試験は、茨城県つくば市のガラス室内で実施し、12~2月はガラス室の窓を閉め、他の期間は解放した。実用に際しては、冬期に水路をビニールハウス等で覆う必要がある。
- 本試験には、生活系排水の2次処理水を模した人工汚水を用いた。
具体的データ
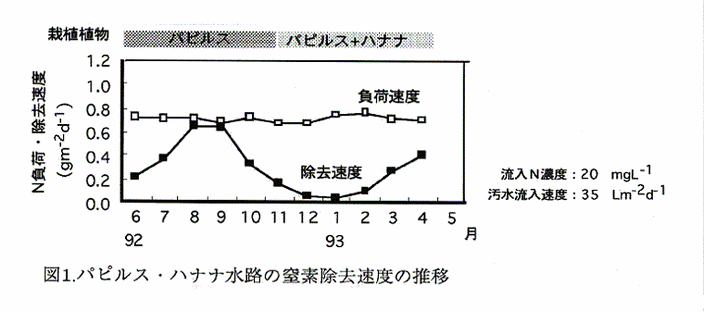
図1:パピルス・ハナナ水路の窒素除去速度の推移
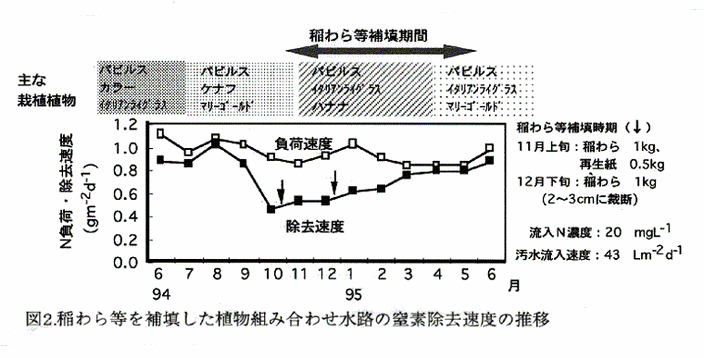
図2:稲わら等を補填した植物組み合わせ水路の窒素除去速度の推移
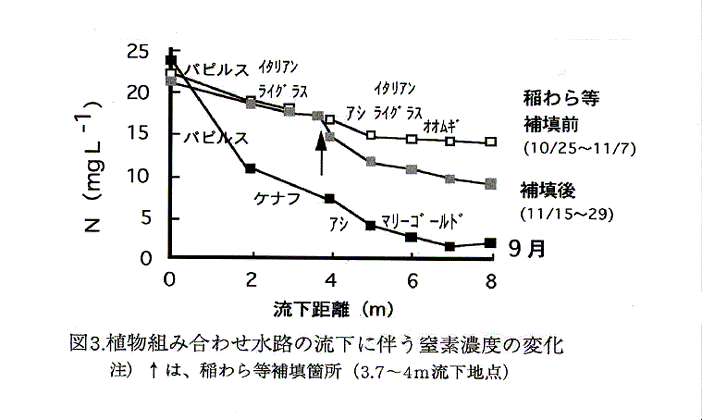
図3:植物組み合わせ水路の流下に伴う窒素濃度の変化
その他
- 研究課題名:資源循環・アメニティー保全型水質浄化技術の開発
- 予算区分 :経常・国県共同研究
- 研究期間 :平成8年度(平成4~8年)
