中山間地域の活性状況別にみた観光施設の稼働状況
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
観光施設の内容及び市町村の活性状況によって,観光用施設の事業費や年間利用者数,費用調達方法,営業収入,従事者構成,村外からの定住状況等で明らかな差異がみられた。
- 担当:農業研究センター・プロジェクト研究第5チーム
- 連絡先:0298-38-8856
- 部会名:総合研究
- 専門:農村計画
- 分類:行政
背景・ねらい
近年,観光開発で活路を見出そうとする動きが中山間市町村に限らず,全国的に広がっている。しかし,この効果が定量的に把握されているとは言い難い。そこで,アンケート調査(平成6年12月実施,回収市町村数1,250,回収率75%)結果をもとに施設整備費用,費用の調達方法,施設の整備者と管理者,利用者数,営業収支,従事者数等の実態を明らかにする。また,観光開発の中でも集客力を始め住民雇用や地場農産物利用に及ぼす効果が大きいと考えられる宿泊施設について,施設の種類,月別利用者数,営業収入,従事者数等を分析し今後の観光開発のあり方を探る。
成果の内容・特徴
観光開発については800市町村から1,094施設,また,宿泊施設については1,158市町村から1万2千施設の回答があり,施設別にカード形式でデータベース化を図り分析を行った。
- 観光施設区分別の開発実態
施設区分毎の開発件数をみると,最も多いのはキャンプ場であり,全施設数の11.4%を占めている(図1)。事業費百万円当たりの年間利用者数が多い施設は,橋梁,観光センター,観光農園等であり,逆に少ない施設としては,ゴルフ場や公共性の高いスポーツ関係施設,文化施設があげられる(図2)。 - 施設利用者数及び営業収入
村外者の利用率は活性化市町村が64%であるのに対し,非活性市町村は80%に達しており,観光開発が交流人口の増加を主目的とするのであれば,非活性市町村では十分にその役割を担っているといえる(図3)。しかし,非活性市町村にとって最重要なのは住民の所得向上であり,観光施設そのものの収益性を向上するとともに,土産物販売等を通じて関連産業が発展する仕組みを作ることが重要である。 - 従事者数
村内正職員の比率は活性化状況にかかわらず31%程度でほぼ等しい(図4)。施設当たり従事者数は非活性市町村が4.7人に対し活性化市町村は9.0人である。また,村外者の定住率は活性化市町村が全従事者の2.1%,非活性市町村は0.7%である。このことは,非活性市町村における観光開発は,交通条件や自然的条件から大規模施設等の開発や誘致が困難であり,小規模施設の開発に止まらざるを得なく,従事者の雇用も自ずと限界があるといえる。 - 宿泊施設の客室数、収容定員、年間稼働率
年間稼働率の全施設平均は19.3%であるが,国民休暇村(51.2%)や保養センター(47.1%)等の公共的な施設で高く,ペンション(12.3%)や民宿(12.5%),農家民宿(14.8%)は極めて低い(図5)。また,月別の宿泊状況をみると,国民宿舎は変動が少ないのに対して,ペンションと農家民宿は1~3月及び8月にピークがあり,さらに,民宿では7・8月の利用者が年間の39.5%を占めている(図6)。 - 宿泊施設における村外からの定住状況及び営業収入
村外からの定住率は全施設を平均すると5.0%であるが,ペンションでは17.3%を占めている。一方,年間営業収入は,ペンションと農家民宿が1千3百万円,民宿が1千万円である。また,宿泊料金(一泊二日)はホテル・旅館が11,700円,ペンションが9.800円,民宿が7,800円,農家民宿が6,400円,国民休暇村が4,500円であるが,キャンプ場は850円に過ぎない。
成果の活用面・留意点
国や自治体等が観光開発を計画する際の参考資料となる。
具体的データ
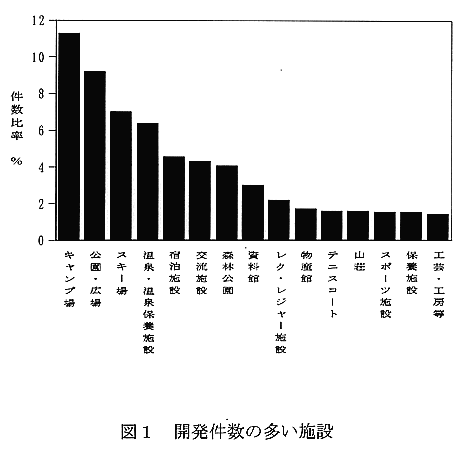
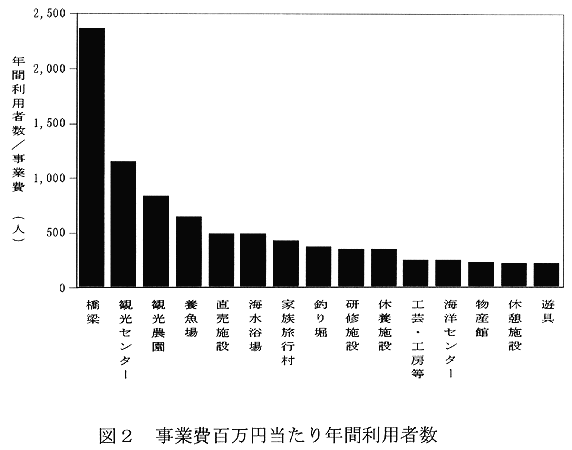
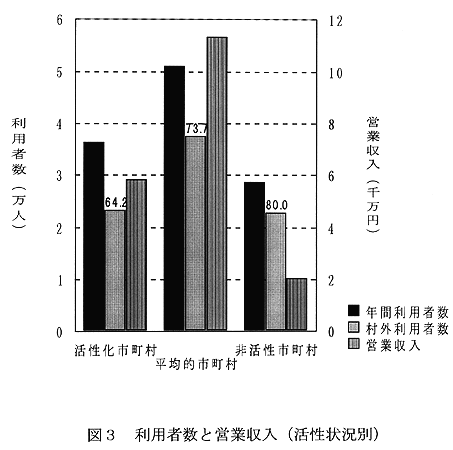
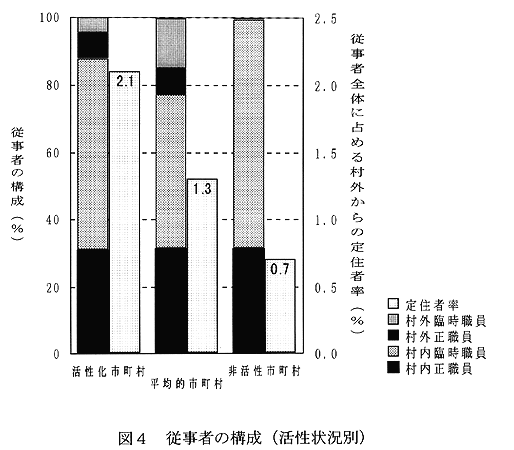
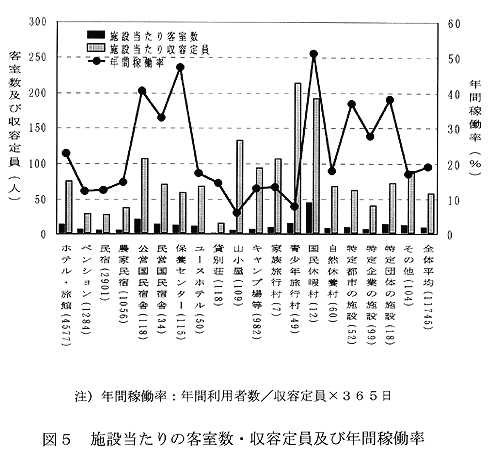
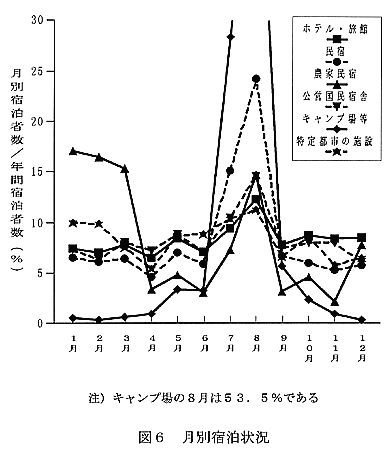
その他
- 研究課題名:条件不利地域における政策的支援手法の開発
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成9年度(平成9年~10年)
