出芽期間の低酸素ストレスによる大豆の生育及び子実生産の低下
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
大豆は出芽期間に低酸素ストレスを受けると、根系発達が抑制され、その後の生育も不十分となり、子実収量も大きく低下する。しかし、トウモロコシではこのような現象は見られない。また、大豆の出芽期間の低酸素ストレス抵抗性には、明瞭な品種間差が認められる。
- 担当:農業研究センター・作物生理品質部・豆類栽培生理研究室
- 連絡先:0298-38-8392
- 部会名:作物生産
- 専門:生理
- 対象:豆類
- 分類:研究
背景・ねらい
これまで、作物は多少出芽が遅れても、出芽さえすれば、その後の生育はあまり影響を受けないと考えられてきたため、出芽勢向上には充分な注意が払われてきていなかった。ところが、水田転換畑の大豆は、過湿や湛水による土壌酸素の不足によって出芽が遅れると、その後の生育が劣ることが多い。そこで、大豆の出芽期間の酸素条件がその後の生育に大きく影響することを、トウモロコシとの比較で明らかにしようとした。また、出芽期間の酸素不足に対して抵抗性を持つ大豆系統を見いだそうとした。
成果の内容・特徴
- 出芽期間中(播種から出芽するまで)に、酸素濃度約21%の通常の空気及び窒素ガスで酸素濃度5%に調整した空気を通気させながらパーライト培地で出芽させると、大豆では出芽した時点の根の発達が、酸素濃度5%区では21%区より劣り、とくに側根数で著しい(表1)。
- 開花期においても、大豆では酸素濃度5%区は21%区に比べて地上部重、根乾物重、根長が3~4割劣る。一方、トウモロコシでは、出芽期間の酸素濃度は開花期(絹糸抽出期)の生育にあまり影響しない。
- 大豆の出芽期間中の低酸素ストレスは、子実重にも大きく影響し、酸素濃度5%区が21%区より25%ほど劣る(表2)。大豆出芽期間の酸素ストレスの影響は、圃場においては一層顕著である。しかしトウモロコシでは、登熟中期でも低酸素ストレスの影響は見られない。
- 出芽期間の低酸素ストレスの影響は、大豆の品種によってかなり異なり、タチナガハ、エンレイ、タマホマレで大きく、五葉黒豆、白鶴の子、ペキンなどでは小さい(図1)。
成果の活用面・留意点
大豆の多収技術の改善、ならびに低酸素ストレス抵抗性大豆育成のための基礎資料となる。
具体的データ
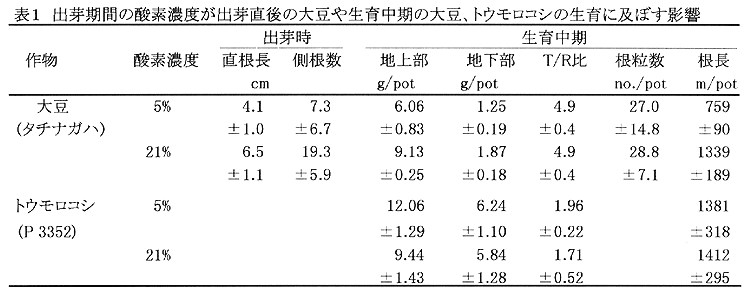
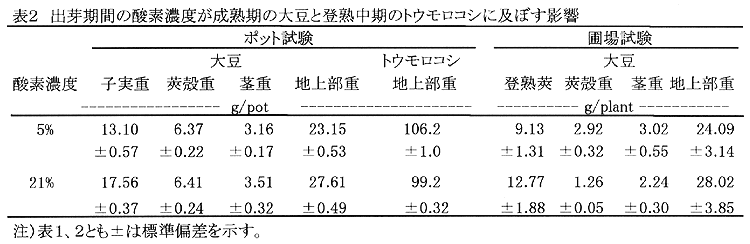
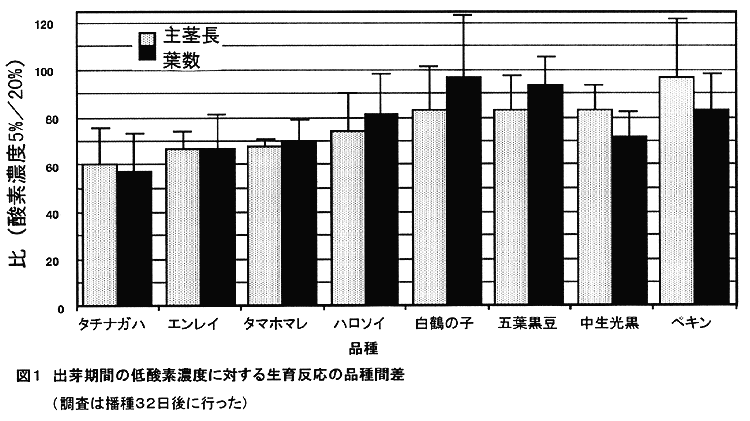
その他
- 研究課題名:根系機能と土壌環境からみた大豆多収要因の解明
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成9年度(平成8~12年度)
