水稲の幼穂長による冷害危険期の推定
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
水稲の幼穂における低温感受性の高い穎花の割合と幼穂長の関係から,幼穂長50~150mmを冷害危険期の指標とすれば,幼穂形成期間の日平均気温によって危険期間と最危険期を推定することができる。
- 担当:農業研究センター・耕地利用部・気象立地研究室
- 連絡先:0298-38-8418
- 部会名:生産環境,作物生産
- 専門:農業気象
- 対象:稲類
- 分類:研究
背景・ねらい
冷害発生時に水管理を行ったり,被害を解析する際には,低温感受性の高い時期(危険期)を把握する必要がある。発育段階の指標として出穂前日数を用いることが多いが,この日数が温度条件により変動し,危険期の開始時期や期間も変化すると考えられる。本研究では幼穂形成始期からの温度条件と幼穂長との関係を明らかにし、冷害危険期推定のための指標を作成した。
成果の内容・特徴
- 幼穂長と低温感受性の高い時期との関係を明らかにするために,4分子期から小胞子前期の花粉を含む穎花を低温感受性の最も高い冷害危険期穎花として,それが1穂中に占める割合(危険期穎花率)と幼穂長の関係を示す(図1)。幼穂長約50mmの時期に穂の先端部付近の穎花が危険期に入り,100mm付近でその割合が最大になり,その後穂の伸長と共に減少する。
- 幼穂形成始期(幼穂長1mm)から幼穂長50mmまでを危険前期,50mmから150mmまでを危険期,100mmの時期を最危険期として,日平均気温と各期間の長さとの関係を示す(図2)。気温の低下にしたがって幼穂の伸長が緩慢になることにより,各時期の日数は日平均気温が1°C低下するごとに1~2日長くなる。この図より、日平均気温の推移から幼穂形成始期を起点として危険期の開始日と継続日数、及び最危険期を推定することができる。
- 主稈の葉耳間長0前後の時期における幼穂長の株内のばらつきを示す(図3)。株内のばらつきには品種間差がみられ,日本晴は他の3品種よりも有意に小さい。晩生の品種ほど株内の出穂日のばらつきが小さくなる傾向があるといわれるが,冷害危険期の幼穂長についても、同様に晩生の品種でばらつきが小さくなると予想される。
成果の活用面・留意点
日平均気温と各期間の長さとの関係については主稈を対象に調査しているため,圃場での危険期の推定には株内,株間の発育の差を考慮する必要がある。
具体的データ
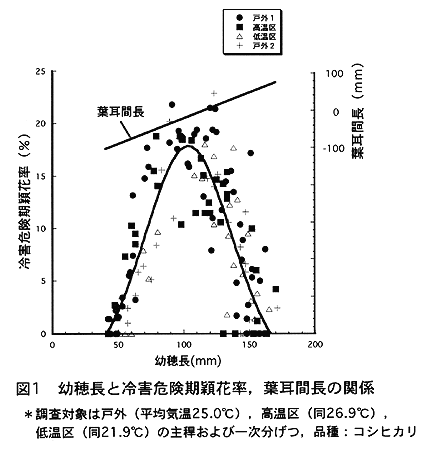
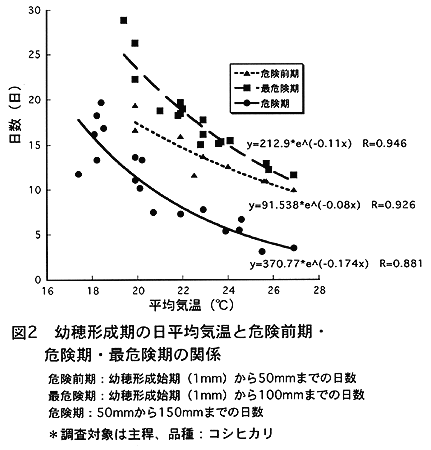
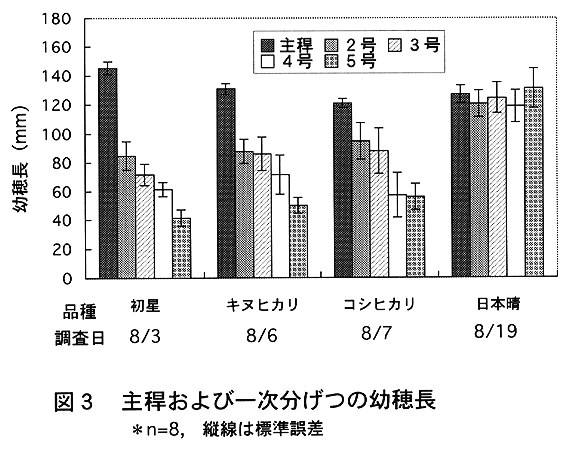
その他
- 研究課題名:冷害発生の気象条件下における水稲の生態・生育反応の解析
- 予算区分:冷害予測
- 研究期間:平成9年度(平成6年~9年)
