水稲直播栽培の定着に影響する要因
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
全国205の直播実施経営を対象としたアンケート調査によると,直播栽培の定着には,単水準,省力化及びコスト削減効果の発現の程度,直播栽培に適した圃場の有無,労力不足の程度が影響している。
- 担当:農業研究センター・プロジェクト研究第1チーム
- 連絡先:0298-38-8512
- 部会名:総合研究,経営
- 専門:経営
- 対象:水稲
- 分類:指導
背景・ねらい
水田作農業の担い手不足が次第に深刻化する中,水稲直播栽培に対する期待が再び高まってきている。しかし直播栽培面積は,近年,1万haに満たない水準で停滞している。このため,水稲直播栽培の定着に影響している要因を明らかにする必要がある。
成果の内容・特徴
直播栽培を行っている全国205の経営体を対象にアンケート調査を実施し,水稲直播栽培の導入目的及びその定着に影響を及ぼしている要因について検討した。
- まず直播栽培実施経営を,「行政等からの要請で試験的に導入している経営(タイプI)」,「試験を目的に自主的に導入している経営(タイプII)」,「移植と組み合わせ経営的に定着している経営(タイプIII)」,「大部分が直播栽培になっている経営(タイプIV)」の4グループに区分し(表1),各グループごとに直播の導入理由を整理した(表2)。タイプIでは「複合部門の拡大」,「転作カウント」が,タイプIIでは「稲作のコスト低減」が,タイプIII及びタイプIVに比べ相対的に高くなっている。これに対し大部分直播に移行したタイプIVでは,水稲の作付規模が小さく,直播の導入理由とて「育苗施設や田植機等が不要」,「労働時間の短縮や作業強度の軽減」,「補助労働力不足」を選択した経営の割合が高い。さらにまた移植と組み合わせた形で直播が定着しているタイプIIIでは,水稲の作付規模が大きく,「稲作のコスト低減」,「労働時間の短縮や作業強度の軽減」,「稲作の規模拡大」を挙げた経営の割合が高くなっている点に特徴がある。
- 直播栽培の定着に影響していると思われる要因を整理すると,表3のようになる。直播が定着しているタイプIII及びIVを,試験段階にあるタイプI及びIIと比較すると,次のような差異がみられる。1タイプIII及びIVは直播の単収水準が高い(移植との単収差が小さい)。2省力化の程度が進んでいる。310a当たりコスト低減効果があると考えている経営が多い。4直播栽培に適した圃場の割合が高い。5「直播栽培導入の必要性(労力面,施設面)が高かった」とする経営が多い。
成果の活用面・留意点
水稲直播栽培の普及・定着を推進する際の参考情報となる。
具体的データ
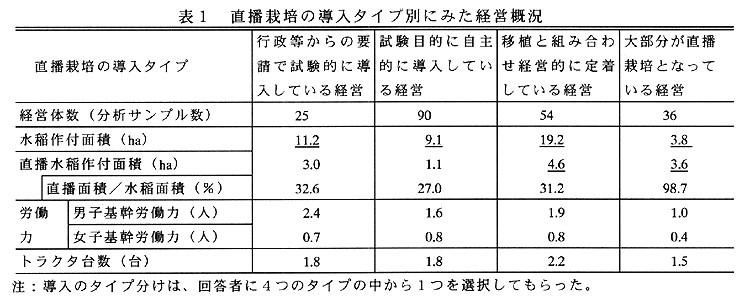
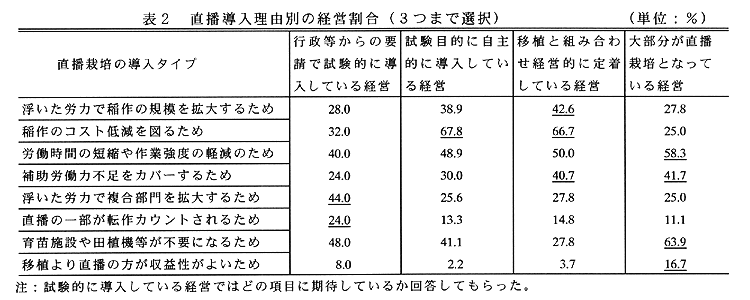
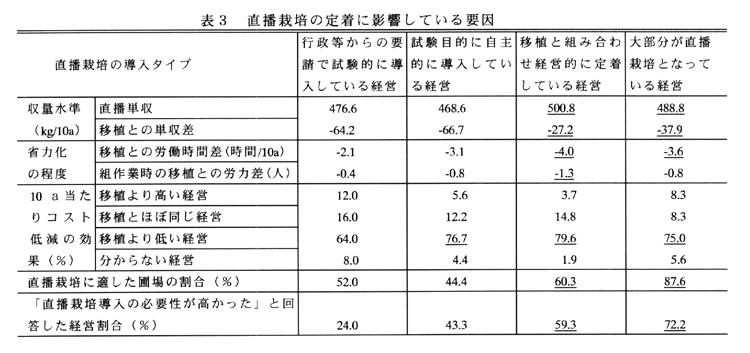
その他
- 研究課題名:大規模低コスト水田営農活性化技術の確立(大規模水田輪作技術体系の確立)
- 予算区分:営農合理化(地域総合)
- 研究期間:平成9年度(平成5~9年)
