評価者の価値観を考慮した生活環境充足意識の評価法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
地域住民の生活環境充足意識をについて,共分散構造モデルを用い,個人の属性や価値観を同時に考慮して把握するための方法を考案し,東広島市の住民 1,200名を対象に実証した。その結果,住民個人の価値観などとの因果関係を含めて生活環境充足意識を的確に把握できることを明らかにした。
- 担当:農業研究センター・農業計画部・農村生活研究室
- 連絡先:0298-38-8419
- 部会名:経営
- 専門:経営
- 分類:研究
背景・ねらい
従来の調査研究では,住民による生活環境の多様な側面の評価や,属性や価値観が評価に及ぼす影響の把握は十分ではない。本研究では,生活環境の総合評価を形成する個別評価項目に共通する評価軸(共通因子)を抽出し,総合評価や個別の評価軸に対する価値観の影響を同時に把握することを目的として,共分散構造モデルを用いた方法を解明する。
成果の内容・特徴
- 環境評価の心理的なプロセスとして以下のような概念モデルを提示した(図1)。
a)地域住民は,生活環境を評価する際,まず自分が住んでいる地域環境に対するイメージ(心理的環境)を評価の判断材料とする。
b)地域住民は,a)の判断材料をもとに価値観を判断基準として生活環境を評価する。
ここで言う「価値観」とは,個々人の意識や行動を一貫したものとしている基本的態度の構成概念として設定したものである。
- 概念モデルに沿った調査のために,生活環境の総合的な充足度や価値観の尺度化,および生活環境評価の個別指標の整理(表1参照)を行い,調査票を作成した(図2)。
- 広島県東広島市の住民 1,200名を対象者とし、訪問配布回収の調査により 1,166票の有効回答を得た(有効回答率97%)。
- まず,30項目の個別指標に対する評価結果に因子分析を適用した結果,I自然環境の保全(自然環境因子),II都市的基盤整備(人工環境因子),III利便性(社会文化的環境因子)の3つの共通因子が抽出できた(表1)。さらに4番目の因子は農地管理,森林管理,伝統文化保存,歴史遺産保存の4項目と関連が強く,農村において人が作り出した生産と文化とを意味する「農村環境因子」と命名した。
- 4つの共通因子を参考にして共分散構造分析を適用した分析結果から,生活環境の総合満足度は自然環境により強く規定され,人為的に作られた農林地などの影響はほとんどみられないことがわかる(図3)。
- 価値観の影響については,自然的な生活を重視する人は,都市的な生活を重視する人よりも都市的利便性を相対的に高く評価し,生活環境の総合的充足度も高い。従って,自然的な生活に価値を置く人は,利便性の向上はあまり望んでいないことがわかる。
成果の活用面・留意点
本方法は,地域性,個人属性,価値観などによる評価の違いを簡潔に示すことで,地域住民が望んでいる環境整備のあり方に関する多様な情報を提供していくために活用できる。
ただし,調査で測定される評価や価値観の尺度の設定に留意し,生活環境評価の共分散構造モデルの説明力を高めていく必要がある。
具体的データ
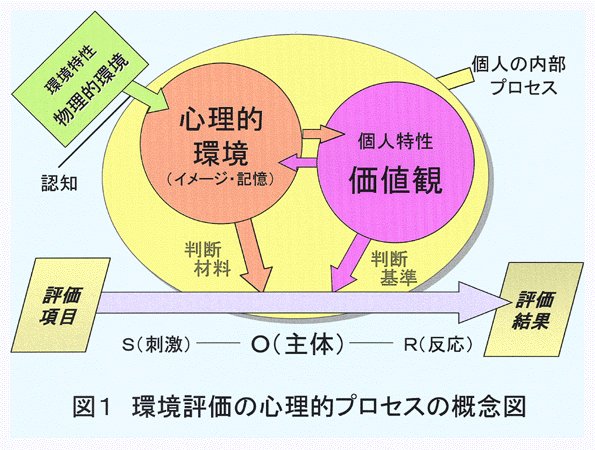
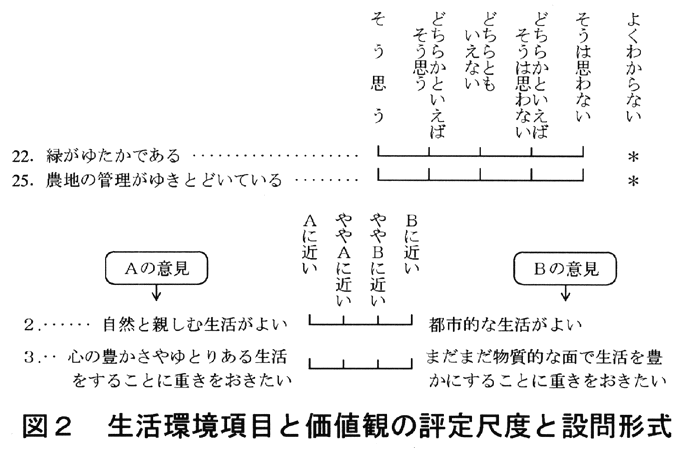
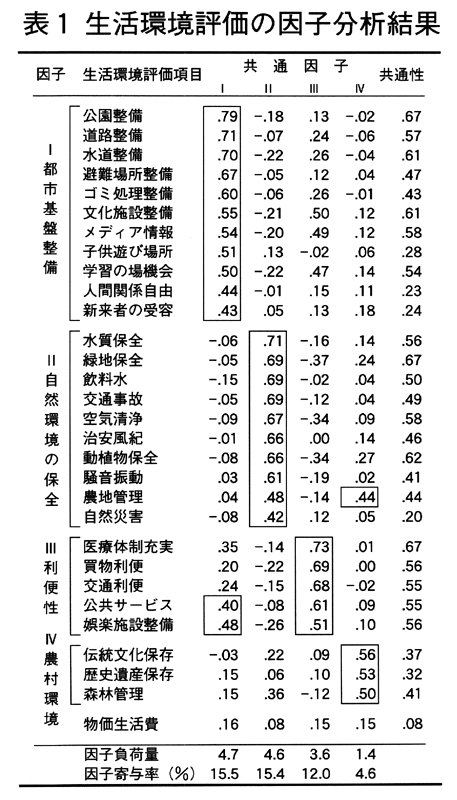
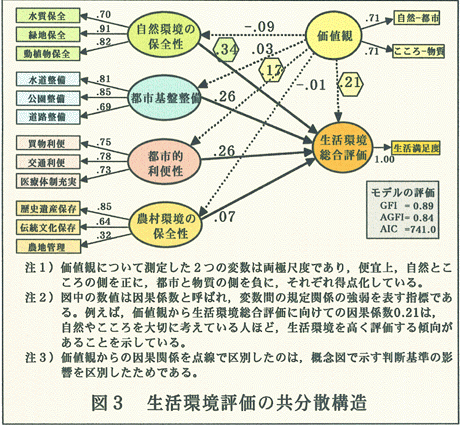
その他
- 研究課題名:評価者の個人特性と環境特性とを考慮した生活環境評価手法の開発
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成9年度(平成7年~9年)
