ディスク駆動式汎用型不耕起播種機で播種した大豆と小麦の収量と根系
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
農業研究センターで開発したディスク駆動式汎用型不耕起播種機により水田転換畑で大豆および小麦を不耕起栽培すると収量は耕起栽培と同等となる。不耕起栽培では大豆の根系は浅く、小麦の根量は少ない。
- 担当:農業研究センター・プロジェクト研究第1チーム
- 連絡先:0298-38-8512
- 部会名:総合研究,作物生産
- 専門:栽培
- 対象:豆類,麦類
- 分類:研究
背景・ねらい
大豆・小麦の二毛作限界地帯において、不耕起栽培は作物切り替え時期の作業競合の緩和に有効である。最近、農業研究センターは稲、麦、大豆に共用できる精度の高い不耕起播種機を開発した。そこで、土壌型の異なる茨城県内の3カ所の水田転換畑で4年間、大豆タチナガハと小麦バンドウワセを不耕起栽培し、その収量と根系の特徴を調べる。
成果の内容・特徴
- ディスク駆動式汎用型不耕起播種機はトラクタ牽引型で、強制回転するディスクでY字型の溝を切り、溝内に播種する。耕起区と不耕起区を設け、耕起区はロータリで耕起した後に同じ不耕起播種機で播種した。出芽密度は1m2あたり大豆で25個体、小麦で250個体を目標としたが、不耕起区の出芽は大豆では17.0~26.1本/m2、小麦では170~250個体/m2となり、各年とも耕起区と同等であった。
- 不耕起栽培した大豆の収量は平均367g/m2で、耕起栽培の102%であった。また、小麦は不耕起栽培の収量平均が586g/m2で、耕起栽培の99%であった。すなわち、不耕起栽培の大豆、小麦とも耕起栽培と同等の収量を得た (表1)。
- 大豆では、全体の根量は両区でほぼ同等である。不耕起区では浅い層の根が多く、根系全体の平均的な深さを示す「根の深さ指数」は、耕起区に比べて不耕起区で小さい。一方、不耕起区の小麦は、耕起区に比べて根量が少ない。小麦の場合、「根の深さ指数」は両区でほぼ同等である (図1)。不耕起栽培した小麦の根量が少なく、根系が浅くならないのは、冬期に降雨が少ないためではないかと推測できる。
成果の活用面・留意点
- 大豆、小麦とも条間30cmで得た結果である。
- 供試圃場の不耕起継続期間は1~2年である。不耕起栽培では雑草の発生が多くなる場合があるため、不耕起継続期間は2~3年が適当と考えられる。
具体的データ
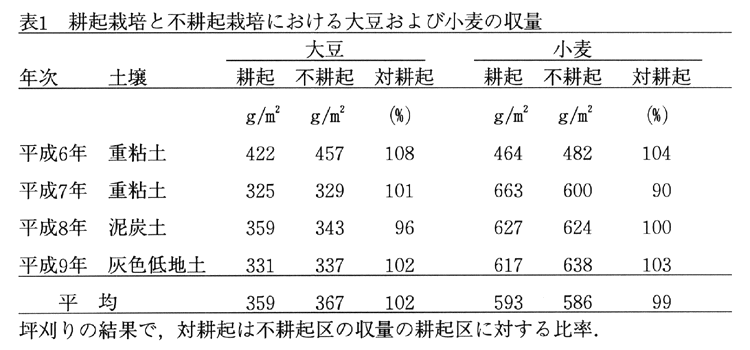
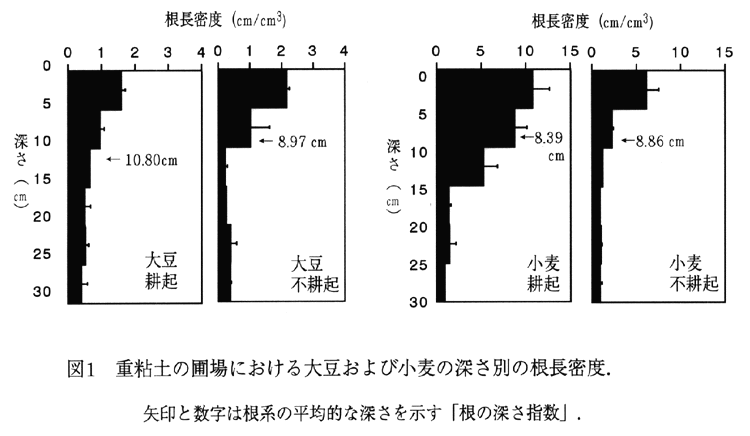
その他
- 研究課題名:二毛作限界地帯におけるミニマムティレッジを基幹とする水田輪作営農技術体系の確立
- 予算区分:総合的開発(新用途畑作物)
- 研究期間:平成9年度(平成8年~10年)
