連・輪作されただいず及びかんしょの根圏土壌細菌群集の変動
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
連作障害が発生した時の作物の根圏土壌細菌群集の多様さを、BIOLOG細菌同定システムで評価することができる。連作障害が発生した場合は、根圏土壌細菌群集の多様性は低くなるが、障害が顕在化しない場合には、多様性にも大きな違いは見られない。また、作物の連・輪作等の耕地管理が土壌の生物性に与える影響を土壌細菌を指標にしてより客観的に解析できる。
- 担当:農業研究センター・プロジェクト研究第2チーム
- 連絡先:0298-38-8840
- 部会名:総合研究,作物生産,生産境環
- 専門:栽培,土壌
- 対象:豆類,いも類
- 分類:研究
背景・ねらい
畑作物の高収益安定生産を確立するためには耕地環境の的確な診断・評価に基づくきめ細かな作付体系を組む必要がある。これまで、土壌の物理性や化学性の簡便な診断法や評価法は確立されてきているが、生物性に及ぼす作付体系の評価法はほとんどみあたらない。そこで横山の炭素源利用能に基づいた土壌細菌集団の多様性迅速評価法(平成6年度、研究成果情報、総合農業)を利用して、連・輪作による土壌細菌の変動を多様性指数で示し、それで土壌の生物性を評価しようとした。また、炭素源利用能の違いから連・輪作が土壌細菌の変動に及ぼす影響を解析した。
成果の内容・特徴
- 連作されただいずは1996年よりダイズシストセンチュウによる連作障害が見られ、精子実重は輪作されただいずに比べ減収した(図2)。一方、連作されたかんしょの収量は、輪作されたかんしょの収量と同程度で連作障害は見られなかった(1997年)。
- 収穫一ヶ月前に作物の根圏土壌細菌群の多様性を算出した(図1)。連作されただいずの根圏土壌細菌群集の多様性は、輪作されただいずに比べ明らかに低く(1996、1997年)、また、相対的に類似の土壌細菌群集が集積している傾向が認められた(図2)。連作、輪作間で生育・収量の差が認められなかったかんしょの土壌細菌群集の多様性は、両者にはほとんど違いはみられなかった(1997年)。
- 1996年に連・輪作されただいずの土壌細菌について比較検討した(図3、表1)。非根圏土壌細菌に関して、輪作されただいずでは全てのクラスターで見受けられたのに対し、連作されただいずでは、A、E、Jのクラスターで認められなかった。一方、根圏土壌細菌に関して、連作されただいずではGのクラスターに占める割合が高く、輪作されただいずでは、Fに占める割合が高かった。FとGとはクラスターが大きく離れていることから、作付様式によってだいず根圏はかなり種類の異なった土壌細菌相になっていることが窺えた。
成果の活用面・留意点
- 本法で使用した機種は、BIOLOGマイクロステーションである。
- 本法では、同定目的ではなく無作為に分離した50菌株の資化性パターンの多様さから母集団の細菌群集の多様性を評価するために利用した。
- 未同定細菌の細菌学的性質の蓄積につながり、将来的な分類研究に利用されることになる。
- 根圏土壌細菌の多様性の値から作付体系を的確に評価していくためには、さらに、各種作物の連・輪作における土壌細菌のデータを収集していく必要がある。
具体的データ
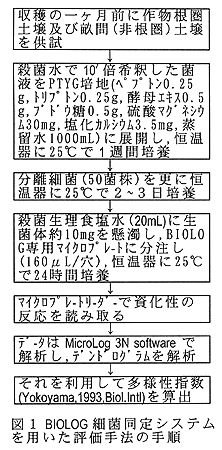
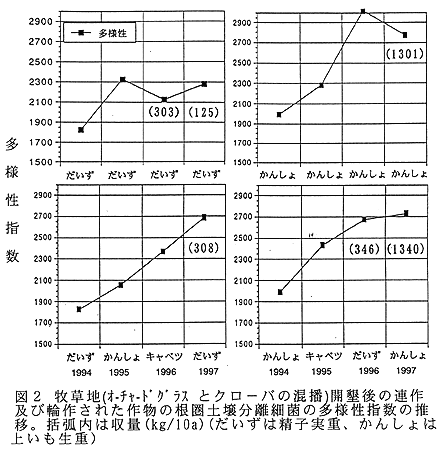
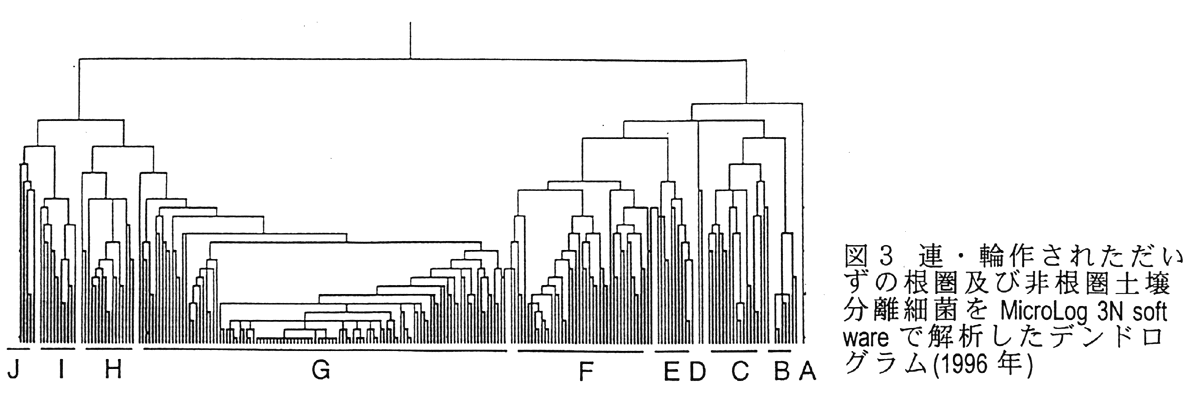
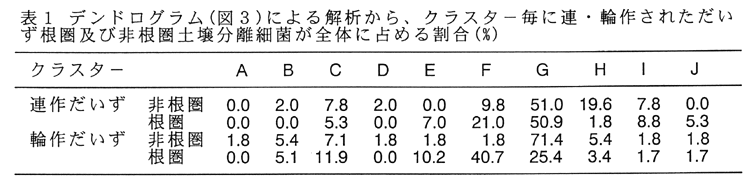
その他
- 研究課題名:土壌の微生物性に基づく輪作体系評価手法の開発
- 予算区分:高収益畑作
- 研究期間:平成9年度(平成7年~9年)
