良食味米の販売量拡大を図る生産者のマーケティング戦略
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
北陸地域において,生産者自身が良食味米を中心とした販売量の拡大を図るためには,生産者間で製品コンセプトに基づいた提携関係を構築するとともに販売ルートの多様化を図ることが重要なマーケティング戦略となっている。
- 担当:北陸農業試験場・総合研究部・農業経営研究室
- 連絡先:0255-26-3231
- 部会名:営農・作業技術
- 専門:経営
- 対象:水稲
- 分類:指導
背景・ねらい
特別栽培米制度,新食糧法の制定を経て,北陸地域ではコシヒカリに代表される良食味米産地の優位性を活かし,米を自ら販売する生産者が増えている。そこで,生産者が実践している米マーケティング戦略を整理し,販売量を拡大するための方策を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 生産者自身が米を販売し,経営形態の異なる4事例のマーケティング戦略をマーケティングミックスの視点によって整理すると次のような傾向がみられる(表1)。
1)製品戦略:食味向上及び安全性を重視した栽培方法が導入されている。また,品種や栽培方法による米の複数品目化と,その他の商品の品揃えも拡充する動きがみられる。 2)価格戦略:生産費補償やブランドを重視して高価格に設定しているものと,市場価格を参考にして価格を変動させているものがある。 3)流通戦略:特別栽培米段階では個人客への宅配便を利用した直販がほとんどであったが,卸業や小売り及び業務用への販売ルートの多様化が図られている。 4)販売促進戦略:広告による効果は低く,口コミ,パブリシティの効果が大きい。 - 販売量を拡大する上で,経営面積の制約を打破するためには生産者間で提携を図ることが有効な方策となっている。この場合,特に製品戦略と流通戦略が重要である。 1)提携関係の構築には,交友関係と製品コンセプトが重要な要因となっている(図1)。当初の提携関係は,B社やCグループのように交友関係や地域(同一市町村程度の範囲)といった信頼関係の強い範囲から始められる。このため,販売量の拡大には限界がある(2)。この限界を打破し,多くの生産者が参加できるようにするためには,A社のように厳格な製品コンセプトに基づく製品戦略によってビジネス的関係を構築することが必要である(1)。このビジネス的提携によって組織の拡張性は高くなり,販売量を大幅に拡大することが可能となる。また,提携相手がいない場合はD経営のように規模拡大による対応となる(3)。 個人顧客が伸び悩む傾向に対して,比較的大口の取引が可能な卸業,小売り及び業務用が重要な販売ルートとなっている。販売ルートの多様化を図る流通戦略は,提携後も販売実績を確保し,販売リスクを分散させるために重要である。
成果の活用面・留意点
- 米の販売量拡大を図る生産者に対して,マーケティング戦略策定を指導するための基礎資料となる。
具体的データ
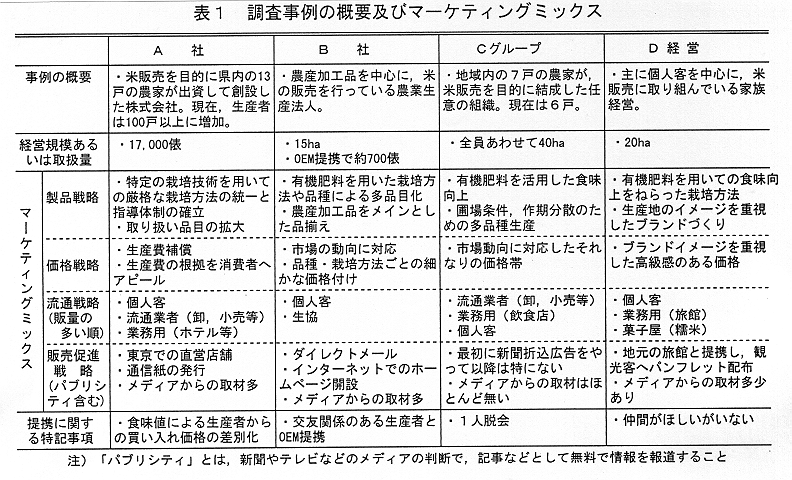
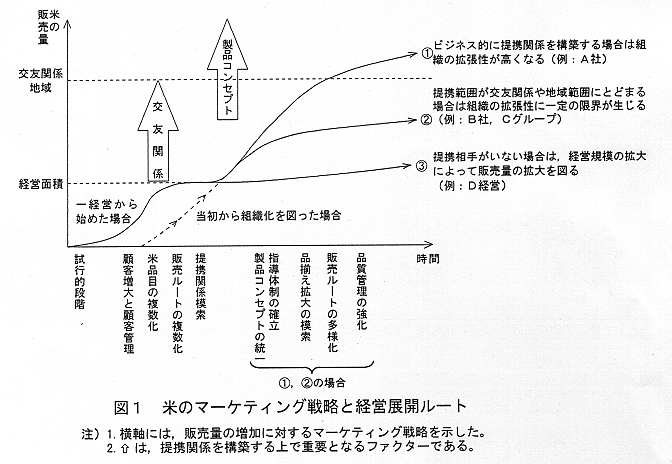
その他
- 研究課題名:大規模稲作経営における米のマーケティング戦略の解明
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成10年度(平成7~10年度)
- 発表論文等:北陸地域の先進事例にみる米のマーケティング戦略と経営展開,農業研究センター経営研究第34号,15-26,1996.6
