可搬型装置で測定したダイズとトウモロコシ圃場からの亜酸化窒素の揮散
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ダイズ圃場からの亜酸化窒素放出速度は、トウモロコシ圃場より高く、根粒非着生系統からの放出量も多い。トウモロコシ圃場からの亜酸化窒素の揮散は降雨直後に高まるが、大豆圃場からは降雨に関わりなくそれを上回る亜酸化窒素が放出される。
- 担当:農業研究センター・作物生理品質部・豆類栽培生理研究室
- 連絡先:0298-38-8392
- 部会名:作物生産
- 専門:栽培
- 対象:豆類
- 分類:研究
背景・ねらい
亜酸化窒素(N2O)は地球温暖化ガスとして大気への放出量の低減が求められている。ダイズには強力な還元能を持つ根粒があり、根圏には脱窒作用をもつ根粒菌が生存していることが知られている。このためダイズの根圏域にある硝酸態窒素が還元さ れ、その一部がN2Oとして放出される可能性がある。そこで、ダ イズ圃場からのN2Oの放出量が普通作物より多いのかどうかを見るために、トウモロコシとの比較のうえで明らかにしようとした。また、現在、一般的に使用されている放射性同位元素をガスのイオン化エネルギー源とする電子捕獲検出器(ECD)は、「放射性物質取扱管理規則」により設置や野外搬出が不可能ため、設置や測定現場への移動が可能な非放射性同位元素型検出器を用いるN2O測定も検討した。
成果の内容・特徴
- 8月に乾燥の続いた1997年に測定した圃場からのN2O放出速度は、ダイズの方が常に高い値を示 した。ダイズの中では根粒着生ダイズよりも、非着生ダイズの方が高い価を示した( 図1 )。
- 7kgN/10aの追肥のN2O放出速度への影響は、トウモロコシではあまり大きくなかったが、ダイズでは明らかに認められ、とくに根粒肥着生系統で顕著であった(図2)。
- 1998年の測定では、ダイズのN2O放出速度は測定期間を通じて前年より著しく高かった。トウモロコシ圃場では降雨直後にN2O放出速度が高くなっていたが、それ以外の時期には放出速度は極めて低かった(図3)。大豆圃場からのN2O放出速度に2か年で著しい差があったのは、測定開始前8週間の土壌水分の動きに差が大きく、1997年には蒸発量が降水量より多く、1998年には大幅に降水量が蒸発量より多く(表1)、土壌水分に大きな差があったためと思われる。
- このように、N2O放出速度の水準は土壌水分で変動するが、大豆圃場からはトウモロコシ圃場よりも常に多くのN2Oが放出されている。
- パルス放電型イオン化検出器(PDD)を利用した非放射線型N2O測定装置は、最低検出感度も約11.6ppbv/vで、空気中のN2O濃度(310ppbv/v程度)測定に十分使用可能である。
成果の活用面・留意点
- この結果は比較的通気の良い火山灰土壌での値であり,土壌の種類により値は異なると考えら れる。
具体的データ
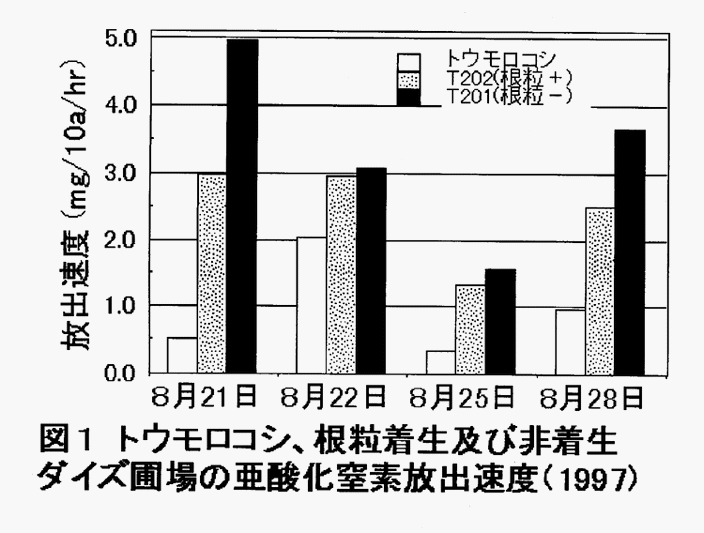
図1:トウモロコシ、根粒着生及び非着生ダイズ圃場の亜酸化窒素放出速度(1997)
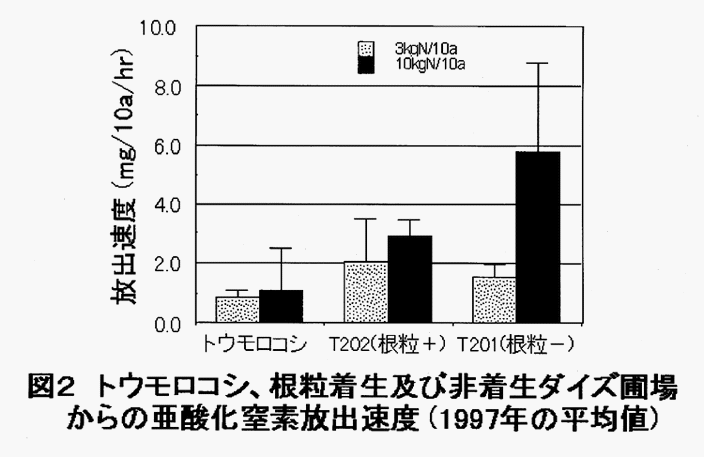
図2:トウモロコシ、根粒着生及び非着生ダイズ圃場からの亜酸化窒素放出速度(1997年の平均値)
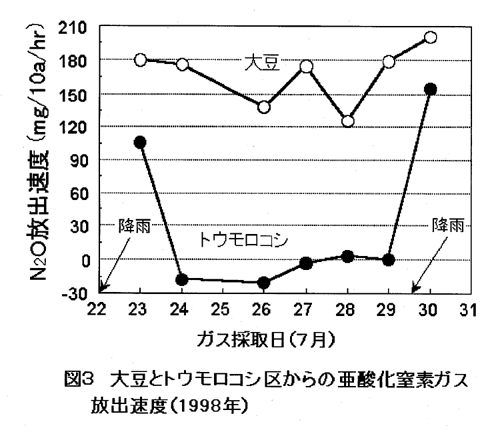
図3:大豆とトウモロコシ区からの亜酸化窒素ガス放出速度(1998年)
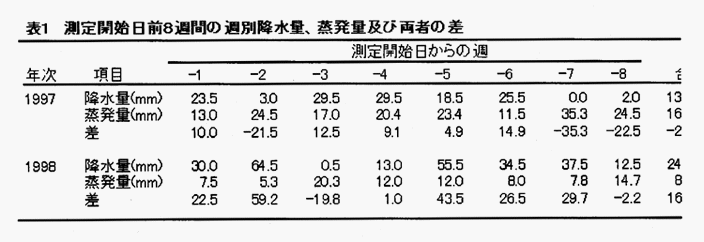
表1:測定開始日前8週間の週別降水量、蒸散量及び両者の差
その他
- 研究課題名:ダイズ根系機能を活用した土壌窒素循環効率の向上技術の開発
- 予算区分 :大型別枠[新需要創出]
- 研究期間 :平成10年度(平成10~12年度)
