鹿沼土・ゼオライト併用バイオジオフィルター水路による窒素・リンの効率的除去
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ヨウサイ、さといも、パピルスなどを栽植した鹿沼土、ゼオライト濾材併用バイオジオフィルター水路は、合併処理浄化槽処理水を全窒素と全リンの平均負荷量 1.35と0.34gm-2d-1で供給すると、夏期には流出水の全窒素、全リン濃度を0.31mgL-1と0.22mgL-1まで浄化できる。
- 担当:農業研究センター・土壌肥料部・水質保全研究室
- 連絡先:0298-38-8829
- 部会名:生産環境
- 専門:環境保全
- 対象:
- 分類:指導
背景・ねらい
生活排水中の全窒素(T-N)、全リン(T-P)は、霞ヶ浦など閉鎖性水域の水質汚濁の主要原因物質となっている。水質保全研究室では、排水中の窒素、リンを資源として有効利用するため、有用植物と天然鉱物濾材を組合せ、植物の養分吸収機能、濾材の吸着・濾過機能及び付着微生物の浄化機能を有効に利用でき るバイオジオフィルター水路(0.4×19.5×0.4Hm、2系列、以下BGF水路と略す)を用いた農山村向きの資源循環型水質浄化システムの開発を進めている。
成果の内容・特徴
- ゼオライトを濾材とした水生植物水路の夏期(6~9月)の流出水の平均T-P濃度は 3.61mgL-1で 、流入したT-Pの57.7%しか除去できなかった( 表1 )。
- 水路流入口から7.3mまで鹿沼土(384kg)、7.3mから14.6mまでゼオライト濾材を充填した水生 植物水路の夏期の流出水の平均T-P濃度は0.22mgL-1で、T-Pの除去率は98.0%に向上した( 表2 )。
- 鹿沼土濾材を用いた水生植物水路(1997年8月)では、合併処理浄化槽処理水が水路内を4.88m 流下する間に、T-P濃度は6.78mgL-1から1.68mgL-1に低下し、ゼオライトに比べると鹿沼土濾 材は、効率よくT-Pを除去できることが判明した( 図1 )。
- 鹿沼土・ゼオライト併用水生植物水路の8月と9月の流出水の平均T-N・T-P濃度は、それぞれ 0.29mgL-1と0.03mgL-1以下になり、湖沼 の水質基準値(類型III、T-N:0.4mgL-1、T-P:0.03 mgL-1以下)よりも低いレベルにまで浄化でき た( 表2 、 表3 )。
成果の活用面・留意点
- 本試験は、粒径3~6mmの選別鹿沼土を1996年10月14日に充填後、合併処理浄化槽処理水を1日 当たり400~500L供給(滞留時間 約2.5日)した際の夏期の浄化成績をとりまとめたものである。現在も、引き続き調査を実施 しているが、少なくとも2年間は、リンの浄化効果が認められ る。
- 浮遊物質濃度の高い汚水を供給すると濾材の目詰まりが生じ、BGF水路の水質浄化機能が低下 することがある。
具体的データ
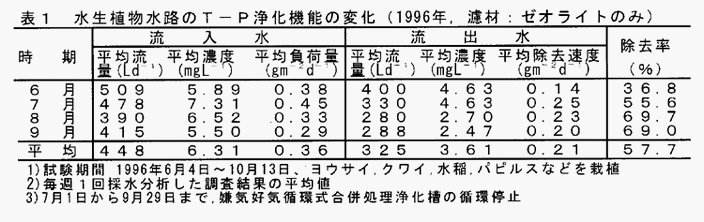
表1:水生植物水路のT-P浄化機能の変化(1996年,濾材:ゼオライトのみ)
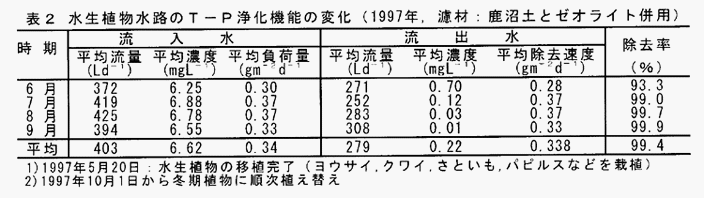
表2:水生植物水路のT-P浄化機能の変化(1997年,濾材:鹿沼土とゼオライト併用)
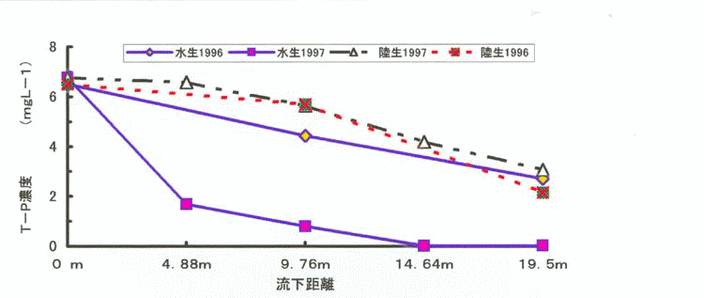
図1:BGF水路流下に伴うT-P濃度の変化(1996年8月と1997年8月の比較)ー水生1997は、水路流入口から7.3mまで鹿沼土濾材、他はすべてゼオライト濾材ー
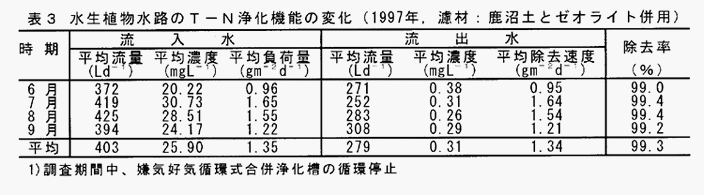
表3 水生植物水路のT-N浄化機能の変化(1997年,濾材:鹿沼土とゼオライト併用)
その他
- 研究課題名:有用植物と濾材を組合せた資源循環型水質浄化システムの開発
- 予算区分 :公害防止「水質浄化」・経常
- 研究期間 :平成10年度(平成8~12年)
