関東東海地域の麦作におけるカラスムギ,ネズミムギの発生実態
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
関東東海地域の麦作でカラスムギの被害が著しい地域が茨城県,埼玉県にある。また静岡県にはネズミムギ(イタリアンライグラス)の被害が著しい地域があ る。両種の被害は畑麦,水田転作圃場で高く,その蔓延には飼料作,堆肥,緑化資材からの逸出ならびに畑条件での麦の連作などが関与すると考えられ,同様の立地では今後被害が拡大する危険がある。
- 担当:農業研究センター・耕地利用部・畑雑草研究室
- 連絡先:0298-38-8426
- 部会名:作物生産
- 専門:雑草
- 対象:雑草類
- 分類:指導
背景・ねらい
関東・東海地域の麦作において近年,カラスムギやネズミムギ(イタリアンライグラス)が防除困難な雑草として報告され,その対策について各県から強く要望 されている。的確な防除手段確立の資料とするため,アンケートおよび現地調査で両草種の分布および発生実態を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 平成8年産4麦合計作付面積が100ha以上の関東東海地域の農業改良普及センター管区60ヶ所を対象に,両種の発生状況,発生圃場の前歴・特徴,蔓延に 関与する要因などについてアンケート調査した結果,両種の存在は全県で確認され,回答した管区の約半数がいずれかの種を麦作の雑草と認識していた(図1,図2)。
- カラスムギでは茨城,埼玉(図1),ネズミムギでは埼玉,静岡(図2)で特に被害が著しい管区があり,麦の収穫放棄・次作断念に至ることもある。ただし,被害の著しい地域においても両種の発生圃場の割合は最大で数~20%と見積もられる。
- アンケート結果によれば,両草種ともに,畑麦および水田転作圃場で発生程度が大きくなる傾向にあり,水稲-麦の体系では被害程度は小さい(表1)。また,飼料作や堆肥,畦畔・法面への緑化資材が発生源として,麦類の連作と機械による種子の拡散といった要因が蔓延に関与すると考えられる要因として多く挙げられている(図3)。
成果の活用面・留意点
- カラスムギ,ネズミムギの発生実態の把握および防除対策に関する基礎資料として活用される。
- カラスムギ種子は夏期の湛水条件下で死滅することが知られている。今後,転作の固定化等で発生に好適な条件が増加する場合は被害が拡大する可能性がある。
- 発生源,蔓延要因については今後,草種・事例ごとに解明が必要である。
具体的データ
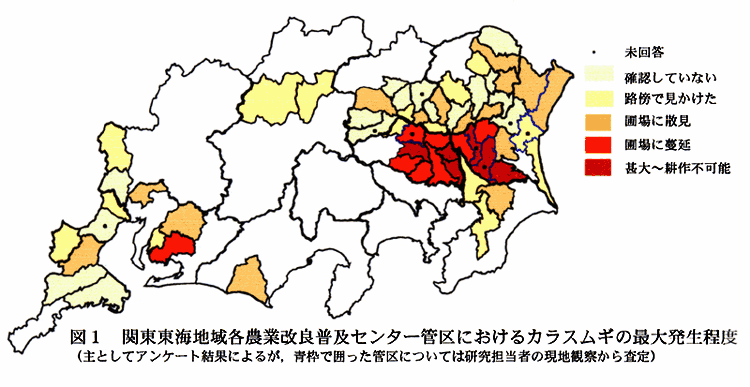
図1:関東東海地域各農業改良普及センター管区におけるカラスムギの最大発生程度
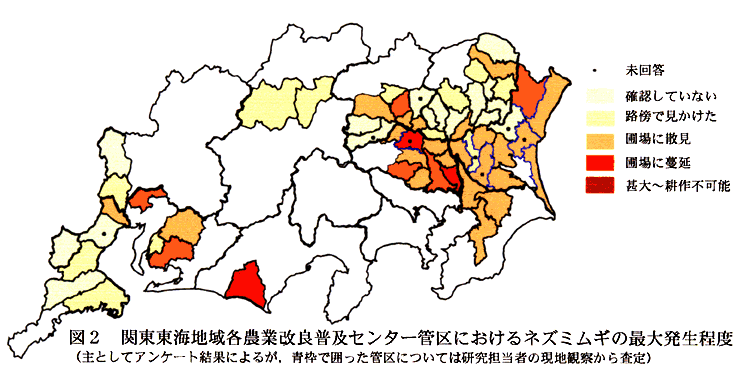
図2:関東東海地域各農業改良普及センター管区におけるネズミムギの最大発生程度
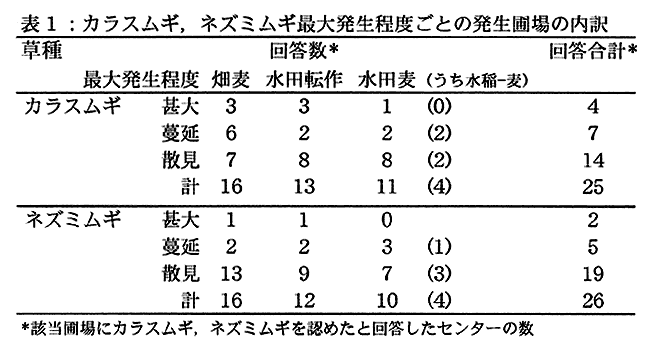
表1:カラスムギ,ネズミムギ最大発生程度ごとの発生圃場の内訳
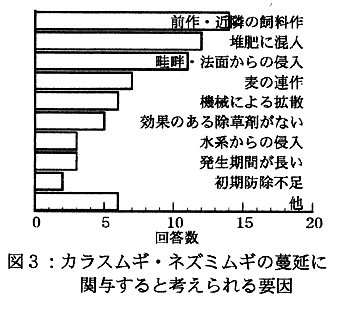
図3;カラスムギ,ネズミムギの蔓延に関与すると考えられる要因
その他
- 研究課題名:麦作における強害イネ科雑草の発生実態と防除技術の確立
- 予算区分 :経常・特別研究「麦緊急開発」
- 研究期間 :平成11年度(平成10~13年)
