滞在型クラインガルテンによる村おこし効果
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
都市・農村交流の1形態である滞在型クラインガルテンの導入は、農村に居住する人々の明確なコンセプトと都市民との農的活動による共生を通して、双方の活力の向上および村おこしへ向けた発想や価値観を醸成し、新しいコミュニティーの形成に効果を及ぼす。
- 担当:農業研究センター・農業計画部・地域計画研究室(農業工学研究所・農村計画部・地域計画研究室)
- 連絡先: 0298-38-7548
- 部会名: 経営,総合研究
- 専門: 農村計画
- 分類: 指導
背景・ねらい
農村と都市交流のうち、都市民が農村に定住・半定住あるいは時々滞在し、地元の人々(農村民)と相互に補足しあう生活を営む状態を共生と呼ぶ。その 共生の対象事例として、10年近く継続調査をしている、平成5年から滞在型クラインガルテン(市民農園の1形態)を導入した長野県四賀村で、「ガルテナー (時々滞在・半定住の都市民)」25人と「ガルテナーを支援する地元の人々(農村民)」23人の調査を行い、両者の意識及びものの見方の変化について、他 の調査事例を踏まえながら考察し、村おこしの効果を明らかにした。
成果の内容・特徴
- 農村民と都市民の間で共生関係が認められる5事例(図1の (4)を参照)には、共通して(1)農村塾、市民農園、田舎風の住まい、たくみによる郷土の伝統技術学習など、農業・農村を中心に置く活動があり(これら を農的活動と呼ぶ)、(2)その下で、異なる生活感からみた田園価値の再認識・発見が、相互の活力(元気さ)の高揚に波及している。
- 四賀村では、当初、都市側の消費団体の働きかけにより有機農産物づくりが始まり、クラインガルテンの導入後本格化した。これを契機に双方の活力向上が促さ れ、有機農産物づくりに対する見方の変化を通し、新しいコミュニティーの形成にも作用するなどの意識の変化が認められた(表1参照)
- 同村では、リーダーの発想が村内の有志を動かしクラインガルテンの導入につながっている。村の村おこし方針として取り組んだガルテンの有機栽培が都市民の意識を変えながら、農村民の意識の変化に波及し、暫時、その変化が村民に拡大するという過程をたどっている(図2参照)。
- クラインガルテンを中心とした農村民と都市民によるコミュニティーの形成は、双方の異なる価値観やものの見方が村おこしへ向ける考え方や対応の相互作用に反映され、農業や農村文化、生活環境、生活感、健康意識などに対する価値の共有化をもたらす効果を見せている(図2の下段参照)。
成果の活用面・留意点
四賀村では、クラインガルテンの導入が地域づくり戦略として有効に機能しているがその村おこし効果を高めるには、村をあげた有機農産物づくりや農的活動を含む農村側の明確なコンセプト(=村おこしの方針)が不可欠である。
具体的データ
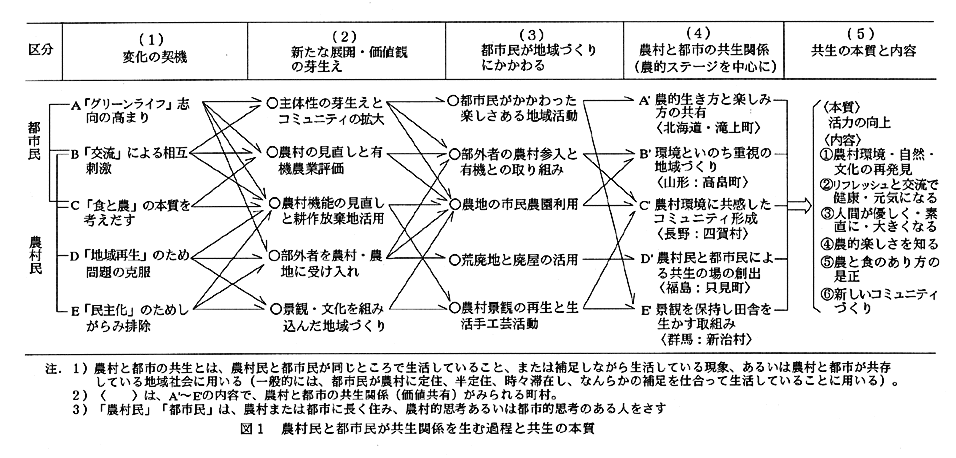
図1:農村民と都市民が共生関係を生む過程と共生の本質
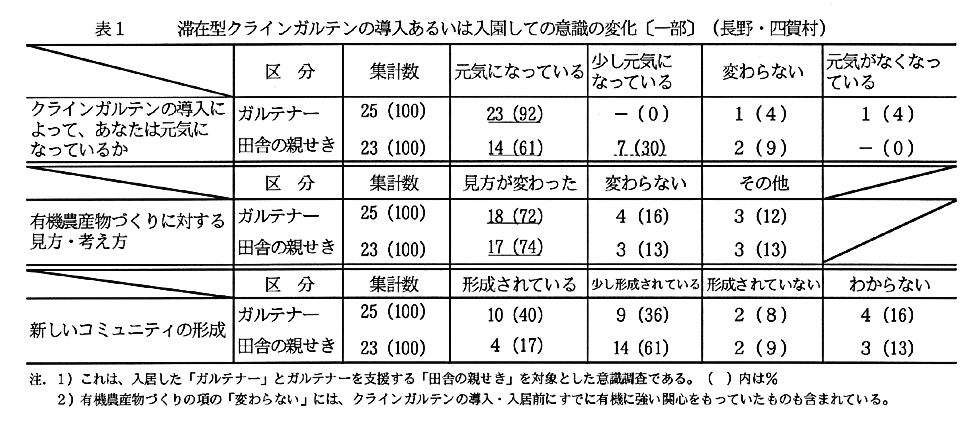
表1:滞在型クラインガルテンの導入あるいは入園しての意識の変化〔その一部〕(長野・四賀村)
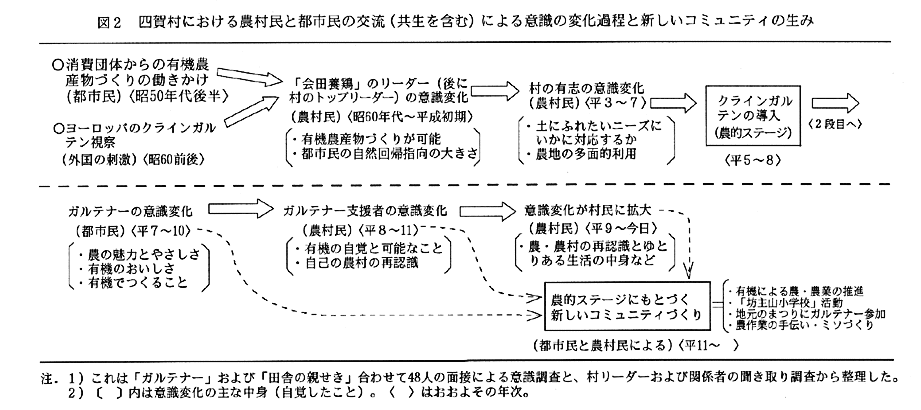
図2:四賀村における農村民と都市民の交流(共生を含む)による意識の変化過程と新しいコミュニティの生み
その他
- 研究課題名:地域づくりにおける農村と都市の共生関係の解明
- 予算区分 :経常
- 研究期間 :平成12年度(平成11~13年)
