東南アジアにおける水稲直播栽培の普及に関する比較考察
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
東南アジアの主要灌漑稲作地帯における直播栽培の普及は,労働力の賦存条件と移植との収量差が主要な要因となって進展した。普及の程度は,農村労働力の多寡との関係がみられた。
- 担当:農業研究センター・経営管理部・比較経営研究室(中央農業総合研究センター・経営計画部・耕種経営研究室)
- 連絡先: 0298-38-8876
- 部会名: 経営
- 専門: 経営
- 対象: 稲類
- 分類: 研究
背景・ねらい
本研究では,東南アジアの主要灌漑稲作地帯である,マレーシア(ムダ灌漑計画地帯),ベトナム(メコンデルタ),フィリピン(中央ルソン平原),タ イ(中央平原)の現地調査を中心に,そこでの直播栽培の普及実態を調べ,各国の稲作経営の特徴から直播普及要因について比較考察した。
成果の内容・特徴
- 対象とした東南アジア各国の中で,最も直播栽培の普及している国は1980年代の初頭から直播が導入・普及されたマレーシアである。他の国の直播普及率は未だ高くないが,メコンデルタ,フィリピン中央ルソンやタイ中央平原では1990年代になり普及がはじまっている。
- マレーシア稲作の特徴は土地・人口比率が低い点で,労働力が寡少な構造にある。当国では,二期作がはじまった1970年時点で既に,農村における労働力不足が懸念されていた。
- 一方,土地・人口比率が高いベトナムでは,土地・人口比率が比較対象とした4国間の中では最も高い。豊富な労働力を利用し労働集約的な管理を要する稲作複 合経営が普及している。ただし,南部のメコンデルタでは,北部の紅河デルタに比較すると経営耕地面積が大きいため,相対的に労働力が寡少であり,直播の普 及がみられている。
- 普及程度の高低にかかわらず,東南アジアの直播の最大の特徴は,移植と同程度の収量水準にある。フィリピンでは水利条件さえ整えば日照時間の多い乾期の直播栽培で5t/ha以上の籾米収量をあげる例もある。
- 以上の点から,労働力賦存状態(土地・人口比率)と移植栽培との収量差の二つの要因が,東南アジアの灌漑稲作地帯における直播栽培の普及の契機になっている。
成果の活用面・留意点
本研究は東南アジアに代表されるわが国近隣諸国の直播の普及事情を知る参考資料として利用することができる。灌漑条件に比較的恵まれた地帯の調査結果であるので,灌漑整備の程度と直播普及との関係を明らかにするためには,天水田地帯等の実態についての精査が必要である。
具体的データ
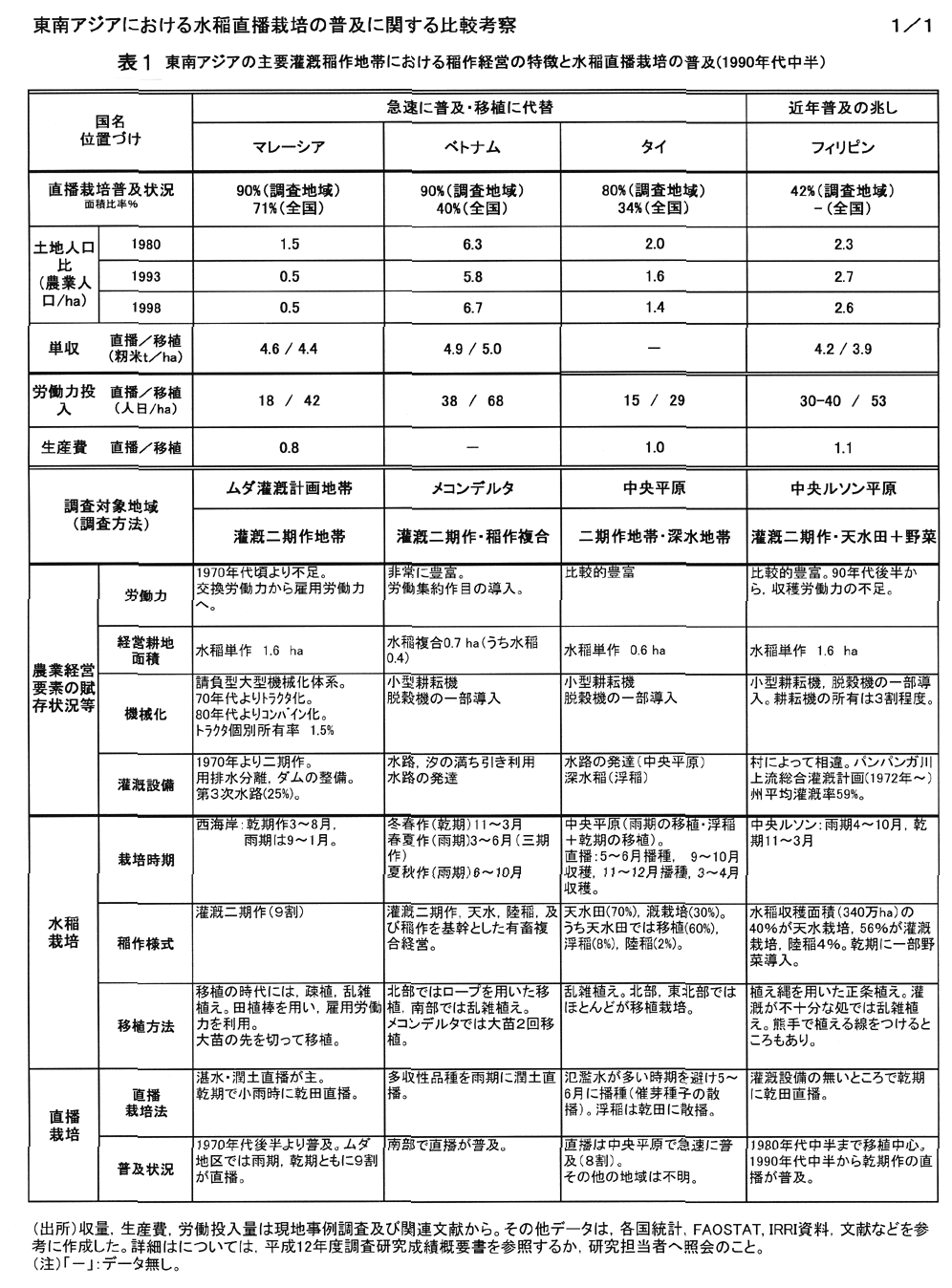
表1:東南アジアの主要灌漑稲作地帯における稲作経営の特徴と水稲直播栽培の普及(1990年代中半)
その他
- 研究課題名:新技術の普及・定着要因の解明
- 予算区分 :経常
- 研究期間 :平成10~12年度
